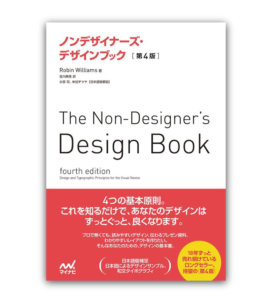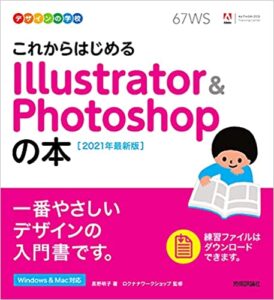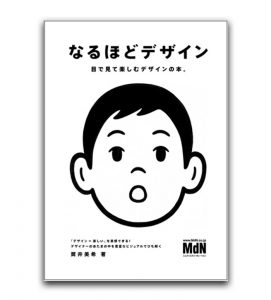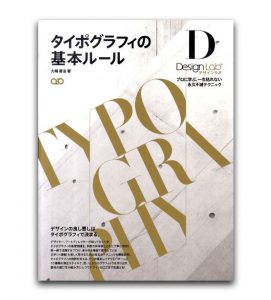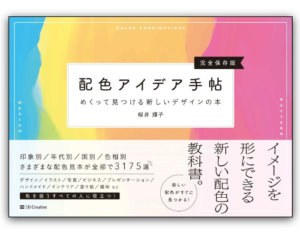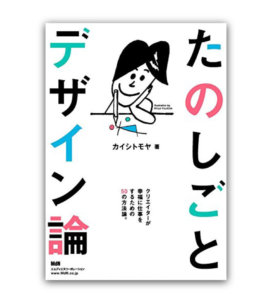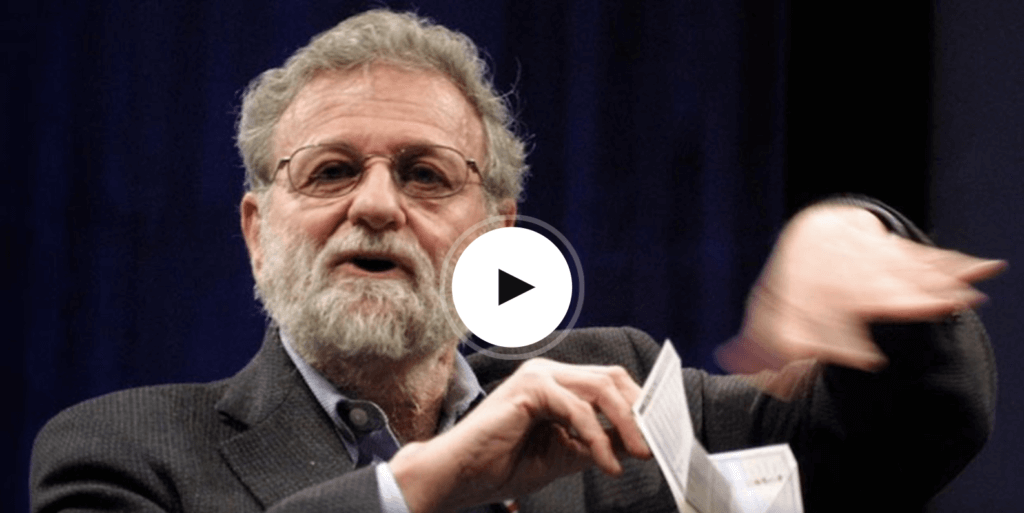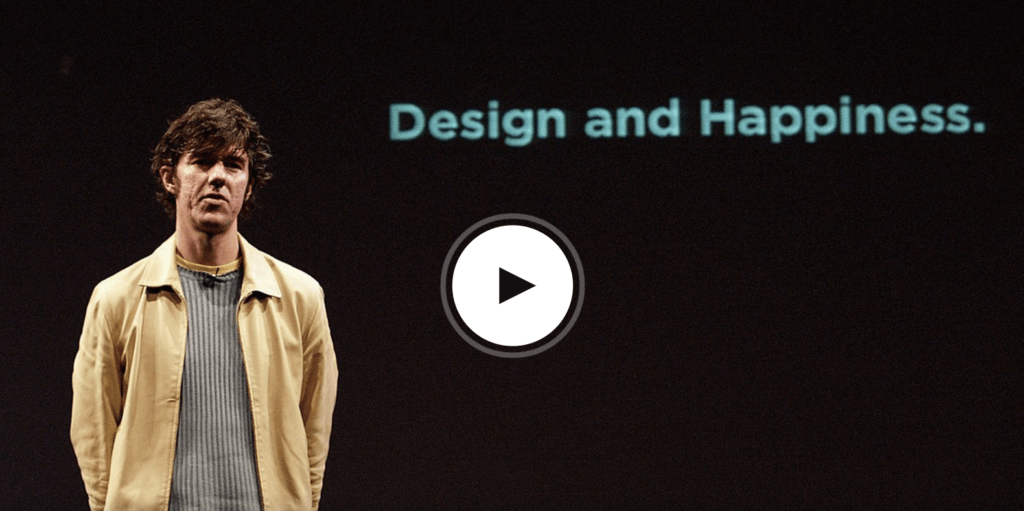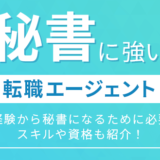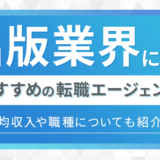結論から言うと、独学でデザインを学ぶ方法はいくつもあります。
ただし、それが故にどうやって学んだらいいか分からないという方も多いでしょう。
そこでこのページでは、独学でデザインを学ぶのに役立つ本やコンテンツを紹介します。
独学でデザインの知識を身につけたい方は、ぜひ参考にしてください。

#この記事を書いた人
グラフィックデザイナー
MOZ
クリエイティブ系専門学校を卒業後、当時はできたばかりのベンチャー企業に就職。グラフィックデザインだけでなく、映像、インタラクションデザインなど幅広く手掛ける。
目次
デザインの基礎を学べる本

ノンデザイナーズ・デザインブック
名前の通り、非デザイナーに向けてデザインのコツを解説した書籍です。日本語版刊行から20年以上売れているロングセラー。
「近接、整列、反復、コントラスト」といったデザインの基本的な4つの原則を学べます。パワポや社内資料、業務マニュアルなどのデザインにすぐ活用できます。
画像が大きめで、なぜこのデザインなのか?箇所ごとに解説されているので分かりやすいです。
名著ですが、デザイン経験がある場合は学びが少ない本なので、デザイン初心者のうちに読んでおきましょう。

これからはじめる Illustrator & Photoshopの本
AdobeのillustratorとPhotoshopの基礎的な知識が身につく本です。シリーズ化されており、現時点(2022年5月時点)ではこちらが最新版となっています。
デザイナーが利用するAdobeのソフトである「illustrator」と「Photoshop」の基礎知識。
初心者が躓きそうな部分を基礎から分かりやすく解説してくれてます。ただし、シンプルに解説している故に経験者にとっては少し物足りないことも。
あくまで初心者向けの本なので、すでに基礎的なことをマスターしている人は読まなくてもいいでしょう。ただし、基礎的なことであっても意外と抜けている知識があるので、ブランクがある人は読んでおくのも有り。

デザインのルール、レイアウトのセオリー。
なぜ、このデザインが魅力的と感じるかが言語化されている本。装丁も美しいです
「レイアウト」「文字組み」「可読性」などデザインの基礎を事例を通して学べます。
1テーマにつき2見開きの構成で、画像が大きいので活字が苦手な人でも簡単に読めます。
kindle版は読みにくいのでおすすめしません。単行本の新品が手に入るところが少ないかも。

なるほどデザイン〈目で見て楽しむ新しいデザインの本。
目で見てなるほどなぁ。と感じられる本。デザインを学ぶ用の書籍というよりも、楽しみながらデザインに触れられる本です。
学びという点ではノンデザイナーズ・デザインブックなどには劣りますが、グラフィック的に見ていて勉強になる部分はあります。
「見て楽しむ」というタイトル通り、ビジュアル多めでサクッと読めます。堅いデザイン書籍が苦手な人向け。
情報量は少なめなので、ガッツリ勉強したいという人には向いていません。

フォント・配色について学べる本
ほんとに、フォント。フォントを活かしたデザインレイアウトの本
フォント選びで迷子にならないための本。どのフォントを使えばいいかわからない。いつも同じフォントを使ってしまうという人におすすめ。
ナチュラル、ゆるい雰囲気など、状況や要望に応じたフォント選びが学べます。
作例多めで気軽に学べます。NG例が掲載されているのもGOOD。
OK例のデザインが微妙と感じてしまうこともあるかもしれません。

タイポグラフィの基本ルール -プロに学ぶ、一生枯れない永久不滅テクニック-
ザ・教科書。文字の基本から代表的な書体まで、タイポグラフィの基礎知識を網羅している一冊です。
デザインと合う文字選びや、ロゴデザインの基本的なテクニック、文字のレイアウト、書体などタイポグラフィの基礎を学べます。
レイアウトが少々読みづらい部分もありますが、表現自体は分かりやすいです。
古い本なので、タイミングによっては入手困難な場合も・・・

配色アイデア手帖 めくって見つける新しいデザインの本
配色見本が大量に掲載されているので、一冊手元にあると便利な本。見ているだけで楽しく、実際の作例などもあるため、実務に活かしやすいです。
配色のアイデアが浮かんだり、色の見方が身につきます。自分でも思いつかないような色の組み合わせに気づくことができます。
どのページも見開き完結で読みやすいです。パラパラめくって見つけやすいのも魅力。
色に関するエッセイなどが、人によっては合わないかも・・・

デザインの考え方や仕事との向き合い方を学べる本
たのしごとデザイン論
アートディレクターのカイシトモヤさんの著書で、辛くなったときにデザインの楽しさを思い出させてくれる本。
仕事としてデザインをする際の楽しみ方。同僚やクライアントの関係の育て方など。
文章自体は平滑で読みやすく、挿絵やラインも引いてあるので重要ポイントだけを読むのも◯
あるあるが結構出てくるので、デザイナーの仕事をしてからの方が楽しめます。

デザイナーになる! 伝えるレイアウト・色・文字の大切な基本と生かし方
グラフィックデザインの仕事のフローや全体像が把握できる一冊です。デザインについて、デザイナーの仕事についてわかりやすく解説されています。
基本知識も学べますが、デザインの心構えが最も参考になります。自分の働き方を見直すために読み返すという使い方もできそう。
画像や図表が多めなので分かりやすいです。解説文が語り口調なので、親しみやすいです。
ある程度デザイナーの知識がある場合は、すでに知っている内容がほとんどになるかもしれません。

グラフィックデザインの独学に役立つ動画(TED)

TED(Technology Entertainment Design)とは、ニューヨークに本部がある非営利団体です。
毎年、世界的な有名人・著名人がプレゼンテーションを行う講演会「TED Conference」を主催しています。
感情に訴えるデザインの3つの要素(ドナルド・ノーマン)
名著「誰のためのデザイン?」の著者で、カリフォルニア大学サンディエゴ校名誉教授・デザイン批評家でもあるドナルド・ノーマン氏のプレゼンです。少々難しいかもしれませんが、デザインとユーザー体験の関係を考える参考になります。
五感に訴えるデザイン(ジンソップ・リー)
「デザイン=見た目が良いもの」と考えがちですが、デザイナーのジンソップ・リー氏は五感に訴えるデザインこそが良いデザインと提言します。視覚だけでなく、五感をフル活用してデザインすることの大切さがわかります。
ハッピーデザインについて(シュテファン・サグメイスター)
「幸せな気分にしてくれるデザイン」についてのプレゼン。引きこもって作業ばかりしてはいけないと気付かされます。
プレゼンがとても面白いので、プレゼンの勉強にもなります。

公式Canvaテンプレートはこちら
グラフィックデザインを独学で学ぶときに挫折しやすいポイントと克服法


ソフト操作が難しくて心が折れそうなとき
IllustratorやPhotoshopは高機能なプロ向けソフト。
起動した瞬間にボタンやメニューが並び、「難しそう…」と感じて挫折する人も少なくありません。


- 最初から全機能を覚えなくてOK
- SNS用の小さなバナーを作るなど、ゴールを絞る
- 模写から始めても十分効果的

インプットだけで終わり、アウトプットが足りないとき
独学の落とし穴は「本を読んで満足してしまう」こと。
知識が頭にあっても、手を動かさなければデザイン力にはつながりません。


- 1冊読んだら必ず作品を1つ作る
- 配色を学んだらSNS画像に応用してみる
- フォントを学んだら既存のチラシを模写して文字を置き換える
- 完成度よりも“手を動かす回数”を優先する
モチベーションが続かないとき
独学は孤独との戦い。
誰にも見られない環境では「今日はやらなくていいか」と先延ばししてしまうこともあります。


- 学習時間は「短く・毎日」を意識(30分でOK)
- 作ったものをSNSやコミュニティで公開する
- 仲間やフォロワーの存在が励みになる
- “誰かに見てもらう環境”を持つことで自然と続けられる

グラフィックデザインのセンスを磨く!独学におすすめの日常インプット習慣


街の広告や雑誌を“教材”として観察する
何気なく目にしている広告や雑誌は最高の教材。
プロのデザインがどう作られているかを意識して観察するだけで、自然と感覚が鍛えられます。


- 広告の「色の組み合わせ」をチェックする
- 雑誌の「文字の余白や整列」を真似してみる
- 同ジャンルの広告を比較して「印象に残る要素」を探す

世界中のデザインをオンラインで収集する
独学におすすめなのが、海外のデザインを気軽に見られるサイト。
Pinterest、Behance、Dribbbleは必ず押さえておきたいプラットフォームです。


- 毎日5分だけ「気になるデザインを保存」
- 保存フォルダを作って整理すると便利
- 「どこに応用できるか」を考えながら眺める
- トレンドの把握に役立つ
アートや展示会からインスピレーションを得る
リアルな体験は、画面越しの学びとは違った刺激を与えてくれます。
美術館や写真展は特におすすめ。


- 写真展で構図を観察 → ポスター制作に応用
- アートの色彩バランス → 配色のアイデアに
- 解説を読むと「作者の意図」も理解できる
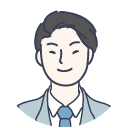

おすすめ記事
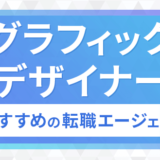 グラフィックデザイナーにおすすめの転職エージェント8選【2025年版】
グラフィックデザイナーにおすすめの転職エージェント8選【2025年版】 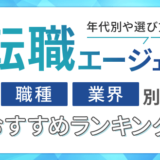 転職エージェントおすすめ53社を徹底比較【2025年】後悔しない選び方も紹介!
転職エージェントおすすめ53社を徹底比較【2025年】後悔しない選び方も紹介!