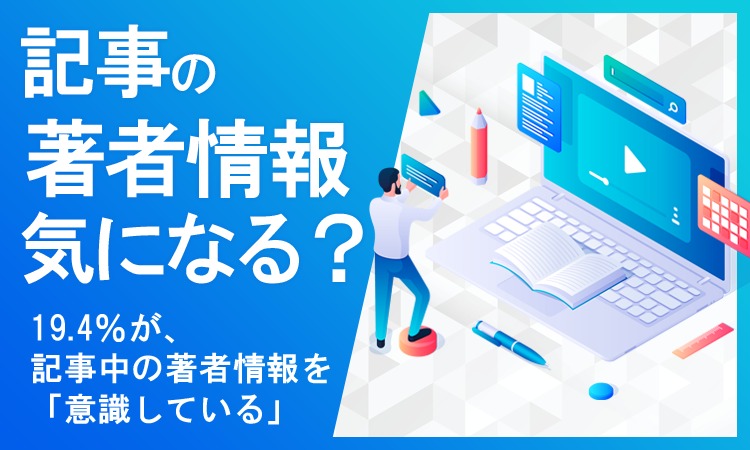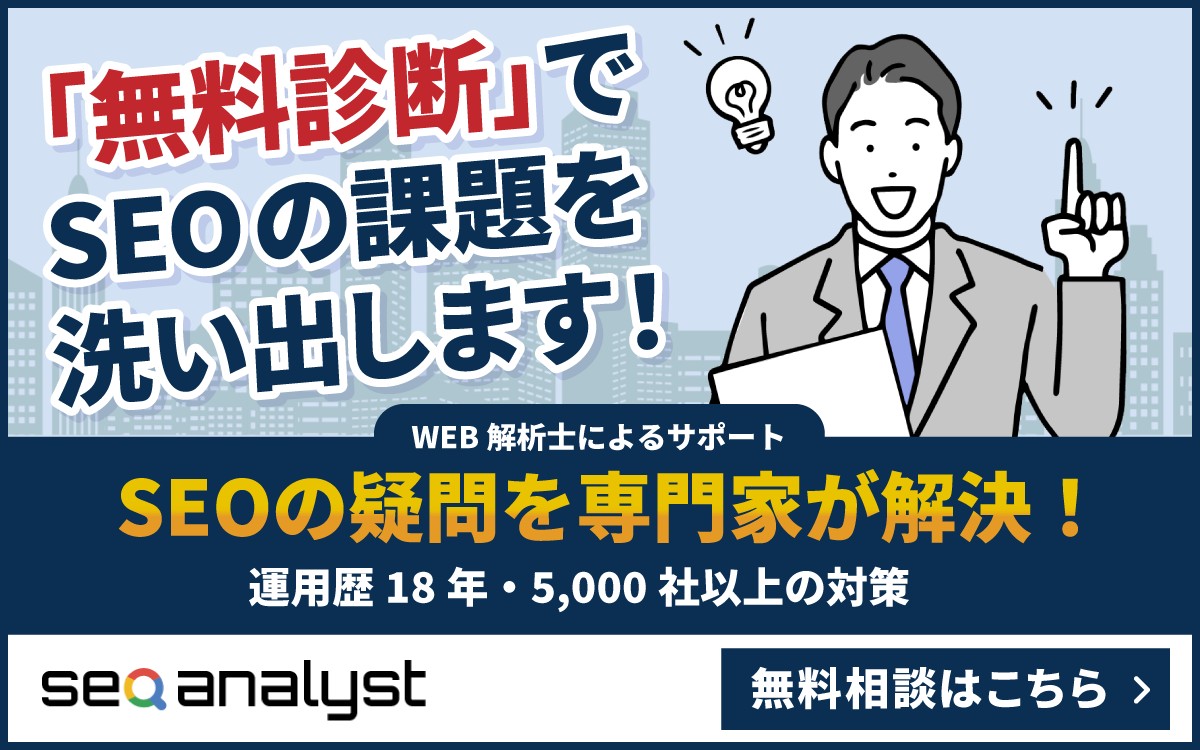この記事の監修SEO会社

株式会社NEXER
2005年にSEO事業を開始し、計5,000社以上にSEOコンサルティング実績を持つSEOの専門会社。
自社でSEO研究チームを持ち、「クライアントのサイト分析」「コンテンツ対策」「外部対策」「内部対策」「クライアントサポート」全て自社のみで提供可能なフルオーダーSEOを提供している。
SEOのノウハウを活かして、年間数百万PVの自社メディアを複数運営。
目次
記事中の著者情報、意識してる?
インターネットで情報を得る際、記事の内容だけでなく「誰が書いたのか」も気にしていますか?
近年、信頼性の高い情報を見極めるために、著者情報を意識する方も増えています。
そこでこの記事では、事前調査で「ネットで記事を見ることがある」と回答した全国の男女500名を対象に「記事中の著者情報」についてのアンケートを実施した結果をまとめました。
| 調査手法 | インターネットでのアンケート |
| 調査対象者 | 事前調査で「ネットで記事を見ることがある」と回答した全国の男女 |
| 調査期間 | 2025年4月4日 ~ 2025年4月14日 | 質問内容 |
質問1:記事中の著者情報を意識していますか? 質問2:その理由を教えてください。 質問3:記事中の著者情報について、当てはまるものを選んでください。 質問4:その理由を教えてください。 質問5:記事中の著者情報が無い場合、記事を読むのをやめることはありますか? 質問6:その理由を教えてください。 質問7:記事中の著者情報にどのような情報があるといいと思うか教えてください。 |
集計対象人数 | 1000サンプル |
約2割が、記事中の著者情報を「意識している」
まずは、記事中の著者情報を意識しているか聞いてみました。

約2割の方が、記事中の著者情報を「意識している」と回答しています。
それぞれ理由を聞いてみたので、一部を紹介します。
- 記事の情報の正確さ、信用に足るものかを判断する要素だから(20代・男性)
- 客観的であるかどうか、感情が入っていないかを確認するためです(20代・女性)
- 変な記事を書く人や、わかりやすい記事を書く人など参考にするため(30代・女性)
- 偏った意見の人の書いた文章を読みたくないから(40代・男性)
- 記事の内容を詳しく調査したりすることはあるが、著者までは普段意識していないため(20代・男性)
- 著者の記載があることを知らないから(20代・女性)
- あまり誰が書いているか気にしてないから(30代・男性)
- 記事を読んだらそのままページを閉じてしまうから(30代・女性)
- 内容にしか興味がないから(30代・男性)
- 意識したことが一度もない。記事をさっと読んで終わっていた(40代・女性)
記事中の著者情報、半数近くが「あったほうがいい」
続いて、記事中の著者情報について、当てはまるものを選んでもらいました。

約半数の方が、記事中の著者情報が「あったほうがいい」と回答しています。
それぞれ理由を聞いてみたので、一部を紹介します。
- 著者が明確でないものは信用できないから(20代・男性)
- 杜撰な内容であるときはその内容を書いた人を知りたいし、逆に素晴らしい内容のときも知りたくなる、応援したくなるから(20代・女性)
- 嘘の記事や誹謗中傷を含む書き方をした場合の特定(30代・男性)
- 記事を書くのに責任が生まれると思うから(20代・女性)
- 責任を果たすために必要だと思うから(30代・女性)
- 記事として書く以上、書く側に内容の責任を持たせるべきだと考える為(30代・男性)
- 特に気にはしていないけど、公に記事を出すならば必要な事だと思うから 時には間違った解釈を与えることもあるかもしれないし、責任として(30代・女性)
- よっぽど必要に感じれば著者の他記事も見て判断することがあるかもしれないが、基本的にそこまで著者に注目した調査はしないため(20代・男性)
- 著者情報をみないから(20代・女性)
- 内容のほうが大事なのでそこまで気にしてはいない(30代・女性)
- 悪い記事や偽りなどがある場合は名前があった方が誰が間違った情報を流しているかはわかりやすいと思うが、そのせいで攻撃に合うのは違うと思うから(30代・女性)
- 知ったからと言って何かアクションを起こす事がないので(30代・男性)
- よほど過激なことを書いていない限り。誰が書いていても気にしない、どうでもいい(40代・男性)
- 見ないから(20代・男性)
記事中の著者情報が無い場合、11%が記事を読むのをやめることが「ある」
続いて、記事中の著者情報が無い場合、記事を読むのをやめることはあるか聞いてみました。

1割以上の方が記事中の著者情報が無い場合、記事を読むのをやめることが「ある」と回答しています。
それぞれ理由を聞いてみたので、一部を紹介します。
- 怪しいし読んでも信じられないから(20代・男性)
- タイトルと中身の乖離が激しいことや課金誘導が激しいことがあるため(30代・男性)
- 経済情報で著者名が無いと、良いことを書いていても、その人の記事を読みたいと思ったときに探せないから(40代・男性)
- 読みたいものであればそれに関わらず読むから(20代・女性)
- 著者よりも中身のほうが大事だと思う(20代・男性)
- そもそも記者の名前を確認してないので、あるのかないのか知らない(30代・女性)
- 気にしたことないから(30代・女性)
- 内容に惹かれて読みたいと思ったから(30代・男性)
- そこまでしっかりとしたソースを求めずに記事は流し読みすることが多いから(30代・女性)
また、記事中の著者情報にどのような情報があるといいと思うかも聞いてみたので一部を紹介します。
- どういった記事を普段書いている人物かを明確にする(20代・男性)
- 一応書いた人の名前と所属か職種(20代・男性)
- 経歴や直近の関連分野記事のリンク(20代・男性)
- どこに所属している人なのかや、インフルエンサーなのか記者なのかなど職業(30代・女性)
- 名前や、どんな資格を持っているか、所属など(30代・男性)
- フルネームと簡単な自己紹介(30代・男性)
著者情報として「名前」「職業」「所属」「資格」「執筆ジャンル」などが明記されていると安心感があるという声が多く見られました。
信頼性や専門性を判断するための手がかりとして重視されているようです。
まとめ
今回は「記事中の著者情報」に関する調査を行い、その結果について紹介しました。
約2割の方が、記事中の著者情報を「意識している」と回答しています。
著者情報を意識する理由としては、「記事の信頼性を判断したい」「偏った意見の人の書いた文章は避けたいから」といった声が多く挙がりました。
今後は読者に安心感を与えるためにも、名前や経歴、所属などの情報開示がより重要になると言えそうです。