AIO・SEO
AIO・SEOブログ
2026年最新|Googleの基準に沿ったSEO対策のやり方と仕組みを解説
2025.11.12 SEO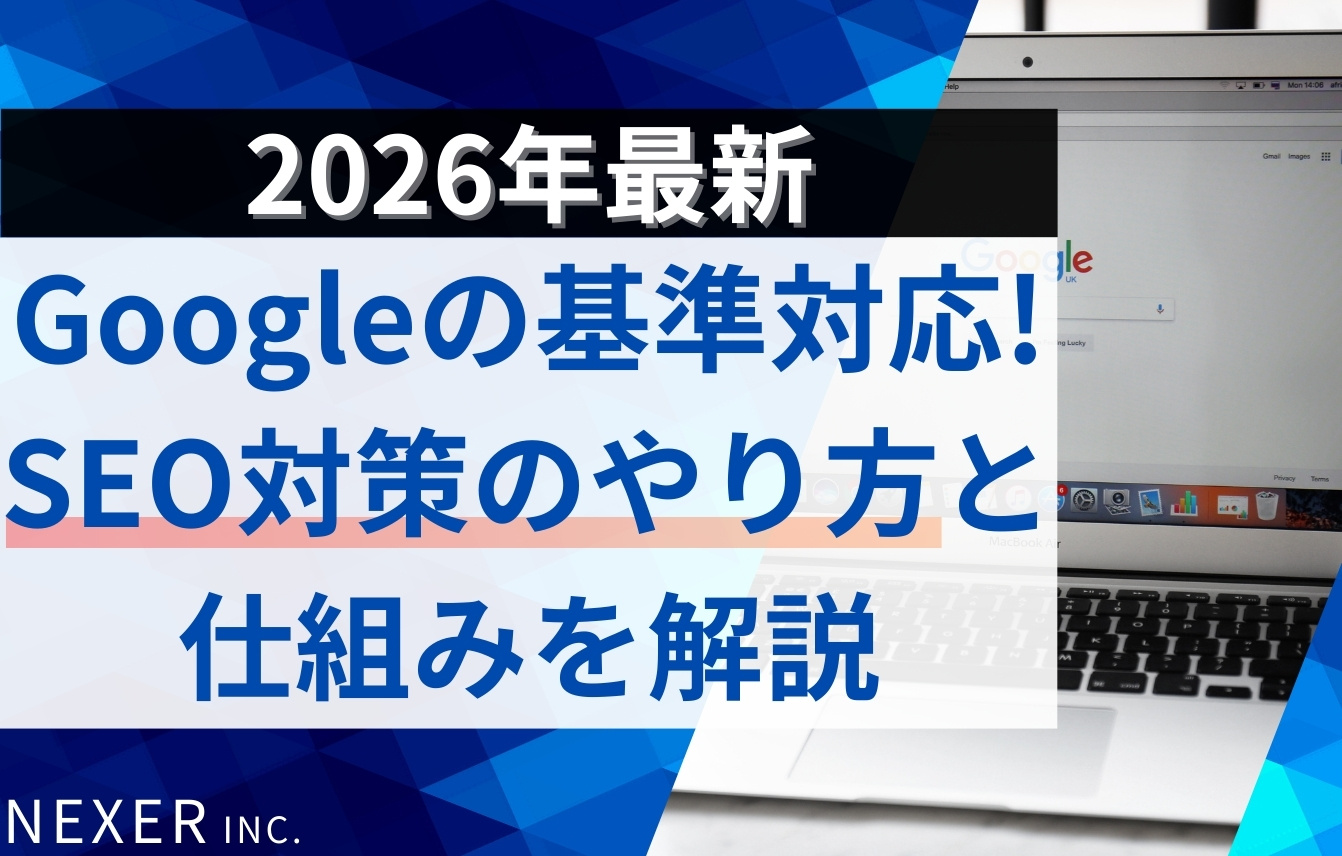
この記事の監修SEO会社

株式会社NEXER
2005年にSEO事業を開始し、計5,000社以上にSEOコンサルティング実績を持つSEOの専門会社。
自社でSEO研究チームを持ち、「クライアントのサイト分析」「コンテンツ対策」「外部対策」「内部対策」「クライアントサポート」全て自社のみで提供可能なフルオーダーSEOを提供している。
SEOのノウハウを活かして、年間数百万PVの自社メディアを複数運営。
GoogleのSEO対策は、日々、変化を繰り返しています。
特にここ数年は、AIの目覚ましい進化によって、Googleの検索環境も大きく変わりました。
そんな目まぐるしく変化するSEO環境においても、SEO対策の基本となるのはGoogleの「検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド」です。
SEOのどんなに優秀な専門家よりも、Googleから教わった方が正しいSEO知識を教えてくれます。
なぜなら、Googleのアルゴリズムを決めているのはGoogleだからです。
この記事は、Google公式のSEOガイドに沿って、最新のSEO対策のやり方を解説していきます。
難しい用語は、なるべく分かりやすく嚙み砕いて解説していきますので、SEO初心者さんも参考にしてください。
この記事は、こんな人におすすめ!
- Googleの公式ガイドを基にした正しいSEO対策を学びたい人
- AI時代にも通用する最新のSEO対策を知りたい人
- SEOの基礎知識を分かりやすく理解したい初心者さん
SEO業界20年、取引実績5,000社で多種多様な企業様の課題解決と成長をサポートしてまいりました。
完全内製の一貫体制でSEO支援を行い、専属のSEO研究チームが「分析→実装→検証→改善」 のサイクルを高速で回します。
問い合わせ増加・ブランディングを全力でサポートいたします。
目次
- 1 2026年最新のSEO業界とGoogle検索の変化
- 2 SEO対策とは?
- 3 GoogleのSEO対策はアルゴリズムの理解が重要
- 4 Google公式ガイドに基づくSEO対策のやり方7選
- 5 Googleの考えるやってはいけない意味のないSEO対策
- 6 無料で使えるSEO対策ツール
- 7 Google Search Consoleでサイトを登録する方法
- 8 GoogleのSEO対策が意味ないと言われる理由
- 9 GoogleのSEO対策を外注する時の費用
- 10 SEO対策を自分でできるか外注するかの判断基準
- 11 GoogleマップとSEOの関係
- 12 GoogleのSEO対策のよくある質問(FAQ)
- 13 まとめ:SEO対策はGoogleを基準で考え、その変化にも対応が必要
- 14 お問い合わせ
2026年最新のSEO業界とGoogle検索の変化
2025年、SEO業界とGoogle検索において、大きく2つの変化がありました。
- AI Overviewsの表示率アップ(特定の分野)
- AIモードが日本でも導入
AI Overviewsは、2024年からGoogle検索に導入されており、検索ワードに対する回答となるような情報を要約し、検索結果の上位に表示する機能です。
Serach Engine Landの調査によると、「エンターテイメント」「レストラン」「旅行」に関連するキーワード検索において、それぞれ528%、387%、381%もAI Overviewsの表示率が上がったことが分かっています。
(参考:Serach Engine Land)
これは2025年の3月のコアアップデート以降で、変化があったことが判明しています。
またGoogle検索に、AIモードが2025年9月9日に正式に日本で導入されました。
(参考:Google Japan Blog)
AIモードとは、Googleの検索窓の真横に搭載された対話式のAIツールです。
クリックするとチャット画面が起動し、「~を教えて」「~ですか?」のように言葉を投げかけることで、回答を得ることができます。
AI OverviewsとAIモードに共通するのは、Google検索結果における記事を参考にして回答を生成していることです。
AIの回答には参考にされた記事も一緒に表示されることが多く、SEO業界においては、このAIの参考記事からのアクセス流入を図るため、よりE-E-A-Tが強く求められるようになりました。
E-E-A-Tとは、経験(Experience)、専門性(Expertise)、権威性(Authoritativeness)、信頼性(Trustworthiness)の略で、Googleの評価基準の一つです。
SEO対策とは?
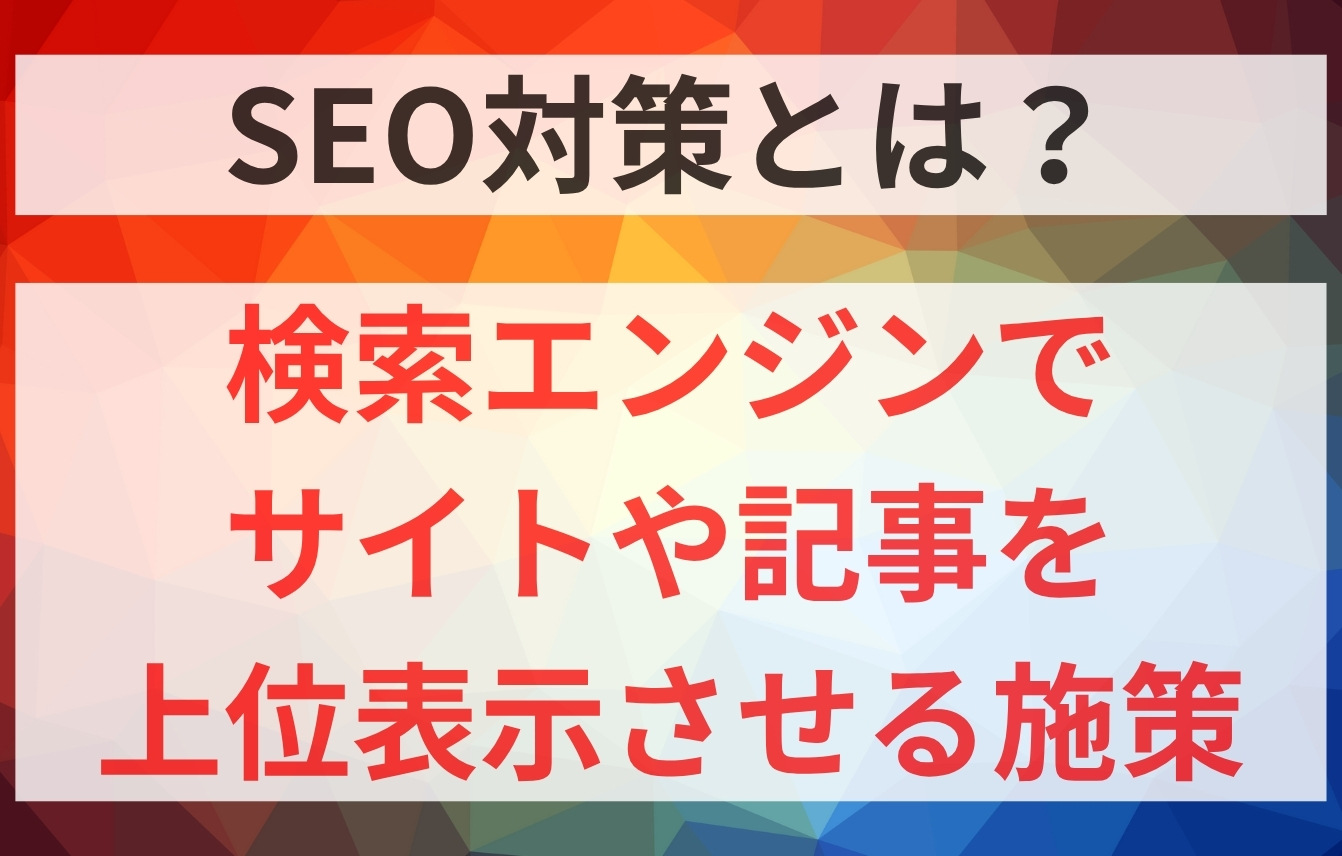
SEO対策とは、Googleなどの検索エンジンで自社サイトや特定の記事を上位に表示させるための施策です。
正式には「Search Engine Optimization」と呼ばれ、検索エンジンの仕組みを理解してサイトを最適化し、ユーザーの検索意図に合ったコンテンツを提供することで、上位表示を目指すことになります。
検索上位に表示されることで、より多くの人に情報が届き、ビジネスやサービスの認知拡大につながります。
近年では、コンテンツの質や専門性、信頼性が重視されるようになっており、より戦略的にSEO対策を行わないと結果を得ることが難しくなってきています。
SEO業界20年、取引実績5,000社で多種多様な企業様の課題解決と成長をサポートしてまいりました。
完全内製の一貫体制でSEO支援を行い、専属のSEO研究チームが「分析→実装→検証→改善」 のサイクルを高速で回します。
問い合わせ増加・ブランディングを全力でサポートいたします。
SEO対策のメリット
SEO対策の魅力は、長期的な集客基盤を築けることにあります。
広告に頼らず自然検索からの訪問を増やすことで、ビジネスの安定性やブランドの信頼性を高めることができます。
代表的なメリットは、以下の通りです。
SEO対策のメリット
- 広告費をかけずに安定したアクセスを獲得できる
- 検索上位に表示されることで、信頼性やブランド力が向上する
- コンテンツを蓄積することで、資産として長期的に効果が続く
- 検索経由のユーザーは購買意欲が高く、成約率が上がりやすい
例えば広告は、掲載をやめた瞬間、そこからのアクセスは0になります。
一方でSEO対策では、一度上位表示に成功すると、放っておいてもその効果はある程度は持続します。
もちろん、継続的に情報の更新や改善が求められますが、広告に比べてもコストパフォーマンスが高い施策と言えます。
SEO業界20年、取引実績5,000社で多種多様な企業様の課題解決と成長をサポートしてまいりました。
完全内製の一貫体制でSEO支援を行い、専属のSEO研究チームが「分析→実装→検証→改善」 のサイクルを高速で回します。
問い合わせ増加・ブランディングを全力でサポートいたします。
SEO対策のデメリット
SEO対策は短期間で成果を出すのが難しいという側面もあります。
アルゴリズムの変化や競合サイトの動きに左右されやすく、常に改善を続ける姿勢が必要です。
代表的なデメリットは、以下の通りです。
SEO対策のデメリット
- 効果が出るまでに時間がかかる
- 継続的な記事更新やリライトなど、運用の手間が発生する
- 競合が強いキーワードでは上位表示が難しい
- Googleのアップデートによって順位が変動するリスクがある
SEO対策は、数週間で効果が出るような施策ではありません。
サイトの規模やドメインの強さ、狙うキーワードにもよりますが、一般的に3〜6か月程度を目安に効果が実感できることが多いです。
また、Googleは年に2〜3回程度のコアアップデートを行い、これによって順位変動が起こることもよくあります。
GoogleのSEO対策はアルゴリズムの理解が重要
SEO対策の基本は、Googleのアルゴリズムを理解することです。
どのようにして、ネット上にある膨大な記事に順位を付けて、振り分けているのか。
検索結果の1位に表示されている記事が、なぜ1位に選ばれたのか。
ここを理解することで、SEO対策に対する考え方や取り組み方の質が高くなるので、初めに押さえておきたいポイントとなります。
検索順位が決まるまでの流れ
Googleの検索結果に表示される順位は、「クロール」「インデックス」「ランキング」という3つの工程で決まります。
これは検索エンジンの基本的な仕組みであり、SEO対策を考えるうえでも必要になる知識です。
クロール
Googleのクローラーと呼ばれるロボットがウェブ上のページを巡回して情報を収集する
インデックス登録
収集した情報をGoogleのデータベースに登録する
ランキング
ユーザーの検索意図に最も合うページを、評価に基づいて順位付けして表示する
投稿したばかりの記事が、いくら検索で調べても表示されないことがあります。
これはその記事が、まだクローラーに収集されて登録されていないためです。
つまり、どれほど良い記事を書いても、クロールやインデックスの段階で正しく認識されていなければ上位には表示されません。
SEO対策では、順位を上げる施策も必要ですが、Googleに認識してもらいやすくする施策も必要になります。
検索順位を決めるために参考にされる要素
Googleは、200以上の膨大な評価項目から検索結果の順位をつけていると言われます。
ただ、そのスコアや項目が詳細に公表されているわけではありません。
しかし、Google公式のSEOの指南書とも言える「検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド」を読み解くことで、おおよその重要な要素は判明しています。
まとめると、以下の4つは特に重要となる要素です。
ユーザーの検索意図に合っているか?
検索ユーザーの悩みや目的を解決し、タイトルや見出しに自然なキーワードを配置しているか
コンテンツの質が高いか?
E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の要素があるか
ユーザー体験を損ねていないか?
表示速度、モバイルでの見やすさ、パンくずリストによる階層整理など
Googleにも認識しやすい構造か?
内部リンクの最適化、サイトマップの登録など
これらの4つの要素は、単独で評価されるというよりも、サイトの信頼性として総合的に評価されます。
どれか1つを極端に伸ばすのではなく、検索意図の理解からコンテンツ制作、技術的な整備までを一貫して最適化することが重要です。
Google公式ガイドに基づくSEO対策のやり方7選

SEO対策を正しく進めるためには、Googleが公式に公開している「検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド」を理解することが重要です。
このガイドは、Google自身が理想的なWebサイトのあり方を示したものです。
つまり経験や実力がなくても、このガイドに書かれている事を実践すれば、誰でもSEO対策ができるわけです。
ただ、このガイドは文章も長く専門用語も多いため、初心者が読んでも理解できない部分が多く、少し敷居の高いガイドになっています。
そこで、この難解なガイドの内容を7つの項目に分かりやすく整理したので、1つづつ分かりやすく解説していきます。
SEO業界20年、取引実績5,000社で多種多様な企業様の課題解決と成長をサポートしてまいりました。
完全内製の一貫体制でSEO支援を行い、専属のSEO研究チームが「分析→実装→検証→改善」 のサイクルを高速で回します。
問い合わせ増加・ブランディングを全力でサポートいたします。
①Googleがコンテンツを見つけられるようにする
どれほど優れた記事やサイトを作っても、Googleがそのページを見つけられなければ検索結果に表示されません。
まずは、検索エンジンの「クロール」と「インデックス」に正しく認識されて登録されるように整備することが重要です。
Googleがコンテンツを見つけられるようにするには、以下の方法があります。
- インデックス登録をリクエストする
- XMLサイトマップを送信する
- 適切な内部リンクを配置する
新規公開の記事は、放っておいても勝手にクローラーが見つけてインデックス登録してくれますが、時間がかかることがあります。
これをGoogle Search Consoleというツールを使って、手動で優先的にインデックス登録してもらう方法があります。
(詳しい方法は記事の後半で解説しています。)
また、XMLサイトマップの送信をすることも有効です。
XMLサイトマップとは、サイト全体の階層構造をGoogleに正しく理解してもらう地図のようなものです。
XMLサイトマップは自分で作成が必要ですが、これもGoogle Search Console上でデータの送信ができます。
そして、サイト内の関連する記事同士を内部リンクで結びつけることでも、Googleは認識を深めることができます。
②Googleとユーザーでページの見え方が同じになるようにする
Googleのガイドでは、ユーザーに見える情報と、検索エンジンが認識できる情報が一致している方が望ましいと言及しています。
まずは、Googleとユーザーでサイト情報にズレがないかを確認する必要があります。
確認には、以下の方法があります。
- 「/robots.txt」で、CSS・JavaScriptなどをブロックしていないか確認する
- URL検査ツールで、Googleから見たページ表示を確認する
「自分のサイトURL/robots.txt」と入力しアクセスすることで、ブロックされた情報を知ることができます。
そこに表示された「Disallow」という項目が、Googleにブロックしている情報です。
WordPressを使っているなら、その欄に「/wp-admin/」と表示されることもありますが、これはワードプレスの管理画面のため、Googleにブロックしていても問題ありません。
また、Google Search ConsoleのURL検査ツールを使えば、インデックス登録の状況やクロール可否、モバイルでの表示状態などが分かります。
(詳しい方法は記事の後半で解説しています。)
③サイトを整理する
サイトを構築する時やリニューアルを行う時には、ページ同士の関係が分かりやすいように整理することが推奨されています。
これは、Googleにサイトの構造を理解させるだけでなく、ユーザーにとっても目的の情報へたどり着きやすくなるためでもあります。
サイトを整理するには、以下の方法があります。
- わかりやすいURLを使う
- 重複コンテンツを減らす
例えば、「猫」に関する記事なら「https://www~/pets/cats.html」のように、URLから内容が想像できる形が望ましいです。
この場合の「/pets/」となっている部分はパンくずリストと呼び、ユーザーにもサイトの階層を分かりやすくさせる効果があります。
「https://www~/2H34/975Y26D703A174」のような英数字の羅列は、あまりよくないということです。
また重複コンテンツを減らすため、同じ内容を複数のURLで公開している場合は、1つに統一します。
もし同じ情報のページが複数ある場合は、使用しないURLから統一したいURLへリダイレクト設定をする必要があります。
SEO業界20年、取引実績5,000社で多種多様な企業様の課題解決と成長をサポートしてまいりました。
完全内製の一貫体制でSEO支援を行い、専属のSEO研究チームが「分析→実装→検証→改善」 のサイクルを高速で回します。
問い合わせ増加・ブランディングを全力でサポートいたします。
④興味深く有益なサイトにする
興味深く有益なサイトにすることは、「このガイドで説明している他のどの方法よりも有効であると考えられます。」と、検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイドに表記があることからも、重要な要素であることが分かります。
Googleのガイドでは、以下の4つの要素が有益なサイトに必要であるとしています。
- 文章が読みやすく整理されており、誤字脱字や文法の間違いがない。
- コンテンツに独自性があり、コピーした要素がない。
- 情報が最新で、古い内容が適切に更新されている。
- ユーザー第一で、信頼できるコンテンツになっている(E-E-A-T)。
これら4つの要素は、単に文章や情報を整えるだけでなく、ユーザーにとっても「ここで知りたいことが全部わかる」と感じてもらえ、また来たいと思われるサイト作りに直結します。
特に、独自性と最新性はGoogleが重視している部分で、他サイトの情報をまとめただけのページよりも、自らの経験・調査・検証に基づく新しい情報が高く評価されます。
また、以下のようなE-E-A-T要素を、積極的に取り入れることも重要です。
経験
実際に商品を使ってみた体験レビュー
専門性・権威性
専門家や公式データを引用した根拠の提示
信頼性
運営者情報やプロフィールの明示
E-E-A-T要素の強化は、検索者に信頼感を与えて、コンバージョンに繋げやすくする効果もあります。
⑤検索結果の見え方を工夫する
Google検索では、検索結果の見え方そのものがクリック率(CTR)に大きく影響します。
検索ユーザーは記事タイトルや説明文(スニペット)を見て、どのサイトをクリックするかを判断するため、見た目の情報設計もSEOの重要な一部としてGoogleは捉えています。
ここでは、良いタイトル記事とスニペットの書き方のコツをまとめておくので、参考にしてください。
良いタイトル記事の書き方のコツ
- 記事のテーマとなるキーワードを自然な形で前半の方に配置する
- 30~35文字前後を目安に、検索結果で途切れない長さにする
- 「おすすめ10選」「7つの方法」など、具体的な数字を入れる
- リライトした場合「2026年最新」など最新性を意識する
良いスニペットの書き方のコツ
- ページの要点を1〜2文(80〜120文字程度)でまとめる
- タイトルで触れられなかった補足情報を入れる
- 行動を促すフレーズを入れる(例:「誰でも分かるように解説」「今すぐチェック」)
- 「誰向けの記事か」を明示する(初心者向け、中小企業向け)
- 自然な文脈で検索キーワードを1〜2回入れる
スニペットを「メタディスクリプション」と呼ぶことがありますが、正確には別のものです。
メタディスクリプションは、Googleにページ内容を伝えるためにHTMLで設定する説明文のことで、これを設定することで、検索結果にその説明文(スニペット)が採用される場合があるということです。
ただし、Googleはユーザーの検索キーワードに合わせて、本文から自動的にスニペットを生成することもあります。
⑥画像を最適化する
画像は、検索ユーザーがサイトを見つける大きなきっかけにもなります。
例えば「旅行」や「料理」のように、視覚的な情報が特に求められる検索においては、文字以上に画像の存在が重要です。
Googleに画像を正しく理解してもらうためには、「alt属性」の設定が重要です。
また「alt属性」は、画像に添えられる説明文(キャプション)のことではないので、混同しないように注意してください。
例えば、飲食店の内観の写真に「(店名)の内観」と「alt属性」を設定することで、Googleがその写真を正しく理解することができます。
また、画像の最適化で注意することが2点あります。
あまりにも容量の大きい画像は避ける
→ 読み込み速度が遅くなり、Google評価の低下につながる
alt属性にキーワードを詰め込み過ぎない
→ スパムと判断され、ペナルティの可能性がある
これらの注意点を踏まえて、画像からの評価も高めていくことが、SEO対策では重要になります。
⑦ウェブサイトを宣伝する
SEO対策では、ウェブサイトを宣伝して、より多くの人に認知してもらうことも必要です。
これは、宣伝そのものの集客効果もありますが、認知度が上がることで、他サイトから被リンクを受けやすくなる効果もあります。
良質なサイトから被リンクを受けることは、サイト評価を高めることにつながります。
ウェブサイトの宣伝方法には、以下の方法があります。
- SNSの活用
- プレスリリースの発信
- ネット広告
- 口コミ(他者の協力が必要)
まず、第三者であるユーザーに、体験レビューや口コミを書いてもらうことは大きな宣伝になります。
ただ、これはユーザーに依存するため、自分でコントロールをすることはできません。
しかし、SNSやプレスリリースは、自分から発信していくことができます。
日本では「PR TIMES」というサイトで、新商品の発表等を配信することで、多くのメディアに取り上げてもらうことができるため、メジャーな宣伝方法の一つになっています。
また、ネット広告も宣伝方法の一つですが、コストが結構かかります。
Googleの考えるやってはいけない意味のないSEO対策

Google公式の「検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド」では、理想のサイトにするためのSEO対策が説明されています。
その一方で、Googleが検索順位において重要としていないものに関しても言及がされています。
これを知っておくことで、意味のないSEO対策をしてしまうリスクを避けることができます。
以下に、Googleガイドで提示されている検索順位における「Googleが重要でないと考えること」をまとめました。
メタキーワード
→ Google検索はキーワードメタタグを利用していない。
※「メタキーワード」とは、HTMLに記述する「ページの主なキーワード」を検索エンジンに伝えるタグのこと。現在は無効化されている。
キーワードの乱用
→ 同じキーワードの多用はスパムと認識される可能性がある。
ドメイン名やURLパスの中のキーワード
→ パンくずリストとして階層理解には有効だが、ランキングには影響しない。
コンテンツの最小長と最大長
→ 文字数は検索順位に直接影響しない。重要なのは内容の質。
サブドメインかサブディレクトリか
→ SEO上の優劣はない。運用や管理しやすい方を選べばOK。
※サブドメイン:shop.example.com
※サブディレクトリ:example.com/shop/
PageRank
→ 多数ある要素の一つに過ぎない。外部には数値が公開されていない。
※PageRankとはリンクの信頼度を数値化するGoogle初期の指標。
重複コンテンツ
→ 複数URLでアクセスできるページがあっても問題はない。ただしコピーコンテンツはNG。
見出しの数や順序
→ 見出しの数や順番は順位に影響しないが、読者の読みやすさに影響する。
E-E-A-T
→ 評価の一要素ではあるが、これだけで順位が大きく決まるわけではない。
※E-E-A-T:経験・専門性・権威性・信頼性
検索順位には全く影響しなくても、読み手にとっては影響する要素もあるので注意しましょう。
無料で使えるSEO対策ツール
SEO対策では、データの分析が重要です。
ページ毎のアクセス数、滞在時間、どのデバイスで閲覧されているかなどを詳しく知ることで、読者のニーズを読み取ることができます。
これらのデータは、現在行っている対策が上手くいっているかどうかを把握するだけでなく、リライトすべき記事の優先順位を付ける時にも活用できます。
ここでは、無料で使えるSEO対策に便利なツールを紹介します。
SEO業界20年、取引実績5,000社で多種多様な企業様の課題解決と成長をサポートしてまいりました。
完全内製の一貫体制でSEO支援を行い、専属のSEO研究チームが「分析→実装→検証→改善」 のサイクルを高速で回します。
問い合わせ増加・ブランディングを全力でサポートいたします。
Google Analytics(グーグルアナリティクス)
Google Analytics(グーグルアナリティクス)は、サイトに訪れたユーザーの行動を詳しく分析できる無料ツールです。
Google Analyticsで分析できること
- アクセス数(ページ単位で確認可能)
- 読者のデバイス(スマホ・PCなど)
- アクセス流入元(自然検索・SNS・ChatGPTなど)
- 滞在時間
- 離脱率
ページごとのアクセス数はもちろん、スマホやPCのようなどのデバイスから見られているのか、どこからアクセスしてきたのかも確認できます。
また、ページの滞在時間や離脱率から「どのページが読まれていて、どこで離脱されているのか」を把握できるため、改善点の発見や記事リライトの判断材料として役立ちます。
SEO対策を行うなら、まず導入しておきたい基本の分析ツールです。
Google Search Console(グーグルサーチコンソール)
Google Search Console(グーグルサーチコンソール)は、Google検索におけるサイトの表示状況を確認できるGoogle公式の無料ツールです。
Google Search Consoleで確認できること
- 検索キーワードでの記事の表示回数・クリック数・平均順位
- ページのインデックス状況(URL検査)
- サイトのエラー
- ペナルティの有無
- モバイル対応状況
検索結果で記事がどんなキーワードで表示されて、何回クリックされているかを確認できます。
また、ページがGoogleに正しくインデックス登録されているか、エラーやペナルティがないかもチェック可能です。
検索順位が上がらない原因や、改善すべきページを見つけるために欠かせないツールです。
キーワードプランナー
キーワードプランナーは、検索数を調べられるGoogle提供の無料ツールです。
キーワードプランナーで分析できること
- キーワードの月間検索数(検索ボリューム)
- 関連キーワードの候補表示
- 広告出稿時の競合性の目安
月間の検索ボリュームや関連キーワードの候補から、競合性の高さを調べることができます。
特に、記事を書く前のキーワード選定の時に役立ちます。
例えば「ダイエット 方法」と「痩せる 方法」のように似た意味のキーワードがある場合、どちらが多く検索されているかを比較することで、狙うべき検索キーワードの優先順位を付けやすくなります。
Google広告のアカウント登録は必要ですが、広告出稿をしなくても無料で使うことが可能です。
ラッコキーワード
ラッコキーワードは、Googleのサジェストワードや関連キーワードを取得できる無料ツールです。
ラッコキーワードで分析できること
- Googleサジェスト・関連キーワードの一括取得
- 競合サイト分析(見出し、獲得キーワードなど)
- 月間検索数取得(有料)
- SEO難易度調査(有料)
ユーザーが実際に検索している言葉を一括で取得できるため、見出し作成や検索意図の把握に役立ちます。
ラッコキーワードとキーワードプランナーを併用すれば、多くのキーワードから読者のニーズを読み解くことが可能です。
さらに、競合サイトの見出しを抽出したり獲得キーワードを調査することもできます。
有料プランに入ると月間検索数やSEO難易度も確認できて便利ですが、無料の機能だけでも十分に即戦力となるツールです。
CopyContentDetector(無料コピペチェックツール)
CopyContentDetectorは、自分の文章が他サイトと似ていないかチェックできる無料ツールです。
CopyContentDetectorで分析できること
- 文章のコピー率・類似率のチェック
- 他サイトとの重複箇所の表示
- オリジナル文章かどうかの判定
文章を入力すると、類似率・一致率が数値で表示されるため、盗用や重複コンテンツの判断に役立ちます。
Googleではコピーコンテンツは、ペナルティの対象となる可能性があるため、記事が完成したらまずはこのツールで確認することをおすすめします。
何%の一致率だとアウトという明確な基準はありませんが、SEOの現場では一致率を約40%未満に抑えるように推奨されることが多いです。
Google Search Consoleでサイトを登録する方法
Google Search Consoleでは、クローラーに自分のサイトの存在を知らせて、いち早く検索結果に表示してもらうことができます。
これを、インデックス登録と言います。
インデックス登録は、新しい記事を投稿したらまず初めにやっておきたい、SEO対策の基本です。
ここでは、インデックス登録をする理由と実際の登録方法を解説します。
なぜサイトを登録する必要があるのか?
Googleでは、クローラーが自動でサイトを見つけてインデックス登録することもありますが、公開したばかりのサイトや更新したばかりのページは、すぐに見つけてもらえるとは限りません。
Google Search Consoleでは、これを手動でインデックス登録をするように促すことができます。
どうせなら、少しでも早く実際の検索結果に反映された方が、アクセス数にも影響するため、手動でのインデックス登録はやっておいて損のない行動です。
特に、1秒で早く見てもらいたいタイムリーな新情報を配信したときには、必須のアクションと言えるでしょう。
さらに、サイトのエラーやモバイル表示の問題、インデックスの不具合、検索ペナルティなども通知されるため、トラブルの早期発見や改善にも役立ちます。
つまり、サイトをGoogleに見つけてもらうだけでなく、正しく評価してもらうために登録が必要です。
サイトの登録の方法(インデックス登録)
Google Search Consoleによる、サイトの登録方法は、以下の手順になります。
まずはサイト全体を登録して、その後に任意のページをインデックス登録する流れになります。
①Google Search Consoleにログイン
→ Google Search Consoleへアクセスし、Googleアカウントを使ってログインします。
②「ドメイン」「URLプレフィックス」の2つが出てくるので「URLプレフィックス」にサイトURLを入力
→ 「ドメイン」でもできますが、WordPressを使っている人や初心者なら「URLプレフィックス」でOKです。
③サイトの所有権を確認
- 指定されたファイルをダウンロードし、サーバーの公開フォルダにアップロードする
- 指定されたHTMLタグをWordPressのテーマの「」内に貼る
④これでサイトの登録は完了。次に記事のインデックス登録
⑤ページ上部のフォームに登録したいページのURLを入力
⑥「インデックス登録をリクエスト」をクリック
⑦インデックス登録をリクエスト済みと表示されたらOK
ちなみに、インデックス登録した瞬間に検索結果に反映されません。早くても数時間はかかります。
また検索順位やクリック数のデータが見れるようになるのは、登録して2日後くらいになります。
インデックス登録されているか確認する方法
そのページがインデックス登録されているかを確認する方法は、簡単です。
先ほどのインデックス登録の手順と同じように、画面上部のフォームに確認したいページのURLを入力します。
インデックス登録されていれば「URLはGoogleに登録されています」や「ページはインデックスに登録済みです」と表示されるので、それで確認ができます。
もし、インデックス登録されていないならば、以下の原因が考えられます。
noindexタグが付いている
→ ページのHTML内に <meta name="robots" content="noindex"> があるとインデックスされない。
WordPressの設定で「検索エンジンがサイトをインデックスしないようにする」になっている
→ robots.txt でクロールがブロックされ、検索エンジンに登録されない。
コンテンツの質が低い、または重複している
→ Googleから低品質と判断され、インデックスされにくくなる。ペナルティの可能性もある。
公開して間もない
→ 手動でインデックス登録をリクエストしても、反映まで数時間〜数日かかることがある。
GoogleのSEO対策が意味ないと言われる理由
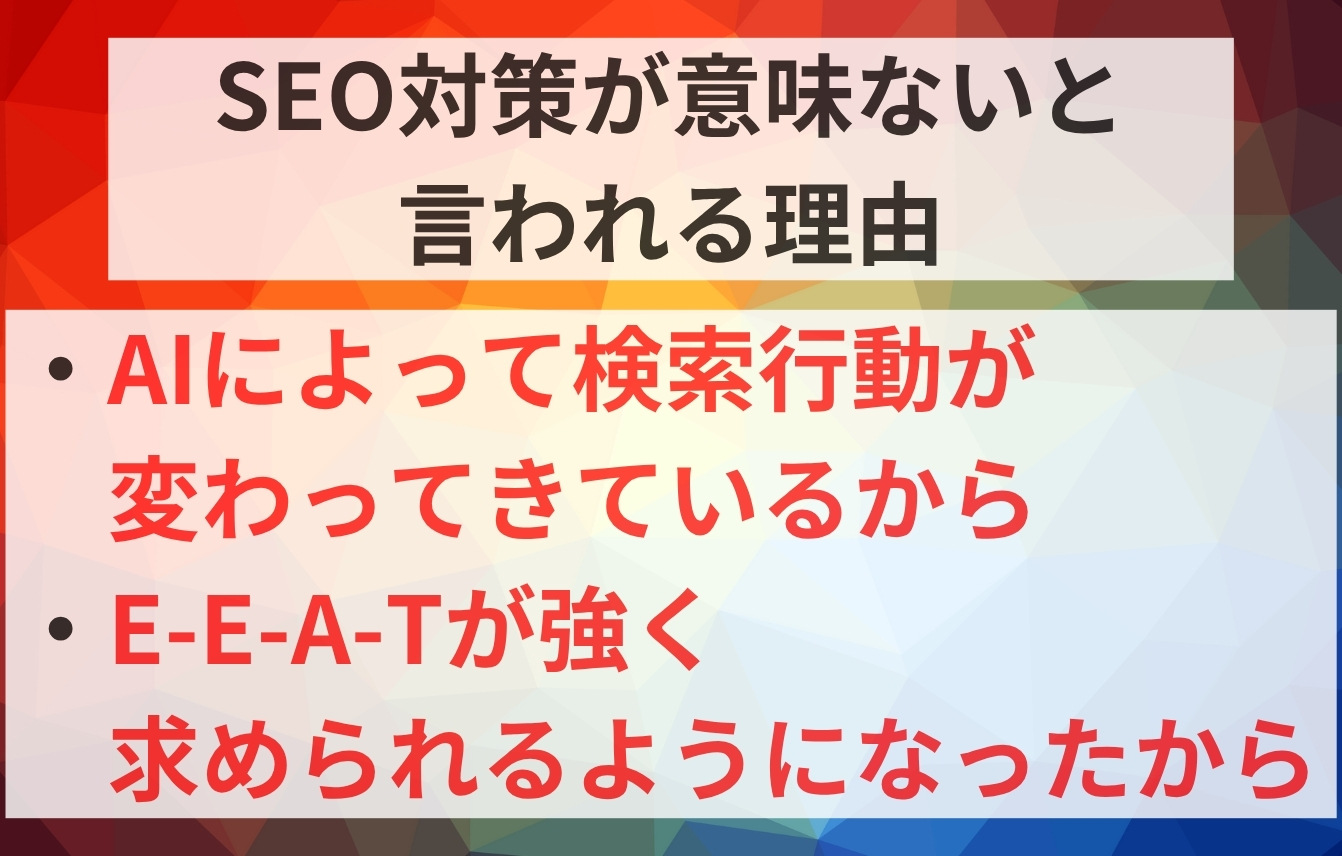
「SEO対策は意味がない」。
SEOに関する情報を収集していると、このような噂を一度は聞いたことがあると思います。
この「意味がない」と言われる理由には、従来通りのやり方では通用しなくなってきた意味も含まれています。
ただ、最新のSEOに上手く対応していけば、AIツールと自然検索の両方からのアクセス流入を確保できるため、SEOはむしろチャンスの場になっています。
AIによって検索行動が変わってきているから
「SEO対策は意味がない」と言われる、大きな原因の一つに「AI」があります。
ChatGPTの登場により、ユーザーは探し物をする時にGoogle検索ではなく、AIに聞くという行動を選択する人が増えてきています。
また、2024年には「AI Overviews」、2025年には「AIモード」と、Googleの検索エンジンにもAI機能が搭載されました。
ここ数年で、ユーザーがAIを利用する機会が一気に増えてきたことで「意味がない」という噂が広がったのです。
ただ「AI Overviews」「AIモード」もベストな回答を導くために、Google検索結果の記事を参考にして、回答を生成しています。
参考にされた記事は横に表示されるため、ユーザーはAIの回答からその記事にアクセスすることが可能です。
例えば、何か商品を購入する場合でも、AIツール内だけで商品の購入はできないため、必ずその商品ページにアクセスする必要があります。
E-E-A-Tが強く求められるようになったから
「SEO対策は意味がない」と言われる理由の一つに、Googleの評価基準の変化があります。
E-E-A-Tと呼ばれる評価基準ですが、これにより今まで個人ブログで頑張ってきた人が、専門性(Expertise)や権威性(Authoritativeness)がないと評価され、SEOで上位を狙うことが難しくなりました。
このような状況が「意味がない」と噂されるようになった理由の一つです。
ただし2022年12月、Googleは従来の「E-A-T」の評価基準から、Experience(経験)を追加し「E-E-A-T」という4つの評価基準に変更しています。
(参考:Google Search Central Blog)
この「経験」というのは、個人でも取り入れることのできる要素です。
例えば、実際の体験談や商品の使用レビュー等が、それにあたります。
E-E-A-Tを強化することは、AIが参考にしたくなる記事にもつながるため、最新のSEO対策として意識したい要素となります。
GoogleのSEO対策を外注する時の費用

SEO対策を、外部の専門会社に依頼する場合、費用は依頼内容やサイトの規模によって大きく変わります。
記事作成だけを任せるのか、サイト全体の設計から改善まで依頼するのか、競合性の高い業界なのかによって必要な作業量も専門性も異なるためです。
一般的な費用相場と、料金が高くなるケースの違いをわかりやすく解説していきます。
SEO業界20年、取引実績5,000社で多種多様な企業様の課題解決と成長をサポートしてまいりました。
完全内製の一貫体制でSEO支援を行い、専属のSEO研究チームが「分析→実装→検証→改善」 のサイクルを高速で回します。
問い合わせ増加・ブランディングを全力でサポートいたします。
SEO対策の費用相場は大きく変動する
SEO対策の外注の費用相場は、おおよそ以下のようになります。
SEO対策の費用相場
| SEO対策サービス | 費用相場 |
|---|---|
| SEOコンサルティング | 月額 10〜100万円 |
| コンテンツSEO(記事ライティング) | 月額 10〜50万円 1記事 5,000円〜5万円 |
| SEO内部対策 | 月額 10〜100万円 |
| SEO外部対策 | 月額 10〜50万円 |
例えば、SEOコンサルティングや内部対策は「10万~100万」と、大きな幅があることが分かると思います。
これは、SEO対策が一律のサービスではなく、依頼者のサイト規模、狙うキーワードなどで作業量が大きく異なるためです。
記事作成一つとっても、新規記事を書いた方がいいのか、既存記事をリライトした方がいいのか、これはその時の状況によって対策アプローチは変わります。
SEO対策の専門業者の多くが、明確な料金を公開をしない理由には、これが影響しています。
逆に言うと、依頼する側は複数社から見積もりを取って、十分に比較吟味することが大事になります。
費用が高くなりやすいケース
SEO対策の費用相場はケースによっても大きく異なり、明確な料金の目安がありません。
ただ、あるケースでは費用が高くなりやすいという傾向はあります。
以下が、SEO対策の外注費用が高額になりやすいケースです。
競合が強く専門性の高いジャンル(医療・美容・法律・金融)
→ 難易度も高く、そのジャンルの専門知識が求められるため
WEBサイトの規模が大きい(1000ページ越えのサイトなど)
→ 内部リンク構造やリライト対象も多く、工数が膨らむ
サイトを0から立ち上げる場合
→ ドメインの強さがないため、上位表示に1年以上かかる可能性
このような傾向を知っておくと、見積もり相談の時にも交渉を進めやすくなります。
SEO対策を自分でできるか外注するかの判断基準
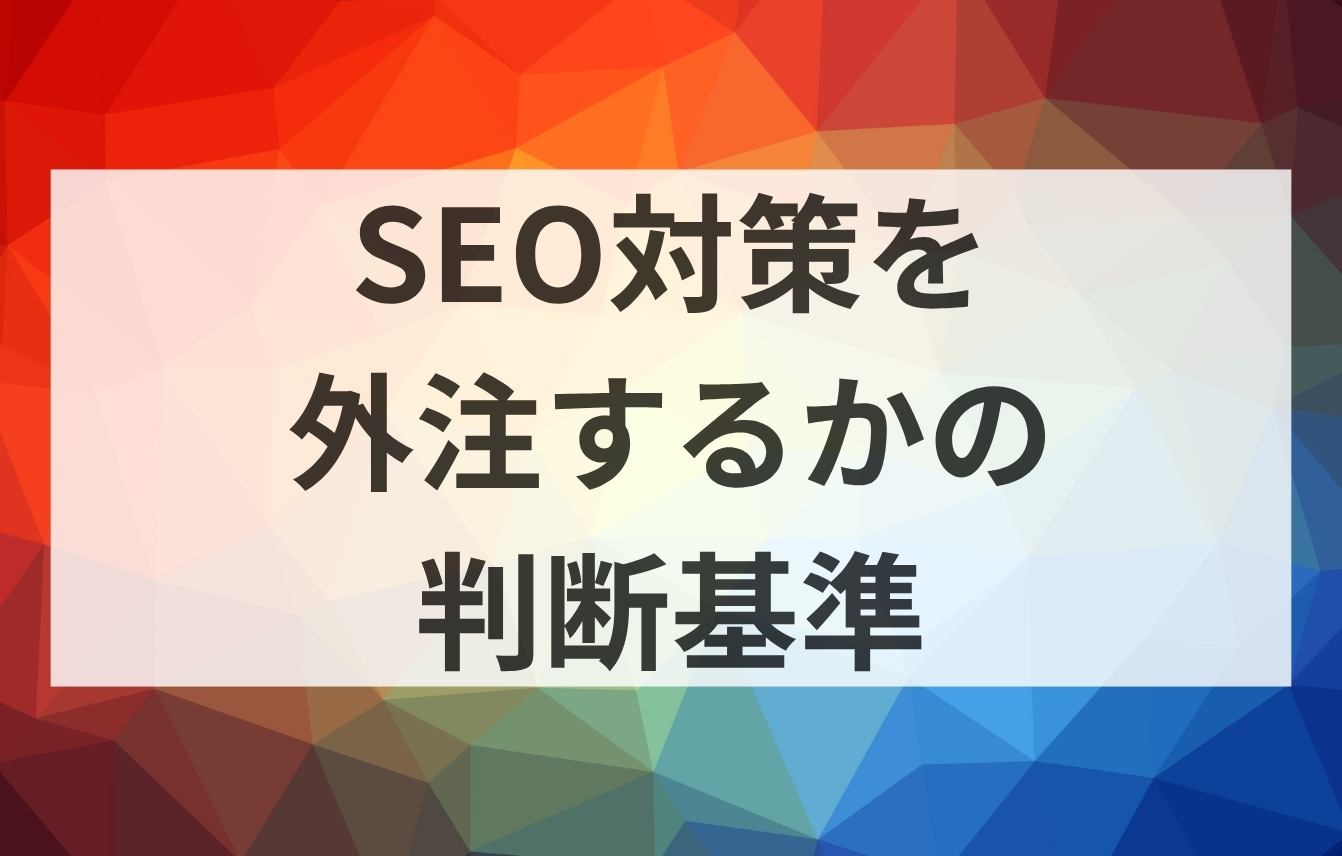
SEO対策は外注に任せることもできますが、自分で取り組むこともできます。
どちらかの選択が必ず正解ということはありませんが、なるべく自分の状況に適した手段を選ぶことが好ましいです。
自分でやるか?外注するか?の判断基準は、「予算・時間・知識」の3つの視点で考えると分かりやすいです。
3つの視点を基に、どちらがおすすめかをまとめました。
自分でSEO対策をするケース
- 外注する予算の余裕がない
- SEO対策を継続していく時間がある
- WordPressやSEO知識に自信がある
SEO対策を外注に任せるケース
- 6か月以上外注する予算の余裕がある
- 本業が忙しくSEO対策に時間を確保できない
- SEOが全く分からない初心者
SEO初心者の人であれば、よほど時間に余裕がない限りは外注がおすすめです。
SEOの知識は、座学だけで得られるものもありますが、実際にやって経験から得られるものも多くあるため、じっくり対策に時間を充てられる人でないと厳しいです。
また外注コストに関してですが、6か月以上は外注できる余裕は必要です。
SEO対策は、効果が出るのに早くても3か月と言われます。
SEO業界20年、取引実績5,000社で多種多様な企業様の課題解決と成長をサポートしてまいりました。
完全内製の一貫体制でSEO支援を行い、専属のSEO研究チームが「分析→実装→検証→改善」 のサイクルを高速で回します。
問い合わせ増加・ブランディングを全力でサポートいたします。
GoogleマップとSEOの関係
SEO対策は、自社サイトのアクセス流入を増やす定番の手段です。
ただし業種によってはSEOだけでなく、Googleマップの最適化も重要になることがあります。
Googleビジネスプロフィールを最適化して、Googleマップに表示されやすくする施策を、MEO対策と呼びます。
MEO対策の重要性を、分かりやすく解説します。
店舗型営業では無視できない要素
Googleマップは、飲食店・病院・美容院など、地域で店舗を構えて集客するビジネスにとって欠かせない存在になっています。
検索結果の上部に表示されるGoogleマップ情報は、ローカルパックとも呼ばれています。
このローカルパックは、検索上位記事より目立って表示されているため、ここでの認知度を向上させて、来客数を増やすことができます。
ローカルパックのGoogleマップで上位に表示されるには、Googleビジネスプロフィールの登録が必要になります。
MEO対策では、Googleビジネスプロフィールの営業時間・住所・電話番号・写真などの情報を整えることが基本となります。
口コミによる影響は高い
MEO対策でGoogleマップ上の認知度を上げることは重要ですが、そこに書き込まれる口コミもまた、重要な要素です。
2025年に行われた20代〜60代の男女500名を対象にした調査によると、Googleマップの口コミの点数について、飲食店に行きたいと思う点数を聞いたところ「3.8点以上を基準にする」と回答した人が全体の49.6%いたことが判明しています。
(参考:イクシアス株式会社調べ:https://storepad.jp/report/202504_report)
このことからも、口コミ評価が来店理由の最後の一押しになっているケースが多いことが分かります。
Googleマップの口コミは店舗側が返信できるので、ネガティブな意見の口コミに真摯に対応してイメージ改善をすることができます。
また、そもそも悪い評価をされないように、店舗サービスの改善と向上をしていくことも重要です。
MEO対策はSEOより始めやすい
MEO対策のメリットの一つに、SEOに比べて始めるハードルが低く、効果も現れやすい点があります。
Googleビジネスプロフィールの登録・店舗情報の入力・写真の追加・口コミ対応などは比較的シンプルな作業のため、PC作業に詳しくない人でも始めやすい施策です。
さらに、SEO対策はネット全体が競合になるのに対し、MEOは「地域名+業種」のように範囲が限られているため、競合が少なく上位表示を狙いやすいのも特徴です。
GoogleのSEO対策のよくある質問(FAQ)
最後にGoogleのSEO対策における、よくある質問をまとめておきます。
SEO対策は始めると、いろんなことが分かってきますが、まだ何も手を付けていない人からすると分からないことだらけです。
少しでも疑問に思うことや不安な部分は解消して、心に余裕をもってSEO対策を始めることが大切です。
Q:AIが流行ってますが今もSEO対策は必要ですか?
AI業界の参入や、Google検索における「AI Overviews」「AIモード」の登場で、通常の検索をする人が減っています。
このことで、SEOは意味がないと噂されることがありますが、これは間違いです。
確かにGoogle検索する人は減るかもしれませんが、AIはSEO上位の記事を参照することがよくあります。
中でもE-E-A-T要素を取り入れた記事は、信頼できるものとして、AIに取り上げられやすい傾向があります。
つまりSEO上位記事は、Google検索とAIツールの両方からアクセス流入を狙うチャンスが増えたことになります。
Q:SEO対策はどのくらいで効果が出ますか?
サイト規模や狙うキーワードによっても差はありますが、3~6か月程度で効果を実感できるケースが多いです。
ただしサイトを0から立ち上げた時は、もう少し効果が出るまでに時間がかかる可能性があります。
生まれたてのサイトは、ドメインそのものが持つパワーが低いため、いい記事を書いてもなかなか評価されにくい傾向があるためです。
あと忘れてはいけないのが、SEOに絶対はないということです。
3~6か月と言いましたが、Googleのアルゴリズムに依存しているため、これらはあくまで大きな目安でしかありません。
Q:Googleのコアアップデートとは何ですか?
コアアップデートとは、Googleが年に数回行うアルゴリズムの大規模アップデートのことです。
コアアップデートされる時期や、アップデートの詳細が公開されることは基本的にはありません。
ただこのコアアップデートで、検索順位が大きく変動することもあり、SEO対策に関わる人は常にこの動向を意識しておく必要があります。
Google Search Status Dashboardで、直近のアップデート履歴を確認することはできます。
Q:SEO対策は無料で自分でできますか?
SEO対策は、自分でも行うことができます。
ただしSEO対策には、Googleのアルゴリズムの理解、WordPressを使いこなせる技術、長期的に対策していく時間の3つが必要になります。
これらのどれか一つでも欠けるようであれば、自分だけでSEO対策することはおすすめできません。
外注費用はかかりますが、SEO対策は一度安定的に上位表示が維持できると、コストパフォーマンスの良い施策になります。
Q:SEOとネット広告の違いは何ですか?
SEOとよく比較されるリスティング広告との違いを、分かりやすくまとめました。
大きな違いは、効果が出るまでの時間とその持続性です。
SEOは効果が出るまでに時間を要しますが、一度上位表示に成功すると、継続運用することで安定的なアクセス流入の確保ができます。
投資のようなもので運用期間が長くなるほど、リスティング広告よりもコストパフォーマンスが高くなっていきます。
| SEO | リスティング広告 | |
|---|---|---|
| 効果が出るまでの時間 | 上位表示までに数か月はかかる | 掲載後すぐに表示される |
| 効果の持続性 | 一度上位表示されるとすぐには落ちない。継続的に更新すれば長期維持も可能。 | 広告を止めた瞬間に効果がなくなる |
| 費用 | 自分で行うなら無料 外注する場合は月額費用が発生 |
クリック毎に費用が発生(CPC) |
| 目的 | 長期的なブランディング サイトの資産化 安定したアクセス確保 |
新商品・キャンペーン告知 短期間で成果を出したい時 |
まとめ:SEO対策はGoogleを基準で考え、その変化にも対応が必要
SEO対策は、AIの登場によってここ数年で、環境が大きく変わりつつあります。
そんな状況でも、まずGoogleの「検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド」に立ち戻って考えることが重要です。
なぜならこのガイドも、そのAIの登場によって、内容が更新される可能性があるからです。
SEOで重要なことは、以下の3点です。
- Googleに評価されるサイトを作ること
- 読者に満足してもらえるサイトを作ること
- 最新のアルゴリズムに適応すること
これらを継続的に意識しながら、改善を繰り返すことで、SEOに強いサイトを作ることができます。
今後もSEOで分からないことがあれば、Google公式ガイドとこの記事を見直してみてください。

