AIO・SEO
AIO・SEOブログ
【2026年最新】SEOとは?初心者でもわかる仕組みと具体的なSEO対策を解説
2025.11.12 SEO
この記事の監修SEO会社

株式会社NEXER
2005年にSEO事業を開始し、計5,000社以上にSEOコンサルティング実績を持つSEOの専門会社。
自社でSEO研究チームを持ち、「クライアントのサイト分析」「コンテンツ対策」「外部対策」「内部対策」「クライアントサポート」全て自社のみで提供可能なフルオーダーSEOを提供している。
SEOのノウハウを活かして、年間数百万PVの自社メディアを複数運営。
つまりSEO対策とは、検索エンジンの最適化によって、検索結果の上位に記事を表示させる対策を指します。
自社のサービスや商品をネット上で売り込むときに、まずは顧客にその存在を認知してもらわないと、せっかく売れるものも売れなくなります。
SEO知識は、自社の認知を高め、商品やサービスを売り込むのに必要不可欠です。
この記事では、Google公式が公開している「検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド」を基に、初心者にも分かりやすくSEOの仕組みと順位が決まる流れを解説していきます。
この記事を読んで分かること
- SEO関連のむずかしい言葉の意味が分かる
- どうやってGoogleの検索結果の順位が決まっているかが分かる
- SEO記事の書き方・内部施策のチェックリスト等、実践的な知識が分かる
SEO業界20年、取引実績5,000社で多種多様な企業様の課題解決と成長をサポートしてまいりました。
完全内製の一貫体制でSEO支援を行い、専属のSEO研究チームが「分析→実装→検証→改善」 のサイクルを高速で回します。
問い合わせ増加・ブランディングを全力でサポートいたします。
目次
- 1 SEOとは?分かりやすく意味を解説!
- 2 SEOの初心者に難しい用語の意味をまとめました!
- 3 SEO対策をするメリット・デメリット
- 4 SEOの検索順位が決まるまでの流れをわかりやすく解説
- 5 SEOでGoogleが検索順位を決める仕組み
- 6 自分でできる!SEO内部施策チェックリスト15選
- 7 上位を狙うSEO記事の書き方の具体例
- 8 SEOコンサル会社よりSEO対策会社に依頼するのがおすすめ
- 9 Googleが提供する無料SEOツール
- 10 SEO対策を自分で勉強できるおすすめの本
- 11 SEO対策が意味ないと言われている理由
- 12 SEO対策のよくある質問(FAQ)
- 13 まとめ:SEOの仕組みを理解してSEO対策で高い成果を出そう
- 14 お問い合わせ
SEOとは?分かりやすく意味を解説!
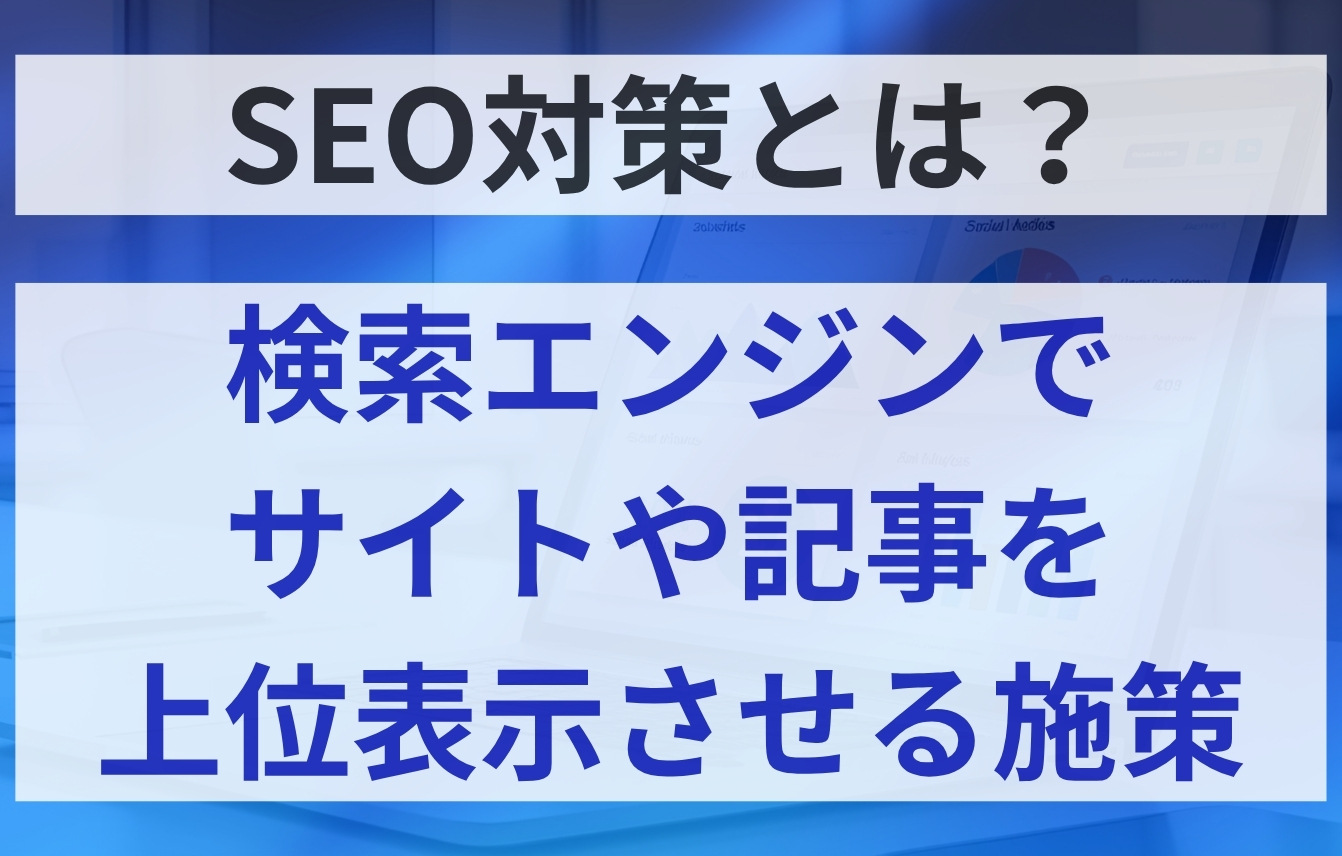
SEOとは、検索エンジンを通じて自社サイトや記事をより多くの人に見つけてもらうための取り組みです。
検索結果上の表示順位が高ければ、広告費をかけなくても自然にアクセスを集められるため、Web集客の基本戦略として欠かせないものでもあります。
ここでは、SEOの意味やMEO・リスティング広告との違いを初心者でも分かるように解説します。
SEOとは「Search Engine Optimization」の略
SEOとは「Search Engine Optimization」の略で、日本語では「検索エンジン最適化」と呼ばれています。
具体的には、GoogleやYahooといった検索エンジンで、自分のページが上位に表示されるよう、サイトや記事を改善する施策を指します。
例えば、検索結果の上位にあるページは自然にクリック率が高くなり、広告を出さなくても安定して集客につなげることができます。
逆に下位に埋もれてしまえば、どれほど有益な内容でも読まれにくくなるのです。
SEOは、ユーザーの検索意図を理解し、それに見合った質の高い情報を提供するための考え方でもあります。
SEO対策とは「検索結果の上位に表示させる対策」
SEO対策とは、検索結果で自分のサイトを上位に表示させるための取り組みです。
検索エンジンは数多くのサイトの中から、ユーザーにとって最も役立つと判断したページを独自のアルゴリズムによってランキング化し表示します。
SEO対策が難しいと思われるのは、単に情報を網羅して有益な内容を書くだけでは上位になれない点です。
検索意図を満たす質の高いコンテンツに加え、ページの表示速度やモバイル対応、内部リンクや見出し構造の整理といったサイトの構造的な工夫も必要になります。
これらが整って、初めて検索エンジンに評価され、上位に表示されやすくなります。
この記事では、単に情報網羅して有益性を高めるだけではない、サイト構造の工夫による順位の上げ方も、分かりやすく解説していきます。
SEOとMEOの違いは?
SEOと似た言葉に「MEO(Map Engine Optimization)」があります。
SEOが検索エンジン全体での上位表示を目的とするのに対し、MEOはGoogleマップやローカル検索での自社の店舗やサービスを目立たせる施策です。
たとえば「東京 カフェ」と検索したとき、検索結果のGoogleマップや記事に複数のカフェが表示されます。
この順位を上げる取り組みがMEOになります。以下にSEOとの違いをまとめました。
| SEO(検索エンジン最適化) | MEO(マップエンジン最適化) | |
| 目的 | 検索エンジン全体での上位表示 | Googleマップ上の上位表示 ローカル検索の上位表示(例:東京+カフェ) |
| ターゲット | すべて | 今そこにリアルタイムでいるユーザー その地域に住んでいるユーザー |
| 適したビジネス | ECサイト、全国展開している企業 | 飲食店、美容室、クリニックなどの実店舗型ビジネス |
| 具体的な施策 | SEO記事作成 内部施策 被リンク対策 サイト構造改善など |
Googleビジネスプロフィールの最適化 口コミ対策 NAP情報の統一(住所・店名・電話番号) |
SEOとリスティング広告の違いは?
リスティング広告もSEOと混同されやすい言葉です。
リスティング広告は、GoogleやYahooの検索結果の上部や下部に自分のページを「広告」として表示させるもので、広告費用を払うことで即座に検索結果に表示させることができます。
例えば、Googleなら検索結果の「スポンサー」と書かれたページが、まさにリスティング広告です。
一方、SEOはお金を直接払うのではなく、コンテンツやサイト構造を改善して、自然に上位を狙う施策です。
以下に、違いを分かりやすくまとめました。
| SEO(検索エンジン最適化) | リスティング広告 | |
| 表示される場所 | 検索結果 (リスティング広告がある場合、リスティング広告の直後から1位の記事が表示) |
検索結果の上部・下部に「広告」扱いで表示 |
| 費用 | 無料 | 基本的にクリックされると課金(CPC課金) |
| 効果が出るまでの早さ | 数か月はかかることが多い | 即日で表示される |
| 継続性 | 一度上位を取ると安定した集客が望める (ただし継続的な維持改善は必要) |
広告費を止めた瞬間に表示されなくなる (集客が広告費に依存する) |
そのためSEO上位よりリスティング広告の方が、必ずしも優位性がとれていると言い切ることはできません。
SEOの初心者に難しい用語の意味をまとめました!
いざSEOに取り組み始めると、カタカナやアルファベットの専門用語が多くて「むずかしい・・・」と感じる方も多いはずです。
そこで、特に初心者がつまずきやすい用語を一覧で整理しました。
これらを押さえておけば、SEO記事や解説を読むときにも理解がスムーズになります。
SEO業界20年、取引実績5,000社で多種多様な企業様の課題解決と成長をサポートしてまいりました。
完全内製の一貫体制でSEO支援を行い、専属のSEO研究チームが「分析→実装→検証→改善」 のサイクルを高速で回します。
問い合わせ増加・ブランディングを全力でサポートいたします。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| アルゴリズム | 検索順位を決めるための計算ルールや仕組み |
| クローラー | サイトを巡回して順位決めの情報収集をするロボット |
| インデックス | クローラーが収集したサイトを検索エンジンに登録(表示)すること |
| 被リンク | 他のサイトから自分のサイトへ向けられたリンク |
| ドメインパワー | サイトやドメインの信頼性や評価の強さ |
| E-E-A-T | Googleが順位評価をする4つの基準の略語 (Experience:経験) (Expertise:専門性) (Authoritativeness:権威性) (Trustworthiness:信頼性) |
| Core Web Vitals(コアウェブバイタル) | ページの表示速度や安定性などを測るGoogleの指標 |
| H2、H3などの記号 | 記事の見出しのタグ。目次のようなもので、記事の構造を整理し検索エンジンに伝える役割 |
| パンくずリスト | サイト内で今いる位置や階層を示すナビゲーションの役割 |
| サイトマップ | サイト全体のページ構造をまとめたファイルやリンク集 |
| 構造化データのマークアップ | 検索エンジンに内容を分かりやすく伝えるためのコードを記述すること |
| スニペット | 検索結果に記事の説明文を載せられる場所 |
| メタディスクリプション | 検索結果に表示される説明文で、自由に内容を変えられる |
| CTR(クリック率) | 検索結果に表示された回数に対してのクリックされた割合 |
| PV(ページビュー) | そのページが閲覧された回数 |
| CV(コンバージョン) | 商品購入や資料請求(問い合わせ)など、成果につながった行動 |
SEO用語は、最初からその細かい意味をすべて暗記する必要はありません。
「なんとなくこういう方向性で大事なんだな」と理解するだけでも十分で、SEO対策を実施していく中で自然と理解は深まっていきます。
SEO対策をするメリット・デメリット
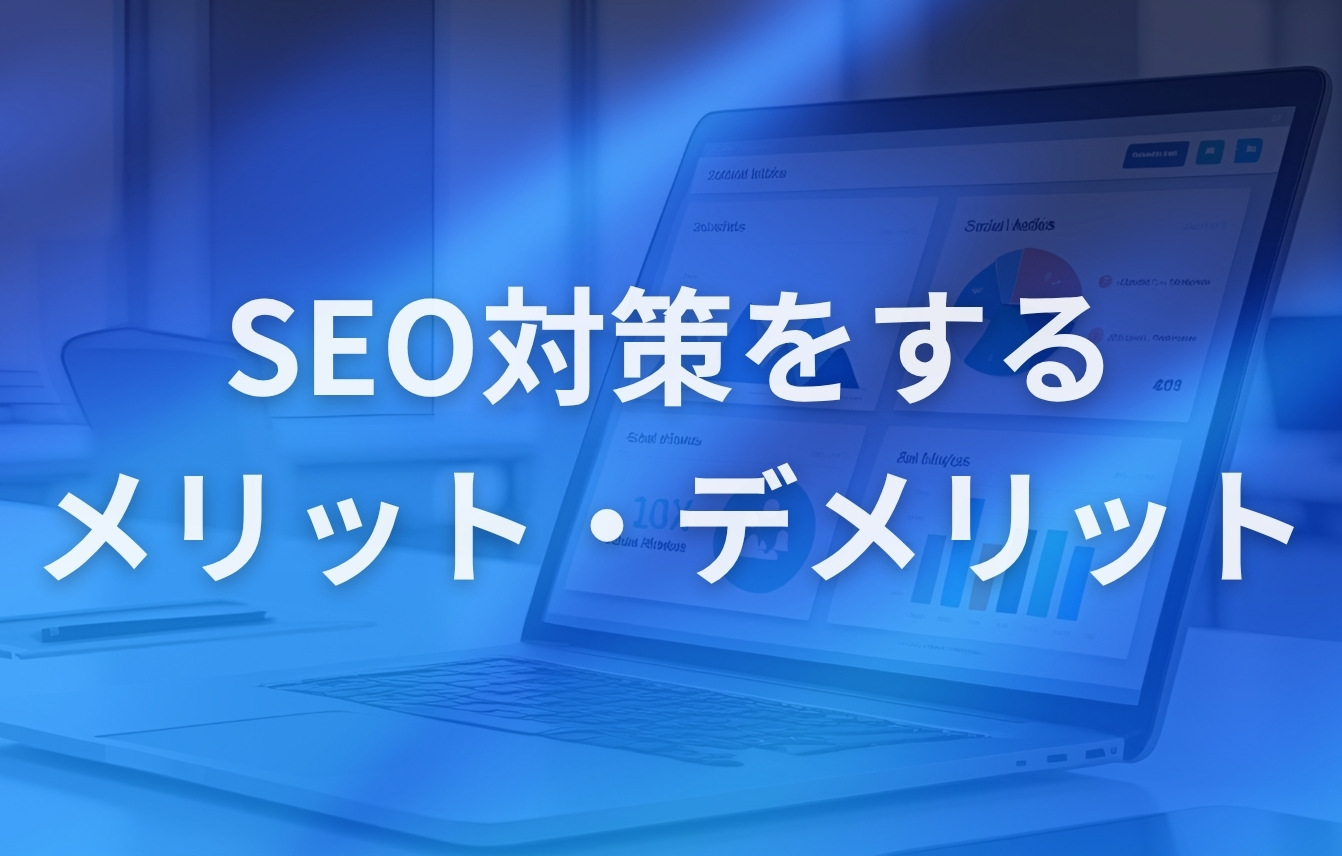
SEO対策は、効果的なネット集客の手段として、多くの企業に取り入れられています。
広告費を抑えつつ長期的にアクセスを集められるなど、大きなメリットがある一方で、成果が出るまでに時間がかかったり、検索エンジンのアルゴリズムに左右されやすいといった注意点も存在します。
ここでは、そのようなSEOのメリットとデメリットを整理し、SEO対策を始める前に知っておきたいポイントを解説します。
SEO業界20年、取引実績5,000社で多種多様な企業様の課題解決と成長をサポートしてまいりました。
完全内製の一貫体制でSEO支援を行い、専属のSEO研究チームが「分析→実装→検証→改善」 のサイクルを高速で回します。
問い合わせ増加・ブランディングを全力でサポートいたします。
メリット①広告費を抑えて集客できる
SEO対策の大きな魅力は、広告費を抑えながら集客できる点です。
リスティング広告のようにクリックごとに費用がかかる仕組みと違い、SEOは上位表示さえできれば、基本的に無料でアクセスを集められます。
特に中小企業や個人事業主のような、限られた予算の中で持続的に集客を確保できることは大きな強みです。
メリット②クリック率が増え売上促進につながる
SEO対策によって上位表示された記事は、実際にクリック率が向上することが分かっています。
アメリカのSEOの研究を行う会社「First Page Sage」の2025年のデータによると、通常検索で1位に表示された記事のクリック率は39.8%という結果が出ています。
一方で、検索順位6~10位のような下位にあたる記事のクリック率は5%未満で、順位が下がるほどクリック率も下がる傾向にあります。
また、リスティング広告はSEOの1位記事よりも上位に複数表示されていますが、最高でも2.1%と低く、検索順位8位の記事と同等のクリック率しか得られていないことも分かります。
このように、SEOで上位に表示されることで、クリック率が増え売上促進につながることは明らかです。
| 検索結果 | クリック率 |
|---|---|
| リスティング広告1 | 2.1% |
| リスティング広告2 | 1.4% |
| リスティング広告3 | 1.3% |
| リスティング広告4 | 1.1% |
| 検索順位 1位 | 39.8% |
| 検索順位 2位 | 18.7% |
| 検索順位 3位 | 10.2% |
| 検索順位 4位 | 7.2% |
| 検索順位 5位 | 5.1% |
| 検索順位 6位 | 4.4% |
| 検索順位 7位 | 3.0% |
| 検索順位 8位 | 2.1% |
| 検索順位 9位 | 1.9% |
| 検索順位 10位 | 1.6% |
参照元:First Page Sage
メリット③信頼性・ブランド力が向上する
検索結果の上位に自社サイトや記事が並ぶことは、それ自体がユーザーからの信頼獲得につながります。
人は検索結果で見たものを無意識に「上にある=評価されている」と感じやすいため、自然とブランドへの好感や安心感が高まります。
これは競合との差別化にも直結し、広告だけでは得られにくい長期的なブランド価値を高めることにもつながります。
メリット④記事やコンテンツが会社の資産として残る
SEO対策として作成した記事やコンテンツは、時間が経っても会社の資産として残り続けます。
広告の場合は出稿を止めれば即座に表示されなくなりますが、SEOは上位に表示されていれば長期間にわたって集客を担ってくれます。
特に検索ニーズが長く続くジャンルの記事は、一度上位を獲得すると継続的に見込み客を呼び込む仕組みとなり、営業活動を自動化するような効果も期待できます。
SEO業界20年、取引実績5,000社で多種多様な企業様の課題解決と成長をサポートしてまいりました。
完全内製の一貫体制でSEO支援を行い、専属のSEO研究チームが「分析→実装→検証→改善」 のサイクルを高速で回します。
問い合わせ増加・ブランディングを全力でサポートいたします。
デメリット①成果が出るまでに時間がかかる
SEO対策は、短期で結果が見える施策ではありません。
検索エンジンがサイトを評価するまでには、クローラーの巡回・インデックス登録・アルゴリズムによる順位付けといったプロセスを経る必要があり、その間に数か月単位の時間がかかるのが一般的です。
特に新規のドメインや実績の少ないサイトでは、評価が定着するまでに時間を要します。
そのため、SEO対策に特化した記事やコンテンツを投稿したとしても、最初のうちは上位を取るのが難しい可能性があります。
「記事を公開すればすぐに上位表示できる」と考えていると、期待とのギャップに悩むことになるでしょう。
デメリット②アルゴリズムの変化に左右される
検索順位はGoogleのアルゴリズムによって日々決定されていますが、そのアルゴリズムは頻繁にアップデートされています。
つまり、せっかくSEOで成果を出しても、外部環境の変化によって順位が変動するリスクが常につきまといます。
アルゴリズムの変更に対応するためには、公式ガイドラインを常にチェックし、コンテンツの品質の改善を継続することが不可欠です。
デメリット③継続的な運用が必要になる
SEO対策は、一度記事を公開して終わりではなく、その後の継続的な運用が欠かせません。
例えば、検索ニーズや競合は常に変化するため、古い記事は定期的にリライトして最新情報に更新する必要があります。
また、内部リンクの最適化やページ表示速度の改善など、技術的なメンテナンスも重要です。
さらに新しい記事を増やし続けることでも、サイト全体の評価が高まり、ドメインパワーの強化につながります。
デメリット④競合が多いと上位表示が難しい
SEOは多くの企業や個人が取り組んでいるため、特に人気のあるキーワードでは競合が激しくなります。
例えば「ダイエット」や「転職」のようなビッグキーワードは、大手企業や高いドメインパワーを持つサイトが上位を独占していることが多く、新規参入のサイトが上位表示を狙うのは容易ではありません。
そのため、中小企業や個人サイトが成果を出すには、ニッチなロングテールキーワードを狙ったり、専門性を活かした独自の切り口で記事を作成する工夫が必要になります。
SEOの検索順位が決まるまでの流れをわかりやすく解説
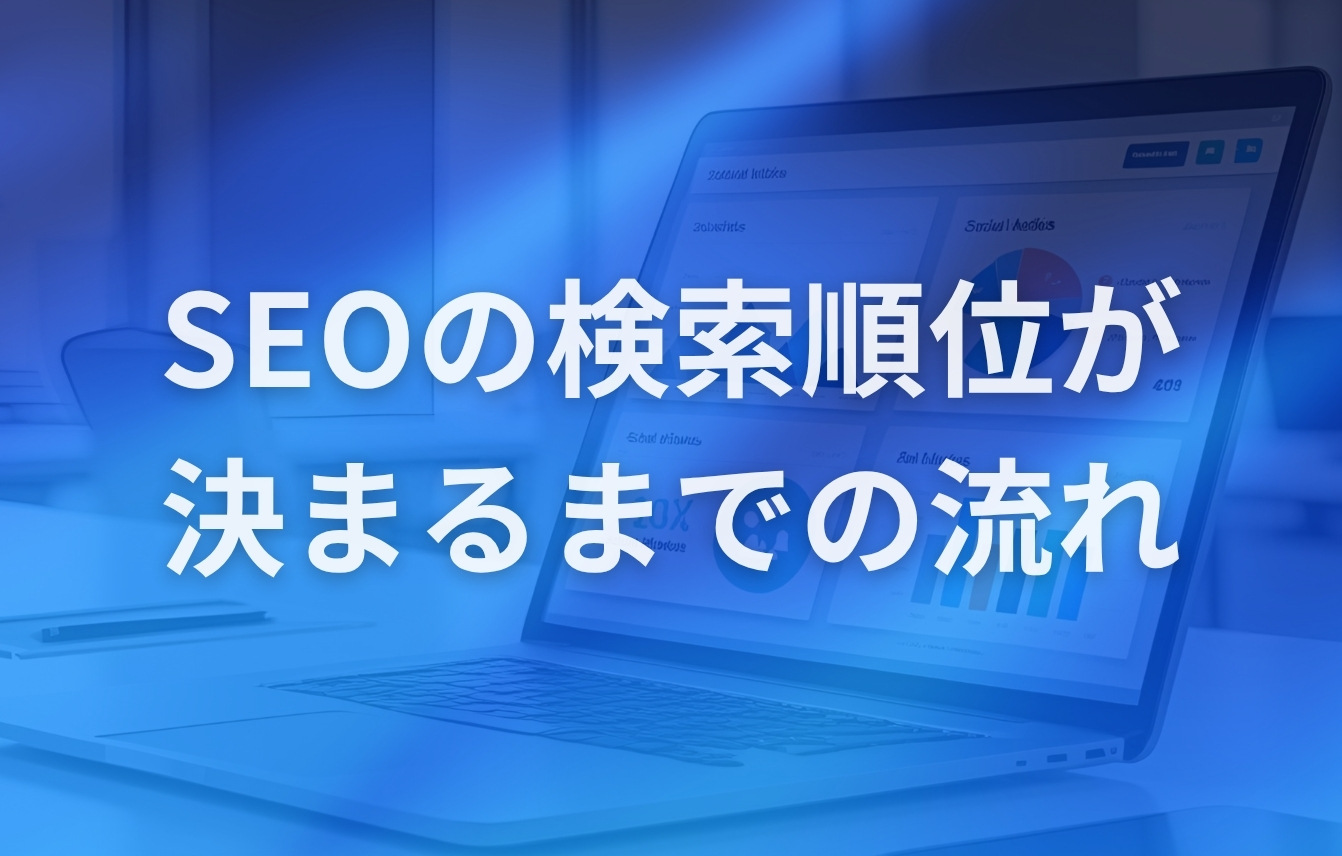
Googleの検索結果にページが表示されるまでには、以下のような流れに沿って順位が決定しています。
- クローラーによるサイト巡回(クロール)
- ページ情報の登録(インデックス)
- 検索アルゴリズムによるランキング処理
- 検索結果への表示
- ユーザーが検索結果をクリック
- 検索順位のフィードバックと更新
このように、まず流れを理解すれば、SEOの仕組みがより理解しやすくなります。
ここからは、それぞれのステップについて、順番にわかりやすく解説していきます。
① クローラーによるサイト巡回(クロール)
まず、Googleのクローラーと呼ばれるロボットがサイトを巡回します。
このことを「クロール」とも言います。
クローラーはインターネット上を常に移動し、新しいページや更新されたページを見つけ出します。
その際、内部リンクや外部リンク等をたどってページを発見する仕組みになっています。
つまり、クローラーに発見されやすいようにサイト構造を整えたり、外部サイトからリンクをもらったりすることが重要です。
② ページ情報の登録(インデックス)
クローラーによって発見されたページは、そのまま検索結果に表示されるわけではありません。
次に、インデックスと呼ばれる工程を経て、Googleのデータベースにページの情報が登録されます。
インデックスとは、ページのテキストや画像、動画、見出し構造などを整理し、検索エンジンが理解できる形に変換し、登録されることです。
インデックスで重要なのは、検索エンジンが内容を正しく認識できるようにすることです。
例えば、見出しタグの適切な使用や構造化データによる情報の補助は、インデックスの精度を高める方法の一つです。
③ 検索アルゴリズムによるランキング処理
インデックスに登録されたページは、Googleのアルゴリズムによって検索順位のランキングが決定されます。
アルゴリズムは数百以上の要素を組み合わせて、どのページがユーザーにとって最も有益かを判断しています。
代表的な要素には、以下のようなものがあります。
- コンテンツの質や検索意図との一致度
- 被リンクの有無
- E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)
- ページの表示速度
これらは、ほんの一例です。
また、アルゴリズムは常に進化しており、年に数回は大きなコアアップデートが実施されます。
そのため、検索順位は固定されたものではなく、継続的に改善し続けることが求められます。
検索順位を決めるGoogleのアルゴリズムの詳しい仕組みは、この後の章で分かりやすく解説していきます。
④ 検索結果への表示
ランキング処理を経たページは、いよいよユーザーの検索結果に表示されます。
ランキング処理されたページは、その中でオーガニック検索の結果に表示されます。
検索順位は基本的に1位から順に並びますが、実際の画面では広告やその他の枠が上にある場合も多く、必ずしも1位が画面最上段にあるとは限りません。
オーガニック検索とは、広告などを含まない「自然な」通常の検索結果のことを指します。
⑤ ユーザーが検索結果をクリック
検索結果に表示されたページは、ユーザーが興味を持ってクリックすることで初めてアクセスにつながります。
ここで大きな役割を果たすのが、タイトルタグとメタディスクリプションです。
検索ユーザーは表示されたわずかな情報から、自分の欲しい情報かどうかを判断するため、魅力的で検索意図に沿ったタイトルや説明文であることが重要です。
上位に表示されていてもクリックされなければ集客にはつながりません。
逆に、下位にあっても工夫されたタイトルでCTR(クリック率)が高まれば、「ユーザーに支持されているページ」と見なされ、順位改善につながることもあります。
⑥ 検索順位のフィードバックと更新
ユーザーが検索結果をクリックした後、その行動は検索エンジンにフィードバックされています。
例えば、クリック率や滞在時間、直帰率などの行動データは、次回以降のランキング評価に影響を与える要素とされています。
これにより検索順位は、常に更新・変動を繰り返す仕組みになっています。
SEO対策が「一度上位を取ったら終わり」ではないのは、このためです。
SEOでGoogleが検索順位を決める仕組み
Googleが公式に公開している「検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド」は、SEOの検索順位を理解するうえで最も信頼できる公式情報です。
ここに書かれている内容を実践すればSEOに強くなれますが、専門的で文量も多く、やや分かりにくい部分もあります。
ここでは、Google公式ガイドをわかりやすくかみ砕いて、初心者でも理解しやすい形でポイントを解説していきます。
SEO業界20年、取引実績5,000社で多種多様な企業様の課題解決と成長をサポートしてまいりました。
完全内製の一貫体制でSEO支援を行い、専属のSEO研究チームが「分析→実装→検証→改善」 のサイクルを高速で回します。
問い合わせ増加・ブランディングを全力でサポートいたします。
コンテンツの質と検索意図の一致
Googleは、単にキーワードが含まれているだけのコンテンツではなく、「ユーザーが求めていること・知りたいこと」に応えているかどうかを重視します。
ここで重要になるのが、E-E-A-T(Experience=経験、Expertise=専門性、Authoritativeness=権威性、Trustworthiness=信頼性)です。
スターターガイド内でも、コンテンツが「有用で信頼性の高い、ユーザー第一」であることが強調されており、E-E-A-Tはその評価指標の一つとされています。
以下に、どんな記事がE-E-A-T評価の高い記事なのか、その例を挙げておきますので、参考にしてください。
| 評価項目 | 具体例 |
|---|---|
| Experience(経験) | 私は小児科医として20年以上診療に携わり、特に季節ごとの風邪予防指導を行ってきました。 |
| Expertise(専門性) | WHO(世界保健機関)のガイドラインに基づき、手洗いの方法や生活習慣を具体的に紹介します。 |
| Authoritativeness(権威性) | 厚生労働省の公式サイトでも「うがい・手洗いの徹底」が風邪予防として推奨されています。 |
| Trustworthiness(信頼性) | 本記事は医療監修を受け、運営者情報と監修者プロフィールを明示していますので、安心して参考にしていただけます。 |
キーワードとコンテンツの最適化
Googleのスターターガイドでは、主に①ページのタイトルタグ、②URL、③見出し構成(H2・H3など)、④本文中のキーワードの使い方が、検索エンジンに内容を理解してもらうために重要とされています。
実際にそれぞれ具体的にどうすればいいか「東京 ラーメン」のキーワードで上位を狙うことを想定して、解説します。
「東京 ラーメン」での上位記事を想定
①ページのタイトルタグ
【2026年】東京のおすすめラーメン店10選|行列必至の人気店を紹介
→タイトルの前半に「東京 ラーメン」を入れて、検索ユーザーが一目で分かるようにする。
②URL
「example.com/tokyo-ramen」
→シンプルで分かりやすく「東京 ラーメン」に沿った内容にする。英語にすることで国際的にも通じる。
③見出し構成(H2、H3など)
H2:東京ラーメンの最新トレンド
H3:SNSで話題の映える東京ラーメン
H2:東京で絶対に食べたいおすすめラーメン店
H3:新宿エリアの人気ラーメンランキング
H3:池袋エリアの人気ラーメンランキング
→各見出しに「東京」「ラーメン」を自然な形で入れる。
④本文中のキーワードの使い方
「東京には数え切れないほどのラーメン店がありますが、その中でも特に人気を集めているのが新宿・池袋エリアです。本記事では、東京のラーメンの最新トレンドを踏まえつつ、おすすめのお店を紹介していきます。」
→「東京 ラーメン」を冒頭の文脈の中に自然な形で入れる。
キーワードの最適化はSEOに欠かせませんが、使いすぎは逆効果になります。
内部リンク構造の最適化
サイト内のリンク構造は、Googleのクローラーがサイト全体を巡回(クロール)しやすくするための地図のような役割を果たします
具体的には、関連する記事同士をリンクでつなげ、適切なアンカーテキストを使ってリンクを貼ったり、階層構造がわかりやすいサイトにすることが挙げられます。
適切なアンカーテキストの例
✖ →「詳しくはこちら」
〇 →「東京のラーメンランキングはこちら」
階層構造がわかりやすいサイト例(パンくずリスト)
✖ → ホーム > 東京のラーメンランキング
〇 → ホーム > グルメ > 東京 > ラーメン > 東京のラーメンランキング
「パンくずリスト」とは、ユーザーが「サイト内のどの位置にいるか」を示すナビのようなもので、上位階層に戻りやすくし、検索エンジンにもサイト構造を伝える役割があります。
外部リンク(被リンク)とドメインパワー
外部リンク(被リンク)は、他サイトから自分のページに対する推薦・投票のようなものです。
Googleの公式ガイドにも、外部の信頼できるサイトからリンクをもらうことが、サイト全体の評価を高める手段として言及されています。
外部リンク(被リンク)は、ただ多いだけでは意味がなく、どんなサイトか、どれだけ関連性や信頼性のあるサイトかも評価に関連します。
つまり、外部リンク(被リンク)は、量より質が求められます。
また、ドメイン全体の評価(ドメインパワーとも呼ばれる)は、そのサイトがどれほど信頼されてきたか、他サイトからどれくらい外部リンク(被リンク)を獲得したかによっても左右されます。
ページ体験(モバイル対応・表示速度・コアウェブバイタル)
Googleは「ユーザーが快適にページを利用できるか」も重視しています。
例えば、スマホで見たときに文字やボタンが小さすぎると使いづらく、順位評価のマイナスになります。
また、ページの読み込み速度が遅ければ、ユーザーが離脱する可能性が高くなるため、これも評価が下がる要因です。
特に高画質の画像が多く使われているサイトは、読み込みが遅くなるため、画像データを圧縮して読み込み速度を改善するような対策も必要になります。
このようなことを、総合的に評価する指標を「Core Web Vitals(コアウェブバイタル)」と言います。
Core Web Vitalsは「表示がどれだけ速いか」「操作がすぐ反応するか」といったページ体験を数値化したGoogle独自の指標です。
特にスマホ依存が高まっている現代においては、無視できないSEOの重要要素の一つです。
構造化データによる検索結果の強化
構造化データとは、検索エンジンに「このページが何について書かれているか」を明確に伝えるための暗号のようなものです。
これを設定しておくと、検索結果に星評価やパンくずリスト、イベント情報のようなリッチリザルトが表示されやすくなります。
たとえば「ラーメン店のレビュー記事」に構造化データを入れると、検索結果に「★4.5」や「営業時間」が表示され、クリック率(CTR)の向上につながります。
コンテンツ内容を正しく理解してもらうだけでなく、検索結果の視覚的に目立つ効果があるのが特徴です。
通常の検索結果(構造化データなし)
東京のおすすめラーメン店10選|人気店を紹介
example.com/tokyo-ramen
東京で話題のラーメン店を厳選して紹介します。新宿や池袋の人気店を中心にまとめました。
構造化データあり(リッチリザルト表示)
東京のおすすめラーメン店10選|人気店を紹介
example.com/tokyo-rame
★4.5(120件のレビュー) | 営業時間: 11:00〜22:00
東京で話題のラーメン店を厳選して紹介します。新宿や池袋の人気店を中心にまとめました。
ユーザー行動シグナル(クリック率・直帰率・滞在時間)
Googleの公式ガイドには明確に記載されていないものの、業界の知見から「ユーザー行動」も検索順位に影響を与える可能性が高いと考えられているため、最後に触れておきます。
例えば、検索結果でCTR(クリック率)が高ければ「このページは検索意図に沿っている」と判断され、評価されやすい傾向があります。
一方で、クリックされたもののすぐに離脱される(直帰率が高い)場合は「期待した情報がなかった」と見なされて評価が下がる可能性があります。
逆に、記事を最後まで読んでもらえたり、他のページにも移動してもらえれば、滞在時間や回遊性が高まり「満足度の高いサイト」として評価されやすくなります。
ユーザー行動シグナルは、Googleの公式な指標として公表されているわけではありません。
ユーザー体験を高める工夫は、SEOの最終目的であるコンバージョンに直結することなので、積極的に対策する価値のあることと言えます。
自分でできる!SEO内部施策チェックリスト15選
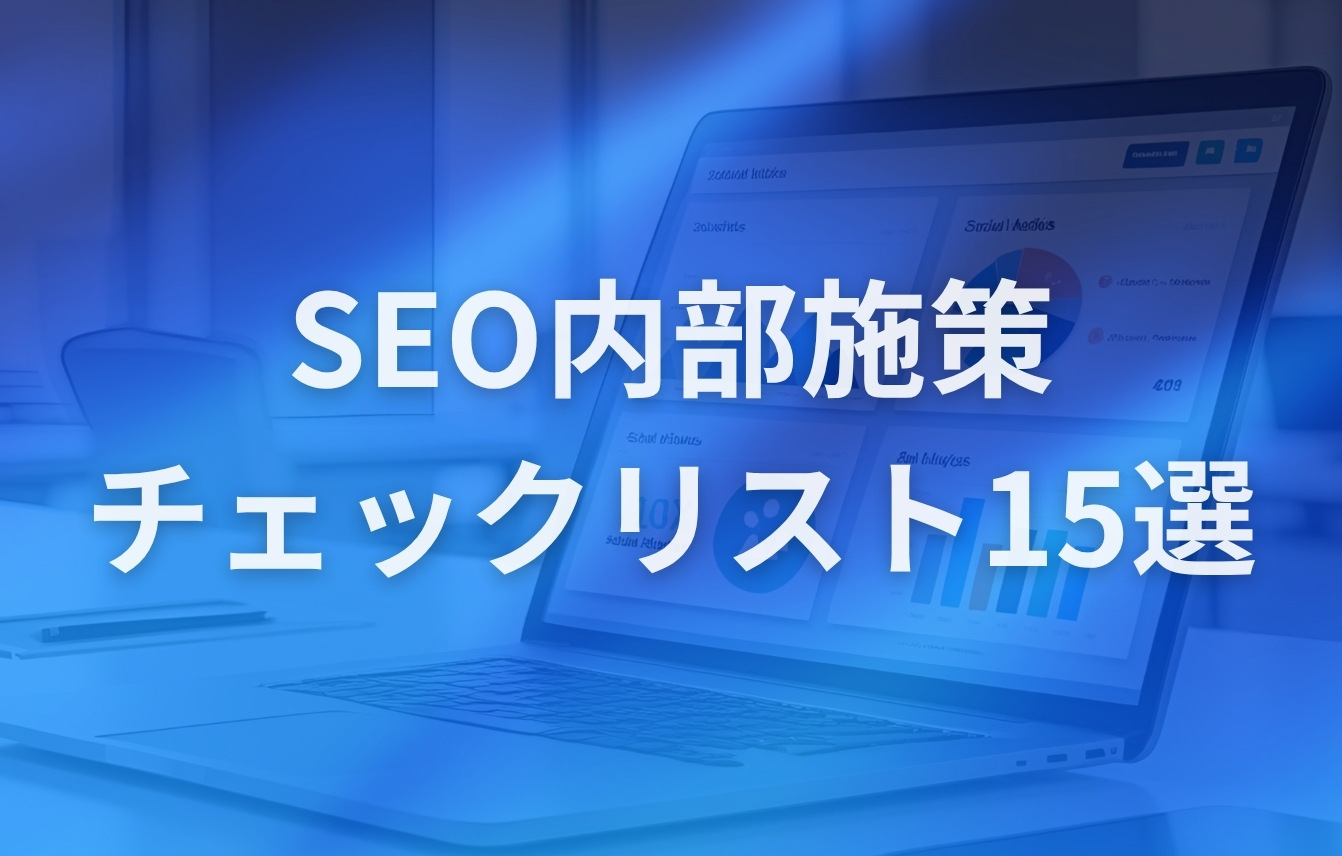
SEOの内部施策は、細かい施策が数多く存在しますが、すべてを一度にやろうとすると初心者にとってはハードルが高く感じられます。
そこでここでは、初心者でも実践しやすい基本的な施策を、15個のチェックリストにまとめました。
一つ一つは小さな施策ですが、これらを積み重ねることで検索順位に大きな差が出てきます。
まずは自分のサイトで、まだできてないことがないか確認しながら、改善ポイントを見つけていきましょう。
SEO内部施策チェックリスト15選
- タイトルタグに主要キーワードを前の方に自然に含める
- メタディスクリプションを120字以内で魅力的に書く
- E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を意識した内容にする
- H2・H3見出しにも主要・関連キーワードを自然に入れる
- URLを短くシンプルにする(例:/tokyo-ramen)
- 定期的に古い記事の情報を見直し、最新にアップデートする
- 画像にalt属性(代替テキスト)を設定する
- 関連記事を内部リンクでつなぐ
- アンカーテキストは「こちら」ではなく内容を具体的に書く
- パンくずリストを設置し、階層をわかりやすくする
- サイトマップを作成し、Search Consoleに登録する
- スマホで表示を確認し、見やすく操作しやすいデザインにする
- 画像を圧縮してページの読み込み速度を改善する
- SSL化して、URLを「https://」にする
- 記事の冒頭に結論や要点をまとめて、離脱を防ぐ
上位を狙うSEO記事の書き方の具体例
SEO記事を書くときに重要なのは、単にキーワードを入れることではなく、「誰が」「どのように」「なぜ」書いた記事なのかを意識することです。
これはGoogleが公開している「検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド」でも強調されていて、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を高める基盤にもなります。
この「誰・どのように・なぜ」の視点を意識しながら、具体的な手順でSEO記事の書き方を解説します。
SEO業界20年、取引実績5,000社で多種多様な企業様の課題解決と成長をサポートしてまいりました。
完全内製の一貫体制でSEO支援を行い、専属のSEO研究チームが「分析→実装→検証→改善」 のサイクルを高速で回します。
問い合わせ増加・ブランディングを全力でサポートいたします。
① キーワード選定と検索意図の分析
SEO記事を書くにあたって、まず始めるのがキーワードの選定です。
どんなキーワードで上位を狙いたいのか、これを決めないと記事の構成を組むことができないからです。
今回は「東京 ラーメン」で上位を狙うことを想定して話を進めていきます。
「東京 ラーメン」で検索する人の気持ち
- 東京23区のエリア別でお店が知りたい
- SNSでバズってる高評価のお店が知りたい
- 今年開店した新しいお店が知りたい
- とんこつ、家系等、味の種類別でおすすめのお店を知りたい
- 各お店の営業時間やGoogleマップの地図も見たい
このように、あらゆる角度から検索意図をあぶりだすことで、構成作成時に記事の方向性がブレにくくなります。
また競合分析時に、競合がここであぶり出した要素を取り入れていなかったら、それは競合と差をつけられる有益な情報ということにもなります。
② 競合記事の分析
検索意図をまとめたら、次に競合記事の分析を行います。
1~5位に表示される競合記事は、Googleに何らかの要素が評価されたから1~5位にいます。
つまり競合記事の傾向は、上位に表示されるためのヒントが隠されていることになります。
競合記事の分析には、以下のポイントを押さえましょう。
・どんな構成・キーワードを使っているか
「おすすめ10選」「ランキング形式」「エリア別」などキーワードと構成をチェック。
・どんな情報をどのように見せているか
写真の有無、営業時間や地図の記載、口コミ引用など情報の見せ方をチェック。
・不足している情報はないか
例えば「SNSで話題の店」「開店したばかりのお店」が載っていないと、競合との差別化のチャンス。
③ サジェストと検索ボリュームの調査
読者の検索ニーズをより掴むために、サジェストキーワードとその検索ボリュームを調査します。
サジェストキーワードとは、「東京 ラーメン」と入力したときに検索窓に続けて表示される検索候補のことです。
このサジェストは、読者が知りたい頻繁に検索されているキーワードのため、取り入れることでより検索意図を網羅した記事にすることができます。
「東京 ラーメン」のサジェストの検索ボリューム
(※これは解説のための架空の数値です)
東京 ラーメン 人気 18,000
東京 ラーメン ランキング 12,000
東京 ラーメン 深夜 6,500 ← 想定していなかったニーズの発見!
東京 ラーメン 新宿 8,200
東京 ラーメン 家系 5,100
東京 ラーメン 行列 3,800
東京 ラーメン 2025 2,200
例えば、ここで「深夜」というここまで想定していなかったキーワードが、意外とニーズのある情報だったことに気付くことができます。
④ タイトルと見出しの作成
ここまで①~③で、調査分析した情報をすべて踏まえて、タイトルと見出しを作成します。
SEO記事の順位を大きく左右するのが、タイトルと見出しです。
検索ユーザーはまずタイトルを見て記事を開くかどうかを判断し、見出しを見ながら記事を読み進めます。
それぞれのポイントを、まとめました。
タイトル作成のポイント
- 主要キーワードはタイトルの前半に入れる → 「東京 ラーメン」
- 検索意図やニーズの高い情報を盛り込む → 「SNS」「エリア別」
- クリックしたくなる要素も入れる → 「おすすめ」「2026」
タイトルの例
【2026年】東京のおすすめラーメン店|SNS話題のお店をエリア別紹介
ちなみにタイトルの文字数は、30~35文字程度がおすすめです。長すぎると検索結果で省略されてしまいます。
見出し作成のポイント
- 検索意図を網羅する → 「エリア別」「味の種類」
- サジェストでボリュームのあったキーワードを盛り込む → 「深夜」「ランキング」
見出しの例
H2:新宿エリアの人気ラーメンランキング
H3:深夜まで営業している新宿ラーメン店
H3:とんこつで人気の新宿ラーメン店
⑤ 本文の執筆(内部リンクや画像の活用)
構成が完成したら、本文執筆に映ります。
本文の執筆で、心掛けることは「結論ファースト」です。
まわりくどい言い回しや、答えを後ろの方に持ってくるような文章は、読者が離脱しやすいからです。
| 良い例(結論ファースト) | 東京で深夜まで営業しているラーメン店なら、新宿の〇〇が特におすすめです。 |
|---|---|
| 悪い例(結論を後回し) | 東京のラーメン店は数多くあります。その中でも深夜まで営業している店はいくつか存在します。いろいろなお店がありますが、特におすすめなのは新宿の〇〇です。 |
また、文章だけではどうしてもコンテンツとして興味がそそられないつまらないものになります。
そのため、文章のなかに画像や表、引用データ等を用いて、記事に抑揚をつけてあげることも大切です。
画像を使用するときには、容量を圧縮してページの読み込み速度を遅らせない配慮が必要です。
また画像には、alt属性(代替テキスト)とよばれるものがあり、ここに適切なキーワードを入れておくことで、Googleに画像を文字情報として認識してもらうことが可能になります。
例えば「新宿の家系ラーメンの写真」であれば、alt属性(代替テキスト)に「新宿 家系ラーメン 人気店の一杯」などと設定しておくと、SEOにプラスにつながります。
SEOコンサル会社よりSEO対策会社に依頼するのがおすすめ
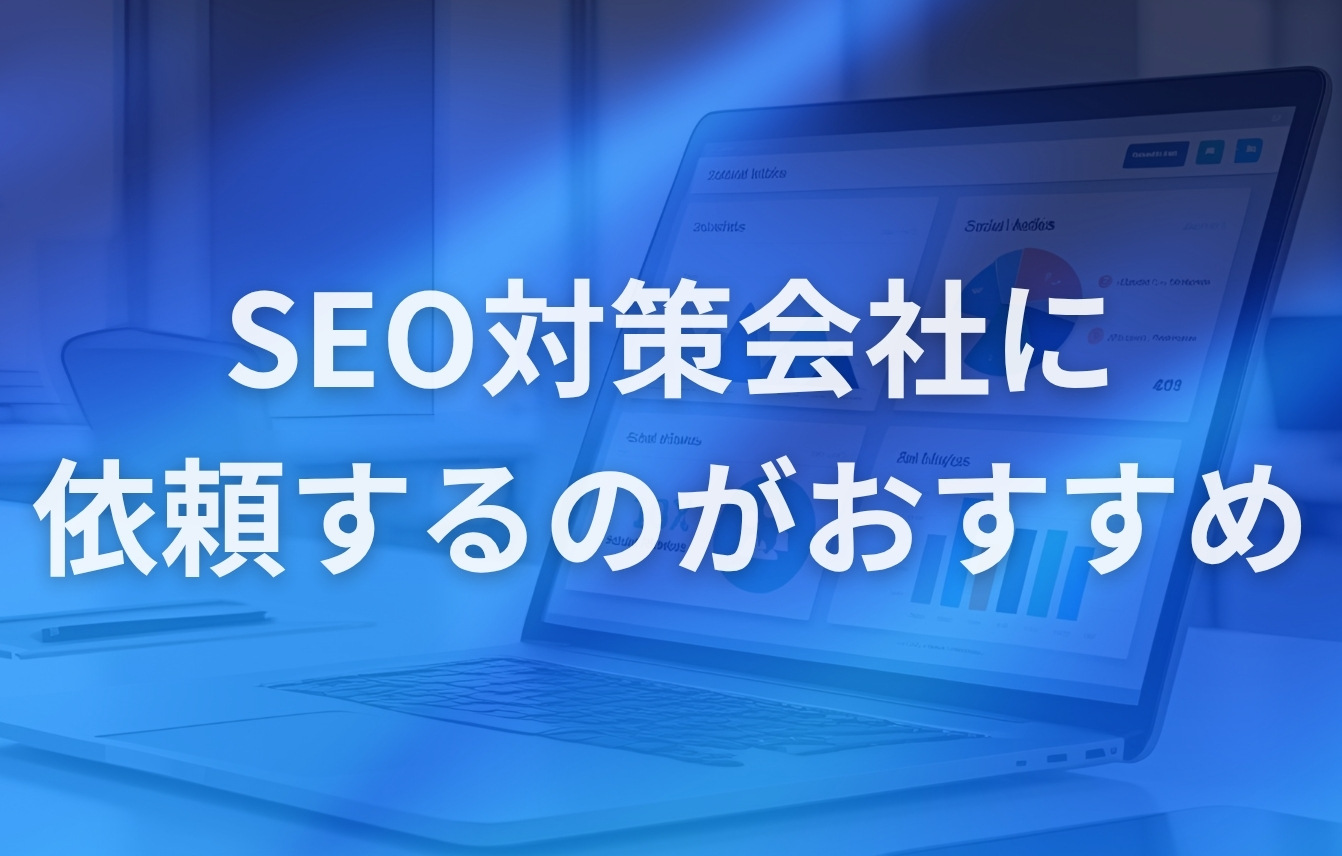
SEO施策を外部に依頼する時、「コンサルティング会社」と「実行型のSEO対策会社」のどちらを選ぶかで、その目的や成果は大きく変わります。
コンサルはアドバイス中心で、実務は自社に任されることが多い一方で、SEO対策会社は実際の施策まで行ってくれるのが特徴です。
また両方を担う会社もあるため、名前だけで判断せず「何をしてくれるのか」をしっかりと見極める必要があります。
SEO業界20年、取引実績5,000社で多種多様な企業様の課題解決と成長をサポートしてまいりました。
完全内製の一貫体制でSEO支援を行い、専属のSEO研究チームが「分析→実装→検証→改善」 のサイクルを高速で回します。
問い合わせ増加・ブランディングを全力でサポートいたします。
SEOコンサルよりSEO対策の会社がいい理由
そのため、社内にSEOに詳しい人材や時間的余裕がない企業では、提案を活かしきれず効果が出にくいことがあります。
社内に専門人材を抱える必要がなく、すぐに改善策を実施できる点が大きな強みです。
特に中小企業のような、専任のWeb担当者を置く余裕のない会社にとっては最大のメリットとなり、安定した成果につながります。
SEO対策会社の費用相場
SEO対策の費用の料金体系は、大きく3つに分けることができます。
固定報酬型
毎月の料金が決まっており、内部対策やコンテンツ制作、レポートなどを継続的に依頼できる形式。
安定した運用が可能。
成果報酬型
検索順位の上昇やアクセス数の増加といった成果に応じて費用が発生する形式。
成果が出るまでコストを抑えられるが、最終的には高額になることもある。
スポット型
内部施策の改善やSEO診断など、一時的に特定の作業を依頼する形式。
短期間で課題を解決したいときに適している。
また、SEO対策の費用相場は、企業規模によっても難易度が変わり、料金も大きく変わります。
ここでは中小企業を想定した、SEO対策の施策ごとの費用相場をまとめました。
| SEO対策内容 | 中小企業の費用相場 |
|---|---|
| サイト診断・分析 (コンサル・記事作成補助など) |
月額 約10〜50万円 |
| コンテンツSEO (記事作成) |
1記事 約5,000円〜3万円 月額 約10〜50万円 |
| SEO内部施策 (タグ修正・内部リンク改善など) |
月額 約10〜50万円 |
| SEO外部施策 (被リンク獲得支援) |
月額 約10〜50万円 |
中小企業でそこまで費用を掛けられない場合は、スポット契約で部分的にSEO施策を依頼して、コストを抑えることもおすすめです。
SEO対策会社の選び方のポイント
SEO対策会社は数多く存在しますが、費用やサービス内容はさまざまです。
以下の3つのポイントを意識して、比較検討することをおすすめします。
①実績や事例を公開しているか
過去にどのような業種・サイトを改善したのか、実績や事例が明確な会社は信頼性が高い。
②施策内容が透明であるか
「順位を上げます」とだけ説明する会社は要注意です。
外部対策(被リンク獲得方法)など、具体的に何をするかを説明してくれる会社でないと、不正な方法でペナルティを受けるリスクがあります。
③レポートや定期的な報告があるか
SEOはすぐに成果が出るものではないため、進捗を可視化して報告してくれる体制があることも、依頼する側としては大切な要素です。
SEO業界20年、取引実績5,000社で多種多様な企業様の課題解決と成長をサポートしてまいりました。
完全内製の一貫体制でSEO支援を行い、専属のSEO研究チームが「分析→実装→検証→改善」 のサイクルを高速で回します。
問い合わせ増加・ブランディングを全力でサポートいたします。
Googleが提供する無料SEOツール
SEO対策を行ううえで欠かせないのが、Googleが公式に提供しているツールです。
どれも基本的な機能は無料で利用でき、記事の改善や構成立案に役立てることができます。
ここでは代表的な3つのツールを紹介します。
Google Analytics(グーグルアナリティクス)
Google Analyticsは、自分のサイトにどんな人が訪れているのかを詳しく分析できるツールです。
Google Analyticsでできること
- サイト全体や記事ごとのアクセス数を確認できる
- 読者のデバイス(スマホ・PC)や地域を把握できる
- ページごとの滞在時間や離脱率を確認できる
改善点を見つけたり、どんなコンテンツが人気なのか、求められているものを知ることは、サイト改善の方向性を決める時に役立ちます。
Google Search Console(グーグルサーチコンソール)
Google Search Consoleは、自分のサイトがGoogle検索でどのように表示され、どのキーワードから流入しているかを確認できるツールです。
Google Search Consoleでできること
- サイトが正しくインデックスされているか確認できる
- どんな検索キーワードで表示・クリックされているか分かる
- ページのエラー(モバイル対応や表示速度など)をチェックできる
- 検索平均順位が分かる
SEOの成果を測定したり、エラーを見つけて修正する時に役立てることができます。
Google Search Console上で、「クエリ」と呼ばれているものが「実際に検索されているキーワード」のことを指しています。
キーワードプランナー
キーワードプランナーは、Google広告向けのツールですが、SEO記事のキーワード調査にも活用できます。
キーワードプランナーでできること
- キーワードの月間検索ボリュームを調べられる
- 関連するキーワードを一覧で確認できる
- 競合度の目安を知ることができる(広告機能だがSEOでも目安になる)
狙いたいキーワードの検索ボリューム(実際の検索数)の分析や、関連する検索語句を見つけることが可能です。
SEO対策を自分で勉強できるおすすめの本
SEOは、日々アルゴリズムがアップデートされる分野ですが、基本の考え方や土台は変わりません。
そのためSEOを体系的に学べる本を手元に置いておけば、ネット情報に振り回されず、自分で判断できる力が身につきます。
ここでは、初心者でも自分で勉強していけるおすすめのSEO本を3冊を紹介します。
SEO業界20年、取引実績5,000社で多種多様な企業様の課題解決と成長をサポートしてまいりました。
完全内製の一貫体制でSEO支援を行い、専属のSEO研究チームが「分析→実装→検証→改善」 のサイクルを高速で回します。
問い合わせ増加・ブランディングを全力でサポートいたします。
いちばんやさしい新しいSEOの教本|初心者におすすめの入門書
「いちばんやさしい新しいSEOの教本 第3版」は、SEO入門書の定番を5年ぶりに全面リニューアルした最新の教本です。
著者は江沢真紀氏、コガン・ポリーナ氏、西村彰悟氏の3名で、実務経験豊富な講師陣が担当しています。
Googleが重視するE-E-A-Tに対応した章を新設し、GA4、Microsoft Clarityといった最新ツールの解説が追加され、「AI時代も変わらないSEO」として再編集されています。
SEO初心者なら、まずは一冊持っておいて損はない、総合的な入門書です。
この本の購入者のレビュー(引用:Amazonより一部抜粋)
- 課題ごとに解説がありとてもわかりやすいです。初心者から中級者まで幅広く使える本です。
- 初心者から実務者まで使える、最新のSEOを網羅した一冊。
- 章立てもよく、わかりやすいです。はじめて読む本として最適だと思います。
沈黙のWebライティング|SEOライティングを学べる本
「沈黙のWebライティング —Webマーケッター ボーンの激闘— アップデート・エディション」は、2016年に初版が出版されて以降、SEOライティング分野の定番書として支持され続けてきたロングセラー本です。
2022年にアップデート版が刊行され、最新のSEOトレンドを反映した内容になっています。
物語仕立てのストーリー形式で展開されるため、専門用語が多くなりがちなSEOやWebライティングの知識を、まるで漫画を読むように直感的に理解できます。
検索意図を満たす記事の書き方や、E-E-A-Tを意識したライティング、読者を惹きつける見出し・本文構成など、実務に直結するノウハウが凝縮されています。
初心者だけでなく、文章で成果を出したいSEOライターやWeb担当者にとって必携の一冊です。
この本の購入者のレビュー(引用:Amazonより一部抜粋)
- ウェブライティングやSEOのことが短時間で分かりやすく、面白く学べるため、これは決定版。
- 漫画形式になっているので、読みやすいです。
- 大変勉強になりました。他のシリーズも読んでみたいです。Webマーケッターに必須の本!
これからはじめる SEO内部対策の教科書|SEO内部対策の実践向け
「これからはじめる SEO内部対策の教科書」は、SEOの中でも「内部対策」に特化して学べる実用的な一冊です。
2015年頃に初版が刊行され、SEO初心者でも理解しやすいよう専門用語をかみ砕いて解説している点が特徴です。
タイトルタグやメタディスクリプションの設定方法、H1・H2など見出しタグの使い方、内部リンクの張り方やサイト構造の最適化など、SEOの基本を着実に実行できる内容になっています。
「何から手を付ければいいのか分からない」という初心者や、企業の新任Web担当者にとって、即効性のある改善手順がまとめられているのが魅力です。
SEOの概念を学ぶというより、実際に手を動かして成果を出すための教科書としては、最適な一冊です。
この本の購入者のレビュー(引用:Amazonより一部抜粋)
- WEBについて、まだ知識の浅い人でもわかりやすい言葉で書いてあり、とても親切で、実践しやすい内容でした。
- SEOが何かも解らないひとなら、きっと役に立つと思う。何も対策してなければ、相当の効果を期待できると思いますよ。
SEO対策が意味ないと言われている理由
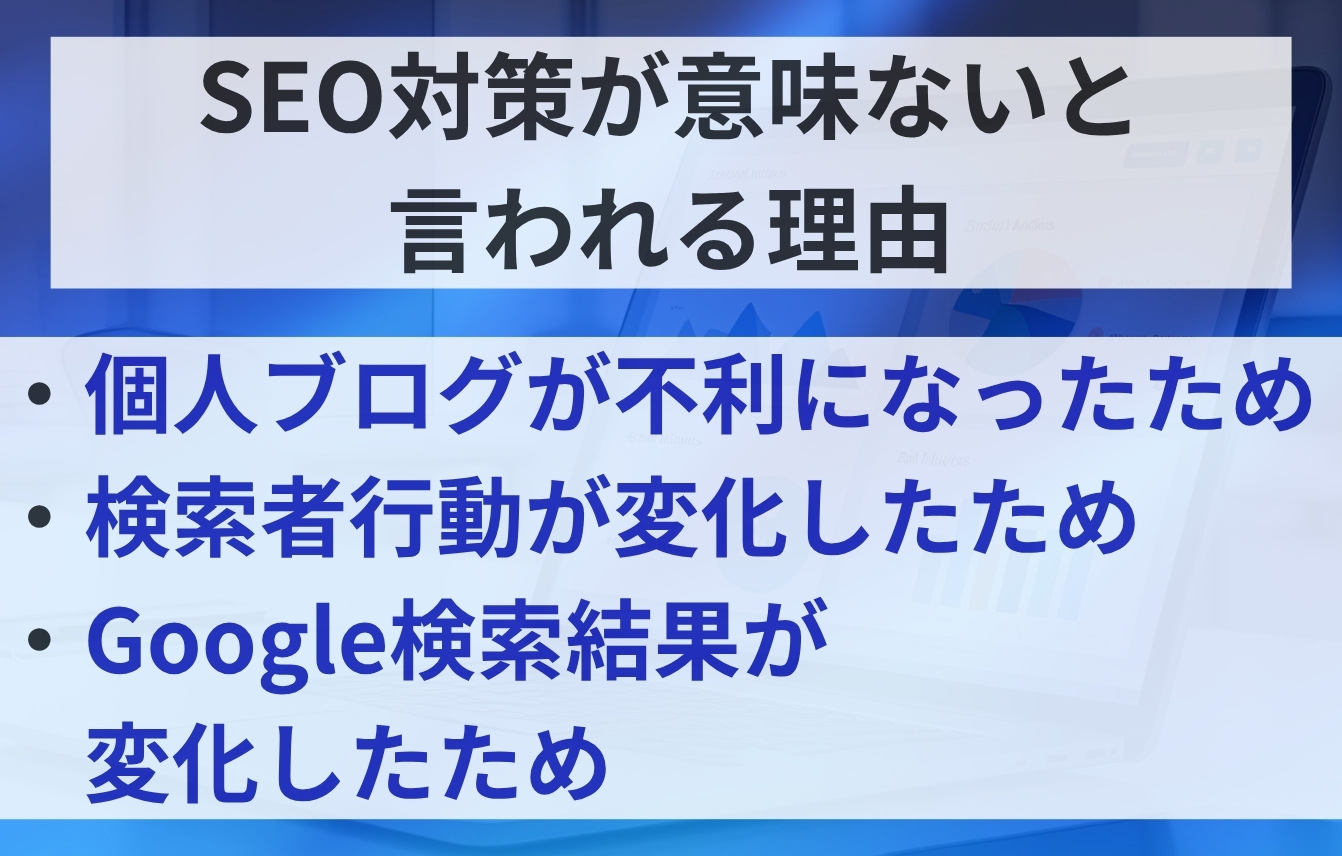
SEOは今も集客に有効な手段ですが、一部では「意味がない」と言われることがあります。
その背景には、検索エンジンやユーザー行動の大きな変化が関係しています。
特に近年は、Googleのアルゴリズムの大きな変化やAIツールの普及により、従来型のSEOだけでは成果が出にくい状況が生まれていることも事実です。
ここでは、その具体的な理由を解説します。
ドメインパワーが強すぎて個人ブログが不利になった
現在、SEOの世界では「ドメインパワー(サイト全体の評価)」がとても大きな影響力を持っています。
大手メディアや公式サイトは、長年の運営実績や豊富な被リンクによってドメインパワーが高く、その結果、同じキーワードと構成で記事を書いても、個人ブログが上位表示されにくいのが現実です。
例えば「東京 ラーメン」と検索した場合、上位は大手グルメサイトやニュースメディアが占める傾向が強く、個人が丁寧に書いた記事は埋もれてしまいます。
もちろん、ロングテールキーワードや独自性を出すことで勝てる余地もあります。
このように、王道キーワードでの戦いが難しくなっていることが「SEO対策が意味ない」と言われる理由の一つです。
AIツールによる検索者行動の変化
AIツールの発展と普及によって、検索ユーザーの行動にも変化が生まれてきています。
2022年、OpenAI社からリリースされた「ChatGPT」は、大規模言語モデルを使用した対話型の生成AIソフトで、その直感的な使い方は、AIに馴染みのなかった一般層にまでAIツールを普及させました。
これによって調べものをするときに「ググる」から「AIに聞く」へと行動がシフトした人が、一定数いることは明らかです。
例えば「東京のおすすめのラーメン店を知りたい」と思ったとき、従来はGoogle検索で「東京 おすすめ ラーメン」と検索していたのが、今はAIに直接ボイス入力で質問し、要約された答えを参考にする人が増えています。
このような変化が、Google検索の利用時間やクリック率の減少につながり、「SEO対策が意味ない」と言われる理由にもなっています。
ただし、AIは情報の正確性に欠けることが、最大の弱点です。
Googleの検索結果の変化
Googleの検索結果画面も、SEO対策に大きな変化を与えています。
SEOで上位に表示されるとクリック率が上がることは確かですが、検索結果画面には1~10位の記事以外の要素が近年増えてきています。
これらは、SEOで上位を取った記事へのクリックを妨害する要素にもなりうるため、そのような傾向を危惧した人から「SEO対策は意味ない」と言われているのです。
リスティング広告
ページ最上部を広告が埋め尽くすケースが多く、オーガニック1位が実質的にスクロールしないと見えない状態になる。
AI Overview(AIによる概要)
検索ワードの答えをAIが要約して最上部に表示。ユーザーが記事をクリックする前に解決してしまう。
強調スニペット
1位の記事が抜粋表示される場合もあるが、ユーザーが本文を見ずに満足して離脱するリスクがある。
関連する質問
Q&A形式で別記事が展開され、ユーザーのクリックが分散する。
ローカルパック(Googleマップ表示)
地図とともに店舗情報を表示。これもクリック分散につながる。
ナレッジパネル
企業・人物・場所などの概要が右側や上部に表示される。Wikipediaや公式サイトの参照が多い。
また2025年、Googleの検索窓の横には「AIモード」が常設されました。
これをクリックすると、対話型のAIソフトが開くようになり、より従来のGoogle検索が選ばれにくい仕様になってきています。
SEO対策のよくある質問(FAQ)
SEO対策は、初心者にとっては分からないことだらけだと思います。
この記事では、「SEOとは?」という基本的なところから、順位が決まる仕組み、実践的な施策と、総合的にSEO知識を解説してきました。
そんな記事本編でも触れられなかった「疑問を抱きやすいトピック」を、よくある質問としてまとめたので、参考にしてください。
Q:SEO対策の効果が出るまでにどのくらいかかる?
SEOの効果はすぐには出ず、一般的に3か月〜半年ほどかかるといわれています。
これは、Googleのクローラーが巡回し、評価が検索順位に反映されるまで時間を要するためです。
特に競合が多いジャンルや、新規ドメインでは成果が出るまで、さらに長引くこともあります。
SEO対策は、後に安定した成果を得るために、先行投資をするという考え方が必要です。
Q:Googleのコアアップデートって何?
Googleは、年に数回、検索アルゴリズムを大規模に見直す「コアアップデート」を実施しています。
これにより順位が急に変動することがあり、上位にいた記事が落ちたり、新しい記事が台頭することもあります。
「コアアップデート」のたびに自分のSEO知識もアップデートさせて、コンテンツの改善を図っていくことが、SEOで安定して上位を維持するために求められています。
Q:東京のSEO対策会社の方がいいですか?
SEO会社は東京に多く集まっていますが、必ずしも東京の会社が優れているわけではありません。
SEO業務はオンラインで完結する部分が大半なので、地方の会社でも十分対応可能です。
重要なのは「実績」「説明のわかりやすさ」などの本質的な中身です。
料金体系が不透明な会社や、短期の成果を謳う会社には注意が必要です。
立地にこだわるよりも、自社に合った信頼できるSEO対策会社を見極めることが大切です。
Q:SEO対策とリスティング広告はどちらを優先すべき?
SEO対策とリスティング広告は役割が異なります。
即効性を求めてすぐにアクセスを増やしたいなら、リスティング広告が適しています。
一方で、SEOは効果が出るまで時間はかかりますが、長期的に安定した集客が可能です。
広告で短期的な流入を確保しつつ、並行してSEO対策を勧めるという考え方もあるので、自社に見合った方法を選ぶことが求められます。
まとめ:SEOの仕組みを理解してSEO対策で高い成果を出そう
SEOとは「検索エンジン最適化」のことで、Googleの検索結果で上位を獲得し、安定した集客につなげるために欠かせない施策です。
本記事では、SEOの基本的な仕組みから、順位が決まる流れ、具体的なSEO施策、メリットデメリットまで、網羅的に解説しました。
SEO対策は、すぐに結果の出るものではありませんが、正しく取り組めば長期的なアクセスを増やし、売上やブランド力を高める資産となります。
上位を狙うには、検索意図を満たす高品質なコンテンツ作成、内部施策の改善、アルゴリズムの変化に適応した運用が求められます。
まずは、本記事で紹介したSEO内部施策のチェックリストや、SEO記事の書き方などを参考に、できることから始めていきましょう。
どうしても自分だけでは難しいようなら、SEO対策会社に依頼するのも一つの手段です。
正しいSEO知識と、それを継続して実行できる環境を選んで、上位を目指しましょう。

