AIO・SEO
AIO・SEOブログ
ホームページコラムの書き方とは?SEO対策や作り方のコツも例文付きで解説
2025.11.12 SEO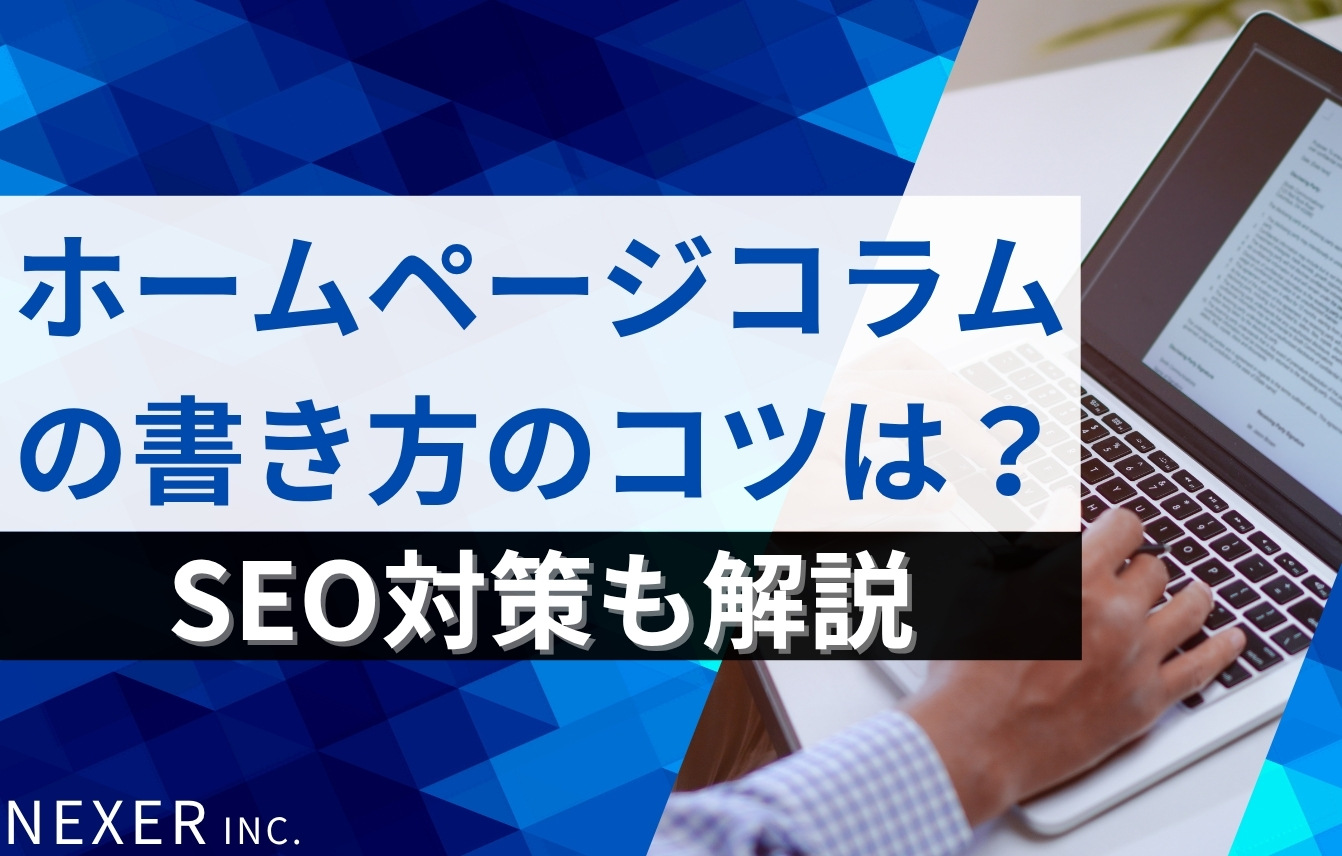
この記事の監修SEO会社

株式会社NEXER
2005年にSEO事業を開始し、計5,000社以上にSEOコンサルティング実績を持つSEOの専門会社。
自社でSEO研究チームを持ち、「クライアントのサイト分析」「コンテンツ対策」「外部対策」「内部対策」「クライアントサポート」全て自社のみで提供可能なフルオーダーSEOを提供している。
SEOのノウハウを活かして、年間数百万PVの自社メディアを複数運営。
企業のHPにコラム記事を載せたいけれど、「何を書けばいいのかわからない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
実は、コラムは検索からの集客や信頼性アップにつながる重要なコンテンツです。
テーマ選びや構成、キーワードの入れ方、読みやすい文章の工夫など、いくつかの基本ポイントを押さえるだけで、成果につながる記事が書けます。
そこでこの記事では、初心者でも迷わず始められるコラム記事の書き方とSEO対策のコツを、具体例を交えながらわかりやすく解説します。
文章に自信がない方や時間がない方にも活用できる実践的な方法を紹介しているので、HPの運用をこれから強化したい方に役立つ内容です。
SEO業界20年、取引実績5,000社で多種多様な企業様の課題解決と成長をサポートしてまいりました。
完全内製の一貫体制でSEO支援を行い、専属のSEO研究チームが「分析→実装→検証→改善」 のサイクルを高速で回します。
問い合わせ増加・ブランディングを全力でサポートいたします。
目次
- 1 コラムとブログ、エッセイとの違い・役割とは?
- 2 企業ホームページにおけるコラムの役割とは?
- 3 企業ホームページコラムの書き方を知る前に準備すべきことは?
- 4 企業ホームページコラムの作り方とコツとは?
- 5 コラムを書くのが難しい・時間がない場合の対策とは?
- 6 ホームページコラムの対策ならNEXERのAI-SEO Studioがおすすめ
- 7 【例文あり】企業ホームページコラムの執筆で活用できるテクニックとは?
- 8 企業ホームページコラムでのSEO対策でやってはいけないこととは?
- 9 「SEO 対策 コラム」「コラム 書き方」に関するよくある質問
- 10 企業ホームページのSEOコラムの書き方まとめ
- 11 お問い合わせ
コラムとブログ、エッセイとの違い・役割とは?
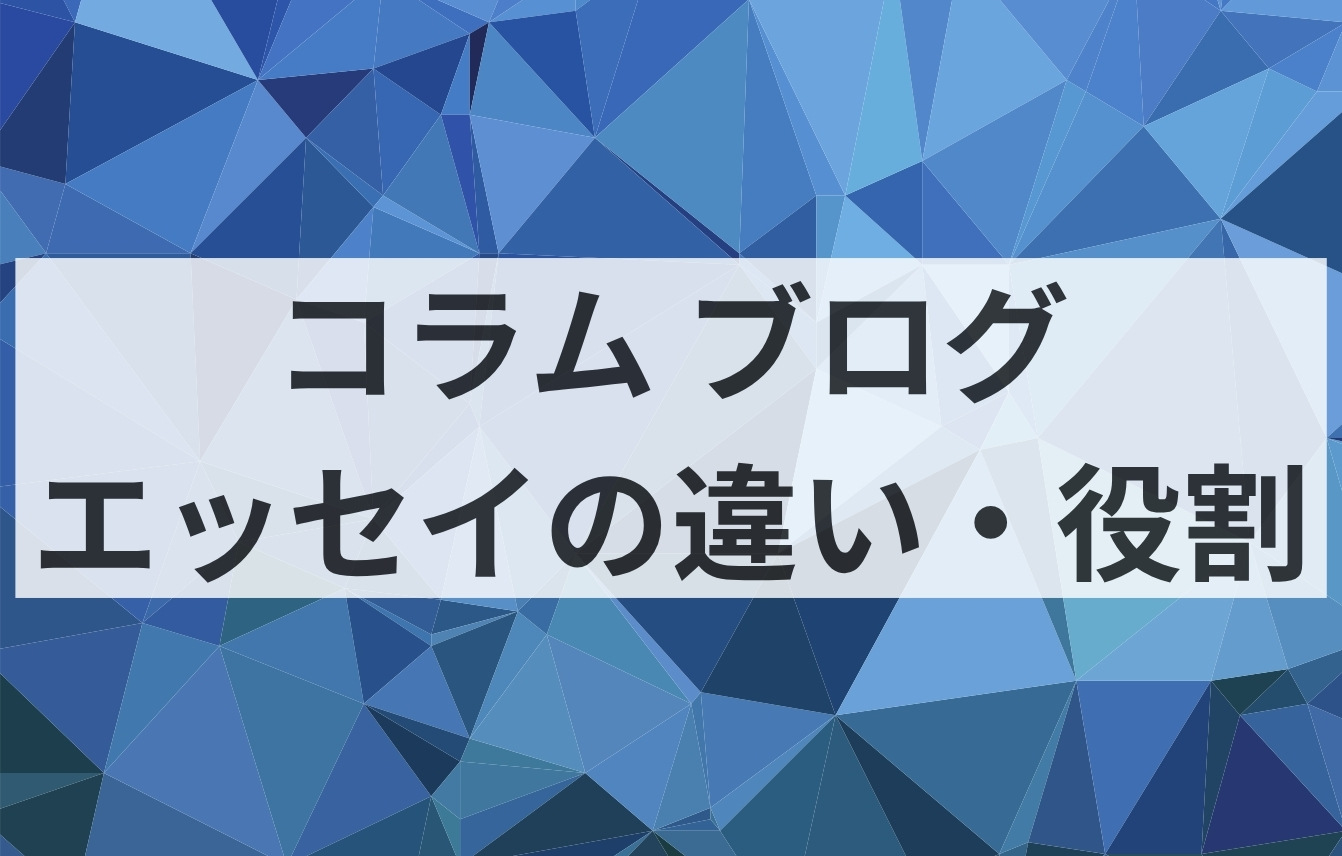
コラム・ブログ・エッセイは一見似ていますが、目的や内容の方向性、SEOとの相性が大きく異なります。
以下の表に主な違いをまとめました。
| コラム | ブログ | エッセイ | |
|---|---|---|---|
| 主な目的 | 情報提供・専門知識の発信・検索流入の獲得 | 個人や企業の日常・活動の発信、情報共有 | 自由な意見・感想・体験を表現する |
| 読者の想定 | 特定の悩みや疑問を持つ読者、見込み客 | ファン・顧客・関係者 | 興味を持つ一般読者 |
| 内容の方向性 | 専門性・信頼性を重視した客観的な内容 | 運営者の目線で柔軟に情報を発信 | 書き手の主観や感情を中心に展開 |
| SEOとの相性 | 高い(テーマ選定や構成次第で検索流入を狙える) | 中程度(更新頻度や話題性によっては有効) | 低い(検索キーワードに合わないことが多い) |
| ビジネスでの活用 | 集客・問い合わせ獲得の柱になる | 企業の顔や情報発信ツール | 企業サイトではあまり使われない |
Googleは、検索ユーザーの疑問に的確に答える情報を重視して評価します。
そのため、専門的なテーマを設定し、構成を整理して書かれたコラムは上位表示されやすく、検索経由の集客に直結しやすいでしょう。
一方、日記のようなブログや感想を中心としたエッセイは、検索キーワードと内容の一致度が低く、流入が安定しない傾向があります。
企業ホームページにおけるコラムの役割とは?
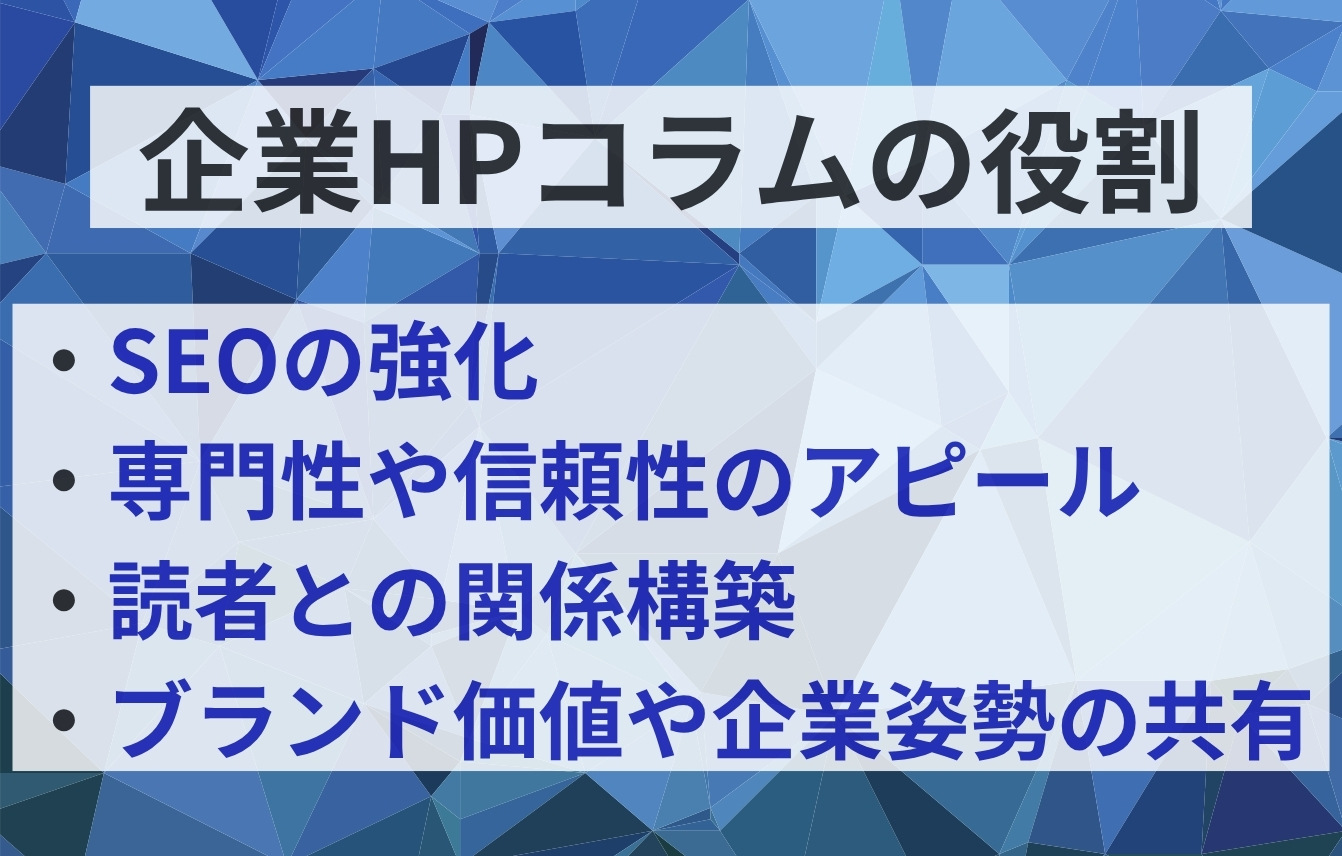
企業ホームページのコラムは、サイトの価値を高めるうえで欠かせない要素です。
単に情報を発信するだけでなく、検索からの流入を増やし、企業の魅力を多角的に伝える役割を持ちます。
例えば、以下のような効果が期待できます。
- 検索流入(SEO)を強化する
- 自社の専門性や信頼性をアピールする
- 読者との関係性を深める
- ブランド価値や企業姿勢を伝える
定期的なコラム更新は、検索対策とブランディングの両面から、サイト全体の成果を底上げする有効な手段です。
SEO業界20年、取引実績5,000社で多種多様な企業様の課題解決と成長をサポートしてまいりました。
完全内製の一貫体制でSEO支援を行い、専属のSEO研究チームが「分析→実装→検証→改善」 のサイクルを高速で回します。
問い合わせ増加・ブランディングを全力でサポートいたします。
検索流入(SEO)を強化する
コラムを定期的に作成・更新すると、検索エンジンにサイトの情報が蓄積され、関連するキーワードで上位に表示されやすくなります。
その結果、広告に頼らず安定したアクセス増加が見込めるというわけです。
Googleは、利用者の疑問や悩みに答える内容を高く評価する傾向があります。
例えば、企業の商品やサービスに関する悩みを解決するテーマを設定し、わかりやすく丁寧に説明するコラムを積み重ねると、検索結果に表示されるページが増え、ホームページ全体の評価も高まるでしょう。
これは、単発の記事では得られない効果です。
自社の専門性や信頼性をアピールする
企業のホームページにコラムを掲載する大きな目的の一つは、自社の専門性や信頼性を伝えることです。
これは、商品やサービスを選ぶときの判断材料として非常に重要な要素です。
例えば、専門用語をやさしく解説したり、現場での実践例を紹介したりすることで、読者はその企業が持つ知識の深さや経験の豊かさを自然と感じ取れるようになります。
また、専門的な内容を丁寧に発信している企業ほど、検索エンジンからの評価も高まりやすくなるでしょう。これは、信頼できる情報源として認識されるためです。
単なる宣伝ではなく、読者にとって有益な情報を届けることで、長期的な集客やブランドの強化にもつながります。
読者との関係性を深める
検索流入や専門性の発信だけでなく、読者との関係性を深めるうえでも大きな効果があります。
読者は、ただ商品やサービスの情報を得たいだけではなく、「どんな考えを持つ会社なのか」「自分と価値観が合いそうか」といった点にも関心を持っています。
そこで、企業の視点から役立つ情報や具体的なエピソードを交えたコラムを届けると、単なる情報提供にとどまらず、読者との心理的な距離を縮めることができます。
文章のトーンやテーマ選びを工夫すれば、硬い印象を与えずに企業の人柄や姿勢も伝えられるでしょう。
例えば、地域密着型の飲食店が「食材の仕入れ先」や「料理に込めた想い」をコラムで発信することで、常連客以外の読者からも共感の声が多く寄せられ、SNSでの拡散やリピート来店につながる、といったことも期待されます。
ブランド価値や企業姿勢を伝える
企業のホームページにコラムを掲載することは、ブランド価値や企業姿勢を伝えるうえでも大きな役割を果たします。
これは、競合との差別化にもつながる重要なポイントです。
昨今の消費者は、価格や機能だけでなく、その企業がどのような姿勢で社会と向き合っているかにも注目しています。
例えば、環境への取り組みや地域貢献、社員の働き方への配慮などをコラムで紹介することで、「この会社は信頼できる」「共感できる」という感情が生まれ、長期的なファンや顧客の獲得にもつながるでしょう。
企業が持つ理念や想いを文章で発信することは、広告では伝えきれない“人となり”を伝える有効な手段です。
企業ホームページコラムの書き方を知る前に準備すべきことは?
効果的なコラムを作るには、書き始める前の準備がとても重要です。
やみくもに執筆を始めると、方向性がぶれたり、読者に響かないコンテンツになってしまうことがあります。
そこで、事前に整理しておくことで、文章の質と成果の両方を高められます。具体的には、以下の5つのステップが基本です。
- 読者ターゲット(ペルソナ)を明確にする
- 検索意図とキーワードを調査する
- コラムの目的を決める
- テーマやタイトル案をリストアップする
- 競合コラムを分析して差別化ポイントを見つける
これらを丁寧に行うことで、読みやすく成果につながるコンテンツを効率的に作成できます。
読者ターゲット(ペルソナ)を明確にする
企業のホームページでコラムを書く前に、まず重要なのは「誰に向けて書くのか」を明確にすることです。
読者ターゲット(ペルソナ)をしっかり設定し、年齢・職業・悩み・検索目的を具体的にイメージすることで、文章のトーンや内容を的確に合わせられるようになります。
これができていないと、内容がぼやけてしまい、読み手の心に届かないコラムになってしまいます。
例えば、同じテーマでも、経営者に向ける場合と学生に向ける場合では、説明の深さや事例の種類、使う言葉のトーンがまったく異なります。
例えば、リフォーム会社が「30代共働き世帯」をターゲットに設定し、「忙しくても手間がかからない家づくり」というテーマでコラムを展開したところ、検索からのアクセスが増え、問い合わせにもつながる、といったケースが想定されます。
このように、読者像を明確にすることで、必要とされる情報や共感を得やすくなり、結果として成果につながるコラムを作成できます。
検索意図とキーワードを調査する
コラムを書く前に、必ず行いたいのが「検索意図とキーワードの調査」です。
いくら文章の質が高くても、検索する人の意図とずれていれば、アクセスや問い合わせにはつながりません。
調査には特別なツールを使う必要はなく、Google検索で実際にキーワードを入れてみたり、検索窓に出てくるサジェスト(関連語句)をチェックしたり、検索上位の記事の見出しを参考にしたりするだけでも十分なヒントが得られます。
これによって、読者がどんな疑問を持ち、どのような情報を求めているのかを自然に把握できるでしょう。
例えば、「リフォーム 費用 相場」というキーワードを調べると、「一戸建て」「マンション」「内装」「外装」など具体的な条件を加えたサジェストが表示されます。
そこから、読者が知りたいのは「費用の目安」や「条件ごとの違い」であることが分かり、その内容を踏まえたコラムを書くことで検索結果に表示されやすくなるというわけです。
コラムの目的を決める
コラムを書く前に、最初に決めておきたいのが「目的」です。
記事を通じて達成したいゴールを明確にすることで、内容の方向性や書き方が定まり、成果につながるコラムを作ることができます。
例えば、次のような目的によって、文章構成や最後の案内(CTA)の設計が変わります。
アクセスを増やしたい
検索されやすい「お役立ち情報」を中心に、幅広い層に届く内容にする
専門性を発信して信頼を築きたい
解説や事例を交え、深い内容で専門家としての印象を強める
問い合わせや資料請求につなげたい
課題と解決策を明確に示し、最後に行動を促す流れをつくる
なお、ここで言う「CTA」(Call To Action)とは、記事を読んだあとに読者に取ってほしい具体的な行動のことです。
- 資料をダウンロードする
- 問い合わせフォームに進む
- 関連サービスのページを読む
といった「次の一歩」を案内する部分を指します。これを目的に合わせて設計することで、ただ読まれるだけでなく、ビジネスの成果につながる導線をつくることができます。
テーマやタイトル案をリストアップする
検索意図や目的に沿ってテーマやタイトル案をリストアップすることも非常に重要です。
記事を書く段階で悩まないように、あらかじめ複数の候補を考えておくことで、効率的に執筆を進められます。
また、キーワードを自然に含めつつ、読者が思わずクリックしたくなるようなタイトルを事前に考えておくことで、アクセスの伸びにもつながるでしょう。
テーマをリストアップする理由は、読者が知りたい内容を幅広くカバーし、計画的に記事を作成できるようにするためです。
思いつきで書くと、同じ内容を繰り返したり、重要な話題を取りこぼしたりする可能性があります。
競合コラムを分析して差別化ポイントを見つける
コラムを書く前の準備として欠かせないのが「競合コラムの分析」です。
差別化された内容は、読者の印象に残りやすく、結果的にアクセスや信頼の獲得にもつなが
るというわけです。
まずは競合の記事をいくつかピックアップし、見出しや構成、内容の深さなどを確認しましょう。
その上で、網羅されていない視点や、具体的な事例、自社の知見を加えることで、より価値の高いコラムに仕上げることができます。
例えば、リフォーム業界で「費用 相場」というテーマを扱う場合、上位記事の多くは金額の目安を紹介する内容が中心です。
そこで、自社の事例や地域ごとの費用差、注意点などを加えると、より具体的で独自性のある記事になります。
また、競合が扱っていないテーマを補うことで、読者にとって「他では得られない情報源」として印象づけることもできるでしょう。
企業ホームページコラムの作り方とコツとは?
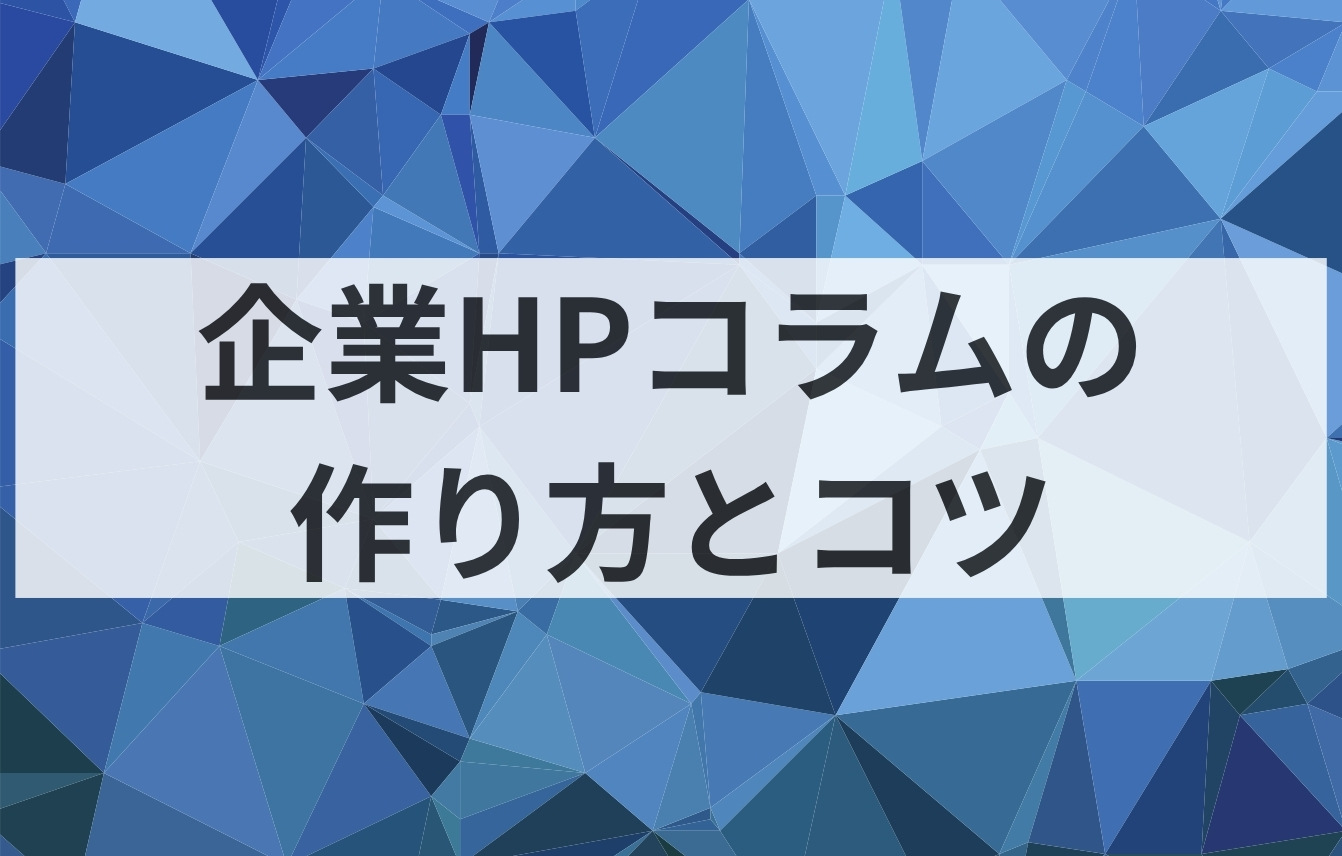
効果的なコラム記事を作成するには、内容だけでなく構成や見せ方にも工夫が必要です。
読者はサイトに訪れた瞬間、短時間で「読むか・離脱するか」を判断します。読んでもらえる記事にするための、具体的なポイントは以下の通りです。
- タイトルと導入文で読者の関心をつかむ
- SEOコラムに適した本文にする
- 見出しと段落を整理して読みやすくする
- 記事中にキーワードを自然に盛り込む
- 図表や箇条書きで情報をわかりやすく伝える
こういった基本を押さえることで、検索エンジンと読者の双方に評価される記事を作成できます。
SEO業界20年、取引実績5,000社で多種多様な企業様の課題解決と成長をサポートしてまいりました。
完全内製の一貫体制でSEO支援を行い、専属のSEO研究チームが「分析→実装→検証→改善」 のサイクルを高速で回します。
問い合わせ増加・ブランディングを全力でサポートいたします。
タイトルと導入文で読者の関心をつかむ
コラムを読んでもらうためには、まず「タイトル」と「導入文」でしっかり関心をつかむことが大切です。
導入文では、読者の悩みを提示し、「この先に解決策が書かれている」と伝えることで、続きを読みたいと思わせる流れをつくることがポイントです。
タイトルと導入文が重要な理由は、検索結果やSNSで表示されるのはこの部分だからです。
例えば、「ふるさと納税 初心者」というキーワードを狙う場合、タイトルを「【初心者でも安心】ふるさと納税のやり方と注意点をわかりやすく解説」とすると、キーワードを自然に含みながら内容が具体的に伝わります。
導入文では「ふるさと納税をやってみたいけれど、仕組みがよくわからない」という悩みを提示し、「この記事では、初心者にもわかるように基本の流れと失敗しないコツを紹介します」と書くことで、続きを読んでもらいやすくなるでしょう。
SEOコラムに適した本文にする
SEOコラムの本文では、読みやすさとわかりやすさを意識した構成が欠かせません。
特に、最初に結論を伝える「結論ファースト」で書くと、読者は短時間で内容を理解でき、途中で離脱されにくくなります。
本文を書くときの基本ポイントは以下の通りです。
- 結論を最初に書く:要点がはっきりして読み手がすぐ理解できる
- 1段落=1テーマに絞る:話が整理され、スマホでも読みやすい
- 短い文を意識する:長文を避け、テンポよく読める構成にする
- 具体例・データを活用する:内容の信頼性と厚みを高める
こうした構成が重要な理由は、多くの読者がスマホで記事を読むためです。
見出しや段落ごとに要点が整理されていれば、最後まで読んでもらいやすくなるでしょう。
見出しと段落を整理して読みやすくする
SEOコラムを読みやすくするためには、見出しと段落の「構成」をしっかり整理することが大切です。
特に、記事の見出しを設定する「h2」や「h3」は重要な役割を持っています。
「h2」「h3」とは、記事の中で見出しの階層(大見出し・中見出し)を表すタグのことで、以下のようなイメージです。
h2:大見出し(章のタイトル)
例:「企業ホームページコラムの書き方を知る前に準備すべきこと」
h3:中見出し(章の中の小見出し)
例:「読者ターゲット(ペルソナ)を明確にする」
見出しの階層を意識して整理すると、記事全体の流れがわかりやすくなり、検索エンジンにも内容が正しく伝わります。
さらに、段落を3〜4行程度でこまめに区切ると、スマホでもスッキリとしたレイアウトになり、最後まで読んでもらいやすくなります。
上記の内容をまとめると、構成を整理する際の基本ポイントは以下のとおりです。
- 見出しタグ(h2・h3)を正しく使う
内容を階層的に整理し、全体像を把握しやすくする - 段落は3〜4行で区切る
スマホでも読みやすく、視覚的にスッキリする - 見出しだけでも内容が伝わる構成にする
必要な情報がすぐ見つかる
記事中にキーワードを自然に盛り込む
SEOコラムでは、狙うキーワードを記事中に自然に盛り込むことが大切です。
ただし、キーワードを不自然に詰め込みすぎると、読みにくい文章になってしまい、かえって評価を下げる原因になるため注意が必要です。
このような工夫が必要な理由は、検索エンジンがページの内容を理解する際に、キーワードの位置や使われ方を参考にしているからです。
一方で、機械的に繰り返される言葉はスパムと判断される可能性があります。
読者がスムーズに読み進められる文脈を意識することが、結果的にSEO対策にもつながります。
そのため、キーワードは「散りばめる」意識が重要です。
- タイトルに1回入れる
- 各見出しに関連語を自然に入れる
- 本文で文脈に沿って数回使う
といった基本を守ると、読みやすさとSEOの両立が可能になるでしょう。
図表や箇条書きで情報をわかりやすく伝える
SEOコラムでは、説明が長くなりそうな部分を図表や箇条書きで整理することが重要です。
長文の中にメリハリが生まれると、スマホで読む場合もスクロールしやすくなるでしょう。
特に、複数の項目を並べて説明する場面や、比較・手順を説明する際には、図表や箇条書きが効果的です。
これは、検索上位の記事でもよく見られる基本的な構成テクニックのひとつです。
例えば、「コラム制作の流れ」を文章だけで説明すると長くなりがちですが、以下のように整理すると読みやすくなります。
- テーマ・キーワードを決める
- 構成を作る
- 本文を書く
- 図表・見出しを整える
- 公開後に分析・改善する
また、ポイントを並べるときは箇条書きを活用するのも効果的です。
- 情報を短く整理できる
- 重要な点が強調される
- スマホでも読み進めやすい
このように、文章・図表・箇条書きを適切に組み合わせると、読者が途中で飽きずに最後まで読み進めやすくなるでしょう。
コラムを書くのが難しい・時間がない場合の対策とは?
コラムを書こうと思っても、「時間が足りない」「何から始めればいいかわからない」と感じる方は少なくありません。
特に企業のホームページ運用では、継続的な記事作成が求められるため、効率化の仕組みを持っているかどうかが成果を左右する大きなポイントになります。
例えば、次のような方法を組み合わせると、負担を大きく減らせます。
- テンプレートや記事構成の型を活用する
- ネタ出しを仕組み化してストックする
- ライターを外注してコラムを作成してもらう
- SEO会社に対策を依頼する
限られた時間で成果を出すためには、自社のリソースに合った効率化の仕組みを整えることが重要です。
テンプレートや記事構成の型を活用する
コラムを書く時間がなかなか取れない場合は、テンプレートや記事構成の型を活用するのが効果的です。
毎回ゼロから文章を考えるのではなく、あらかじめ定番の流れやフレーズを用意しておくことで、作業時間を大幅に短縮できます。
この型に沿って執筆すれば、文章全体の流れが自然になり、途中で迷うことも少なくなります。
初心者でも書きやすく、複数人で執筆する場合にも内容のばらつきを防ぐことができるでしょう。
たとえば、導入部分には「〇〇で悩んでいませんか?」などのリード文の定番フレーズを用意しておくと、スムーズに書き始められます。
まとめ部分も「今回紹介したポイントを押さえれば〜が実現できます」といった定型文を決めておけば、毎回悩まずに文章を締めることができます。
ネタ出しを仕組み化してストックする
コラムの更新を続けるうえで意外と時間がかかるのが「ネタ探し」です。毎回ゼロからテーマを考えると時間がかかり、更新のハードルも上がってしまいます。
そこで効果的なのが、ネタ出しを仕組み化してストックしておくことです。
あらかじめテーマの候補をリスト化しておけば、「次は何を書こうか」と迷う時間を減らせます。
たとえば以下のような方法が役立ちます。
- お客様や取引先から寄せられる「よくある質問」をピックアップする
- 業界の最新ニュースや制度の変更をチェックして、解説記事のネタにする
- 季節やイベントに合わせた話題を年間スケジュールとしてまとめる
このように定期的に情報を集め、テーマをストックしておくことで、思いつきに頼らないコラム運用が可能になります。
たとえば、建築業界であれば「夏の台風対策」や「補助金制度の変更点」など、季節や制度に関わる話題をあらかじめ整理しておくと、繁忙期でもスムーズに執筆できるでしょう。
ライターを外注してコラムを作成してもらう
コラムを継続的に更新する時間がない場合、ライターへの外注は非常に有効な手段です。
社内の人手や時間を使わずに記事を増やせるため、限られたリソースでも継続的な情報発信が可能になります。
また、内容や分量によっては、社内で一から執筆するよりコストを抑えられるケースもあるでしょう。
ただし、外注には注意点もあります。
具体的には以下のようなリスクが考えられるでしょう。
- 内容が表面的になり、専門性や説得力に欠ける
- 構成が不十分なまま公開され、検索で評価されにくい
- 複数のライターに依頼した場合、文体や方向性がバラバラになる
例えば、複数のライターにコラムを依頼したところ、記事ごとに内容の深さや言い回しが異なり、サイト全体の統一感が崩れる、といったケースも想定されます。
これを防ぐには、発注側でテーマや見出し構成を設計し、執筆ガイドラインを用意することが重要です。
SEO会社に対策を依頼する
コラム制作を自社だけで行うのが難しい場合は、SEO会社に依頼する方法もあります。
キーワード選定から構成、執筆、効果測定まで一貫して任せられるため、社内の負担を大幅に減らしながら、戦略的なコンテンツを継続的に発信できるでしょう。
SEO会社に依頼する主なメリットは次のとおりです。
キーワード戦略〜執筆〜分析まで一括対応
→ 記事制作だけでなく、全体のSEO対策をセットで進められる
最新の検索エンジンの傾向に基づいた施策
→ 自社だけでは難しい検索上位の獲得を狙える
集客・問い合わせを意識した構成提案
→ 単なる情報提供にとどまらず、成果につながる内容になる
幅広い施策の一括依頼が可能
→ キーワード設計、サイト構造の改善、内部リンク整理、既存記事のリライトなどにも対応
一方で、以下のような注意点もあります。
- ライター外注に比べて費用が高くなる傾向がある
- 価格だけで業者を選ぶと成果が出ないケースもある
- 業界理解が浅い業者だと、表面的な内容の記事が量産される恐れがある
そのため、依頼先を選ぶ際は、実績・得意分野・運用体制を事前にしっかり確認することが大切です。
SEO業界20年、取引実績5,000社で多種多様な企業様の課題解決と成長をサポートしてまいりました。
完全内製の一貫体制でSEO支援を行い、専属のSEO研究チームが「分析→実装→検証→改善」 のサイクルを高速で回します。
問い合わせ増加・ブランディングを全力でサポートいたします。
ホームページコラムの対策ならNEXERのAI-SEO Studioがおすすめ
ホームページコラムのSEO対策を外部に任せるなら、NEXERの「AI-SEO Studio」がおすすめです。
お客様それぞれのサイトの特性や狙うべきターゲットなどを分析し、フルオーダーメイドの対策によって、費用対効果の高いコラム運用を実現できます。
株式会社NEXERは19年にわたるSEO対策の運営実績があり、これまでに5,000社以上のお客様をサポートしてきました。
一般的なSEO対策業者は下請けや外部委託に頼ることもありますが、「AI-SEO Studio」は企画から実行、検証まで完全内製化していることが特徴です。
そして、ムダを省いた、お客様ごとに必要な施策のみをご提案するので、コストを抑えながら高い効果を期待できます。
実際に「サイトへのアクセス数11倍」「問い合わせ数5倍」などの成果も出ています。
サイトの課題や改善点などを徹底的に調査いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
SEO業界20年、取引実績5,000社で多種多様な企業様の課題解決と成長をサポートしてまいりました。
完全内製の一貫体制でSEO支援を行い、専属のSEO研究チームが「分析→実装→検証→改善」 のサイクルを高速で回します。
問い合わせ増加・ブランディングを全力でサポートいたします。
【例文あり】企業ホームページコラムの執筆で活用できるテクニックとは?
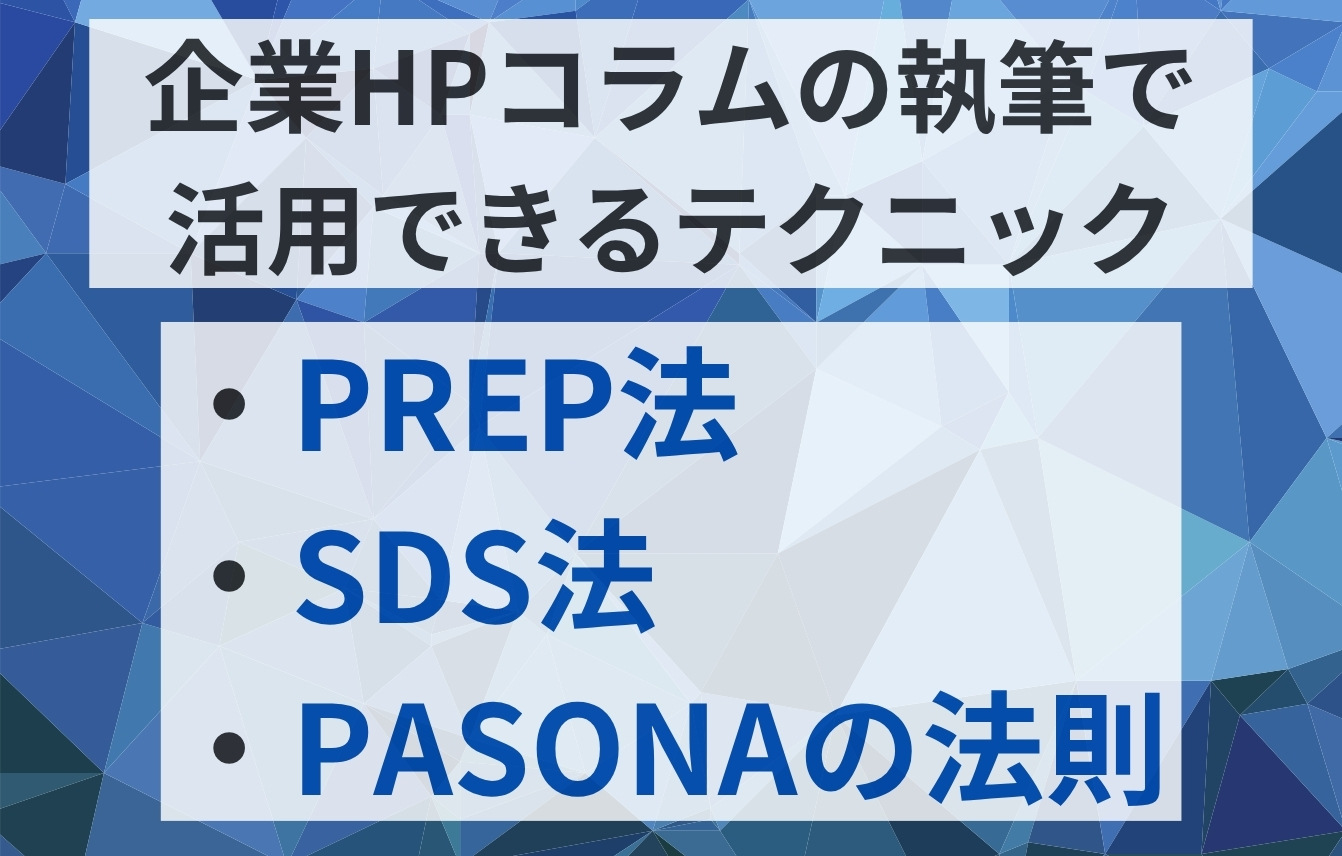
企業ホームページのコラムでは、内容をわかりやすく整理して伝える「文章構成の型」を活用すると、初心者でも読みやすく説得力のある記事を作成できます。
特に、以下のような型はSEOコラムとの相性が良く、構成に迷ったときにも役立ちます。
- PREP法(結論→理由→具体例→結論)
- SDS法(要点→詳細→要点)
- PASONAの法則(問題提起 → 共感・危機感 → 解決策 → 限定 → 行動)
- 起承転結・序破急はSEOコラムには不向き
構成の型を活用すると文章に一貫性が生まれ、読者に伝わりやすいコラムになるでしょう。
ここからは、それぞれの「型」について具体例を交えながら紹介します。
PREP法(結論→理由→具体例→結論)
PREP法は、読みやすく説得力のあるコラムを作るための基本的な文章構成です。
最初に結論を伝えるため、読者は冒頭ですぐに答えを把握でき、満足度が高まりやすいという特徴があります。
特に、忙しいビジネスパーソンや検索で情報を探している人にとって、最初に要点が提示されている文章は信頼感を持ちやすく、最後まで読み進めてもらいやすくなるでしょう。
PREP法は以下の4ステップで構成されます。
| P(Point) | 最初に結論を伝える |
|---|---|
| R(Reason) | その理由を述べる |
| E(Example) | 具体例を出して理解を深める |
| P(Point) | 最後にもう一度結論を述べて印象を残す |
例えば、「企業コラムは定期的な更新が大切です」というテーマをPREP法で書くと、冒頭で「定期更新は検索順位の安定に役立ちます」と結論を述べ、その理由として「検索エンジンは更新頻度の高いサイトを評価する傾向がある」と説明します。
その後、「週1回のコラム更新でアクセス数が2倍になった企業がある」といった具体例を挙げ、最後に再度「だからこそ、定期更新が重要です」と締める流れです。
この構成を使うことで、文章全体に一貫性が生まれ、読者に伝わりやすい内容になります。
SDS法(要点→詳細→要点)
SDS法は、短時間で情報を理解してもらいたいときに効果的な文章構成です。
最初に全体の要点を提示し、次に詳しい内容を説明し、最後に再び要点をまとめるという流れで構成します。
特に、忙しいBtoB層に向けたコラムでは短時間で内容をつかめることが重視されるため、この構成は非常に有効です。
SDS法は以下の3ステップで成り立っています。
| S(Summary) | 最初に全体の要点を簡潔に伝える |
|---|---|
| D(Details) | 次にその内容を具体的に説明する |
| S(Summary) | 最後にもう一度要点をまとめ、印象を残す |
例えば「コラム更新の頻度が検索結果に影響する」というテーマの場合、冒頭で「更新頻度が多いほど検索順位が安定しやすい」と要点を伝え、その後に「検索エンジンは新しい情報を重視する傾向があるため、定期的な更新が評価につながる」と詳細を説明します。
最後に「だからこそ、更新頻度の維持が重要」と再度まとめることで、内容を短時間で理解してもらえるでしょう。
SDS法は、結論が冒頭と末尾にあるため、途中で離脱する読者にも伝えたいポイントが届きやすいのも利点です。
PASONAの法則(問題提起 →共感・危機感 → 解決策→限定→行動)
PASONAの法則は、読み手の感情に働きかけながら自然な流れで行動を促す構成です。
問題提起から始まり、共感や危機感を示して関心を高め、解決策を提示し、限定的な提案で背中を押し、最後に行動を促します。
読者の心を動かしやすいため、後半でサービス訴求につなげたい企業コラムにもよく使われる手法です。
この構成は以下の5段階で成り立っています。
| P(Problem) | 問題提起:読者が抱える課題を明確に提示する |
|---|---|
| A(Affinity) | 親近感:同じ視点に立って共感し、課題を放置するリスクや重要性を伝える |
| S(Solution) | 解決策:課題を解決する具体的な方法を紹介する |
| O(Offer) | 提案:特典や期間限定の情報などを提示し、行動への後押しをする |
| N(Narrow down) | 絞り込み:読者に「自分に向いている」と感じさせるよう絞り込みを行う |
| A(Action) | 行動:資料請求・問い合わせ・購買など、次に取ってほしい行動を明確に示す |
例えば「コラム更新が後回しになっている中小企業」というテーマの場合、まず「更新が止まると検索順位が下がることがある」と問題提起をし、「忙しい担当者が多く、更新が後回しになるのはよくある」と共感を示します。
次に「ネタ出しを仕組み化し、月1本でも継続する方法」を解決策として提示し、「今月中の無料相談受付」といった限定的な提案を加え、最後に「まずは問い合わせフォームから相談を」と行動を促すという流れです。
起承転結・序破急はSEOコラムには不向き
起承転結や序破急といった文章構成は、物語や読み物では効果的な手法ですが、SEOコラムにはあまり向いていません。
実際に、上位表示されている企業コラムの多くは、冒頭で要点を提示し、すぐに本文で理由や具体例に入る構成を採用しています。
起承転結は、「起」で導入し、「承」で展開、「転」で視点を変え、「結」でまとめる伝統的な構成です。
序破急も同様に、序で始まり、破で展開し、急で一気に盛り上げて締める流れを持っています。
これらは読み物としての起伏があり、物語性や感情的な盛り上がりを作るのに適しているでしょう。
一方、SEOコラムはストーリーよりも「問題の解決」を重視します。
例えば「SEOコラム 書き方」というテーマで起承転結を使い、結論を最後まで引っ張ると、読者は途中で離脱し、検索結果に戻ってしまう可能性が高まるというわけです。
企業ホームページコラムでのSEO対策でやってはいけないこととは?
企業ホームページのコラムでSEO対策を行う際は、基本を押さえるだけでなく「やってはいけないこと」を避けることも重要です。
誤った手法を続けると、検索順位が下がったり、読者の信頼を失ったりする原因になります。
特に以下の3点には注意が必要です。
- キーワードを詰め込みすぎない
- 他サイトの文章をコピーしない
- 内容が薄い記事を量産しない
正しい知識を持ち、避けるべきポイントを押さえることで、長期的に成果を出せるコラム運用につながるでしょう。
SEO業界20年、取引実績5,000社で多種多様な企業様の課題解決と成長をサポートしてまいりました。
完全内製の一貫体制でSEO支援を行い、専属のSEO研究チームが「分析→実装→検証→改善」 のサイクルを高速で回します。
問い合わせ増加・ブランディングを全力でサポートいたします。
キーワードを詰め込みすぎない
SEO対策のために狙ったキーワードを盛り込むことは重要ですが、不自然に詰め込みすぎるのは逆効果です。
その理由は、検索エンジンも近年は文章全体の自然さや読みやすさを重視しており、キーワードの数よりも内容の質が評価される傾向にあるからです。
実際には、タイトルや見出し、本文の自然な流れの中でキーワードを配置すれば十分です。
言い換え表現や代名詞を使いながら、読者が違和感なく読み進められる文章を意識しましょう。
また、キーワードを詰め込みすぎると検索エンジンにスパムと判断されるリスクもあります。
Googleの公式ガイドラインでも、過度なキーワードの繰り返しは評価対象にならないと明示されているので、注意が必要です。
他サイトの文章をコピーしない
他サイトの文章をそのままコピーしたり、内容を丸写しすることは絶対に避けるべきです。
また、Googleはオリジナルの情報を重視しており、他と同じ内容の記事は検索結果で上位に表示されにくくなるというリスクもあります。
特に企業ホームページでは、信頼性の低下にもつながるため注意が必要です。
検索エンジンは文章の一致率や構成、言い回しなどを自動的に分析し、他サイトとの重複を検出します。
そのため、意図的でなくても、他社の説明文やサービス紹介をそのまま使うと重複とみなされることがあります。
また、法律的にも著作権侵害にあたる可能性があるため、リスクは小さくありません。
例えば、自社と同じ業種の企業サイトからサービス説明文をコピーして掲載した場合、一見わかりやすい文章でも検索エンジンには「独自性のないコンテンツ」と判断され、検索順位が上がらない可能性があります。
反対に、自社の言葉で言い換えたり、事例や具体的な数字を加えてまとめ直すことで、独自性が生まれ評価されやすくなると言えるでしょう。
内容が薄い記事を量産しない
文字数だけ多くても中身がなければ、検索エンジンから高く評価されることはありません。
読者にとって役立つ情報が含まれていない「内容が薄い記事」を量産するのは、SEO対策として逆効果です。
検索エンジンは、単に文字数や更新頻度だけでなく、記事の中身や読者の行動(滞在時間・離脱率など)も重視しています。
SEOでは「量より質」が基本です。
無理に記事数を増やすのではなく、1本ずつ丁寧に仕上げることが重要です。
「SEO 対策 コラム」「コラム 書き方」に関するよくある質問
コラムの書き方がわかりやすく解説されている本はどれですか?
初心者に人気が高いのは『新しい文章力の教室』(唐木元著)です。文章の基本構成をわかりやすく解説しており、「書きたいことを整理する→伝わる形に整える」という流れが実践的に学べます。
このほか『沈黙のWebライティング』(松尾茂起著)もSEOを意識した文章の書き方を学べると評判です。
文章がうまい人の特徴は何ですか?
文章がうまい人は、一文が短く主語と述語が明確です。難しい言葉を並べるのではなく、誰が読んでもすぐ理解できる言い回しを心がけています。
また、文章全体の構成にも無駄がなく、段落ごとに一つのテーマが整理されているという特徴もあります。
SEO対策でまずやることはなんですか?
まず取り組むのは、狙うキーワードの選定です。読者が実際に検索しそうな言葉をリサーチし、タイトル・見出し・本文の中に自然な形で配置することで、検索結果で表示される可能性が高まります。
誰に何を届ける記事なのかを明確にすることが、SEO対策の第一歩です。
「SEO対策 ゴミ」「SEO対策 意味ない」という意見があるのはなぜですか?
こうした意見は、誤った方法や短期的な視点でSEOを行った場合によく見られます。SEOは結果が出るまでに時間がかかるため、数週間で効果が出ないと「意味がない」と感じる人も少なくありません。
また、キーワードの詰め込みやコピペなど、昔の手法をそのまま続けているケースもあります。
企業ホームページのSEOコラムの書き方まとめ
企業ホームページのコラムは、構成やキーワード、読みやすさを意識することで集客効果を高められます。
タイトルと導入文で関心を引き、本文では結論ファースト、図表で情報を整理すると、読者に伝わりやすい記事になるでしょう。
また、キーワードの詰め込みやコピー、内容の薄い量産は避け、自社の言葉でまとめることが大切です。
自社での対応が難しい場合は、外注、専門会社への依頼も有効な手段です。
NEXERの「AI-SEO Studio」では、毎月20社限定で詳細な無料診断レポートをプレゼントしています。まずはお気軽にお問い合わせください。


