MEO
MEO記事
クリニック・病院の集客方法おすすめ8選!成功のポイントも紹介
公開日:2025/09/30 最終更新日:2025/11/28 クリニック・医療施設
クリニックや病院を安定的に経営していくためには、「集客(集患・増患)」が欠かせません。スマートフォンやインターネットの普及により、オンラインを活用した集客戦略が医療施設でも必須となってきています。
一方で、競合がひしめく都市部では、「差別化が難しい」などの悩みを抱える医療機関も少なくありません。こうした課題を乗り越えるには、患者のニーズを的確に捉え、自院の強みを効果的に発信することが重要です。
この記事では、クリニック・病院の集客に役立つ具体的な方法や成功のポイントを、事例や考え方とともにわかりやすく解説します。
目次
クリニック・病院における集客の必要性

クリニックや病院が安定して経営を続けていくためには、新規患者の獲得と、既存患者の再来の両立が不可欠です。いくら質の高い医療を提供していても、認知されなければ患者との接点は生まれません。まずは知ってもらうことが、診療の第一歩となります。
とくに新規患者の獲得は、売上や稼働率に直結し、スタッフのモチベーションや院内の活気にもよい影響を与えます。一方で、リピーターの定着はかかりつけ医としての信頼を高め、安定した経営の基盤となります。
とくに近年は、受診前にスマートフォンやパソコンで医療機関の情報を調べる患者が増加しており、WebサイトやSNSなどを活用したオンラインでの情報発信が、集客力に直結する時代です。厚生労働省の調査によれば、患者の8割以上が医療機関を選ぶ際に情報を収集しており、6割以上が「家族や知人からの口コミ」を、3割近くが「医療機関自身が発信するWeb情報」を参考にしています。
このように、口コミによる信頼性と、オンラインでの正確な情報発信の両方を組み合わせた集客戦略が、今後のクリニック経営において極めて重要だといえます。
クリニック・病院での集客が難しい理由
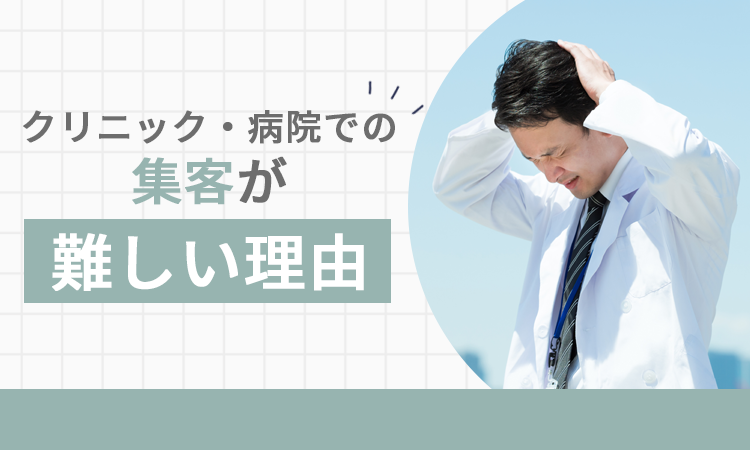
クリニックや病院において、患者を安定的に集めるのは決して簡単なことではありません。高い医療技術を有していても、地域で選ばれ続けるには「知ってもらう」「違いを伝える」「信頼を得る」といったマーケティングの視点が欠かせません。
ここでは、医療機関の集客が難しいとされる主な4つの理由をご紹介します。
- 認知度が低い
- 他のクリニックや病院との差別化を図れていない
- クリニックや病院の口コミが少ない
- オンラインで予約ができない
それぞれ具体的に解説します。
認知度が低い
そもそも、クリニックや病院の存在が知られていなければ、患者は足を運ぶことができません。とくに開業したばかりの医療機関や、立地が目立たない場所にあるクリニックは、地域住民からの認知が得られにくく、スタート時の集客に苦戦しがちです。
患者が医療機関を探す際には、スマートフォンやパソコンで「近くの内科」「〇〇市 整形外科」などのキーワードで検索するのが一般的です。しかし、ホームページがなかったり、検索結果に表示されにくかったりすると、存在そのものが埋もれてしまいます。
また、駅前などに競合が多いエリアでは、患者の目に留まる機会が少なく、実力があっても“選択肢の外”になってしまうことも少なくありません。
他のクリニックや病院との差別化を図れていない
医療機関は、競合との差別化が難しい業種のひとつです。「診療科目が同じ」「立地が近い」といった条件が重なるなかで、自院を選んでもらうためには、明確な“選ばれる理由”が必要です。
たとえば「夜間診療対応」「女性医師が在籍」「土日診療あり」「託児所あり」など、患者にとっての具体的なメリットを打ち出せているかがポイントになります。しかし現実には、公式サイトやポータルサイトに掲載されている情報が競合と似通っていたり、自院の強みをうまく伝えられていなかったりするケースが多く見受けられます。
その結果、患者から見てどの医院も似たような印象になってしまい、選ばれる確率が下がってしまうのです。差別化には、診療内容や対応だけでなく、発信の工夫も必要です。専門的な言葉ばかり並べるのではなくどんな人に、どんな価値があるのかを具体的に伝えることが求められます。
クリニックや病院の口コミが少ない
近年、医療機関を選ぶ際に口コミを重視する患者が増えています。とくに初診の患者にとっては、医療の質やスタッフの対応を事前に把握する手段が限られているため、第三者のリアルな声が信頼性を判断する重要な材料となっています。
その一方で、口コミが少ない、あるいは評価が古いまま更新されていない医療機関は、患者にとって不安材料となりやすく、来院をためらわせる原因となることもあります。とくに新規開業のクリニックや専門性の高い診療科では、口コミが自然に蓄積されにくく無評価状態が続いてしまう傾向があります。
さらに、Googleマップやポータルサイトなどに悪意のある口コミや誤解による低評価が掲載されている場合、それが放置されることでイメージダウンにつながりかねません。仮にSEO対策や広告運用によってWeb上での認知が高まったとしても「口コミがない」「評価が低い」といった理由だけで来院を避けられてしまうケースも少なくありません。
とくに医療は「健康」や「命」に関わる分野であるため、患者側は少しでも安心できる場所を選びたいと考えるのが当然です。口コミは目に見えない信頼資産です。Webマーケティング施策とあわせて、口コミ戦略を組み合わせることで、集客効果を最大化することが可能になります。
オンラインで予約ができない
スマートフォンの普及により、医療機関の予約もネットで完結させたいというニーズが急増しています。しかし、電話予約しか対応していなかったり、予約制そのものを導入していないクリニックも少なくありません。
とくに働く世代や子育て中の方にとって、診療時間中に電話をかけるのは心理的なハードルが高いためオンライン予約の有無が医院選びの決め手になることもあります。また、予約が取りづらい・キャンセルしづらいといった不便さがあると、初診の機会を逃すだけでなく、リピーター離れにもつながりかねません。
最近では、LINE予約やWeb問診など、診療前の手続きがスマホで完了できるクリニックが増えており、患者の利便性を高めると同時に、医院側の業務効率化にもつながるというメリットがあります。オンライン予約の導入は、それだけで他院との差別化になり通いやすさ=選ばれやすさにつながる大きな要素となります。
クリニック・病院における集客成功のポイント

医療機関の安定経営には、継続的な患者の来院が欠かせません。そのためには、戦略的な集客施策を実行し、自院の魅力を的確に届ける必要があります。
ここでは、クリニック・病院の集客を成功に導くために意識すべき5つのポイントをご紹介します。
- ターゲットを明確にする
- 患者のニーズを把握する
- 他のクリニックや病院との差別化を図る
- 高評価の口コミを集める
- 複数の集客施策を組み合わせる
それぞれ具体的に解説します。
ターゲットを明確にする
効果的な集客戦略を立てるには、まず誰に選ばれたいのかを明確にすることが重要です。ターゲットを決めないと、ホームページの内容も広告の訴求ポイントも曖昧になり、どの層にも響かない情報発信になってしまいます。
たとえば、同じ内科であっても「働く世代を中心に診るビジネス街のクリニック」と「高齢者の多い地域密着型の医院」では求められる役割が異なります。
前者であれば「予約のしやすさ」「診療のスピード感」「アクセスのよさ」などが重視されますし、後者では「丁寧な説明」「親身な対応」「継続的なフォロー」が求められるでしょう。このように、ターゲットを定めることは、選ばれる理由を明確にすることに直結します。
さらに、訴求の優先順位やメッセージの伝え方も、ターゲットによって変わります。ターゲット設定をする際は、次のような視点で具体化していくと効果的です。
- 年齢・性別・家族構成
- 居住地域・アクセス手段
- ライフスタイル(働いている/子育て中/高齢など)
- 医療に対する価値観(利便性重視/丁寧な対応重視など)
こうしたペルソナ(理想的な患者像)を描くことで、どのような情報発信が必要か、どのような診療体制が好まれるかといった戦略の軸が明確になります。結果として誰でもいいから来てほしいという状態から脱却しこの人に来てほしいという戦略的な集客が可能になるのです。
患者のニーズを把握する
ターゲットを明確にしたあとは、患者層のニーズを正確に把握することが、集客成功の鍵となります。医療機関を選ぶ際、患者は単に「近いから」「診療科が合っているから」だけではなく「安心して相談できるか」「通いやすいか」「スタッフの対応はどうか」といった、より感覚的・心理的な部分を重視しています。
年齢やライフスタイルごとのニーズの例はこちらです。
| 患者層 | 主なニーズ |
|---|---|
| ビジネスパーソン | 平日夜間の診療対応がある。土日・祝日も診療が可能なこと。昼休みや仕事前後に立ち寄れる診療体制となっている。 |
| 子育て世代 | キッズスペースや絵本コーナーが設置されている。授乳室・おむつ替えスペースがある。小児診療に慣れた医師・看護師の対応がある。 |
| 高齢者・シニア層 | バリアフリー設計。自宅や施設からの送迎サービスがある。待ち時間が短く、身体的負担が少ない診療体制が整っている。電話予約や紙ベースの案内にも対応している。 |
このように、年齢やライフスタイルによって、重視するポイントは大きく異なります。医療技術そのものよりも、むしろ通いやすさや人間的な対応に価値を感じる患者も多いため、これらのニーズを見逃してはいけません。
ニーズの把握とは単なる情報収集ではなく患者との対話としてとらえるべき大切なプロセスです。相手の気持ちや行動に寄り添いながら、それを施策に反映できるかどうかが、差のつく集客につながります。
他のクリニックや病院との差別化を図る
医療機関は競合が多い業種です。とくに都市部や駅近のエリアでは、同じ診療科目のクリニックが複数並んでいることも珍しくありません。そのなかで選ばれるには、自院ならではの強みや特色を明確に打ち出すことが求められます。
たとえば次のような視点が差別化のポイントになります。
- 女性医師在籍/女性専用外来あり
- 小児科と内科の連携による家族診療
- 土日診療・19時以降も対応
- オンライン診療の導入
- 空気清浄機・換気設備の強化や感染症対策の徹底
差別化は単に設備や診療時間だけでなく、医師の考え方や対応方針、院内の雰囲気なども含まれます。 自院が提供できる価値を客観的に見直し他院にはない魅力をわかりやすく伝えることで、患者から選ばれる確率は大きく高まります。
高評価の口コミを集める
信頼性のある口コミは集客に有効ですが、ただ待っているだけでは好意的な口コミはなかなか集まりません。口コミは不満があるときだけ書くといった傾向があるため、意識的にポジティブな声を増やす仕組みづくりが重要です。
高評価の口コミを集めるためには、以下のような方法が効果的です。
- 診療後に口コミのお願いを案内する
- レビューページのQRコードを待合室へ掲示する
- 診療後にLINE公式アカウントやメールでレビューを依頼する
- 満足度アンケートを実施し、Webに掲載する
こうした取り組みは集めるのではなく自然に集まる環境を整えることが目的です。大切なのは、患者の声をマーケティングの材料として扱うのではなく、医院と患者との信頼関係の延長線にあるものとしてとらえることです。
また、高評価を得るには、当然ながら診療体験そのものの満足度が前提になります。受付対応、待ち時間、医師の説明、院内の清潔感といった要素がトータルで良好であることが、ポジティブな口コミにつながる土台となります。
複数の集客施策を組み合わせる
最後に大切なのが、複数の集客施策を組み合わせて運用することです。ひとつの施策だけに頼るのではなく、複数の導線を用意することで、さまざまな属性の患者にアプローチできます。
たとえば以下のような施策が考えられます。
| WebサイトのSEO対策 | Google検索で上位表示を狙う |
|---|---|
| SNS運用(Instagram・LINE公式など) | 親しみやすく継続的な接点を確保 |
| チラシ・地域情報誌 | 年配層へのアプローチ |
| 紹介カード・紹介制度の導入 | 口コミ促進 |
重要なのは、それぞれの施策を連携させて機能させることです。SNSからWebサイトへ、Webサイトからオンライン予約へと導線をつなぐことで、患者がスムーズに行動できる流れが生まれます。
単発で施策を打つのではなく、一貫した集客設計ができているかどうかが、成果に大きく影響します。施策の具体的な方法については後述します。
クリニック・病院の効果的な集客方法

近年、医療機関における集客は選ばれる時代へと変化しています。単に存在を知ってもらうだけでなく、どのようなクリニックか信頼できるかを明確に伝えることが重要です。
ここではクリニックや病院が実践すべき集客方法をオンライン・オフラインの両面から紹介します。
- MEO(マップエンジン最適化)
- SEO(検索エンジン最適化)
- SNS
- ポータルサイト
- WEB広告(リスティング広告)
- チラシ・ポスティング
- DM(ダイレクトメール)
- オフライン広告
それぞれ具体的に解説します。
なお、効果的な集客を実現するためには、これらの手法を単体で行うのではなく、複数の施策を組み合わせて活用することが不可欠です。各手法の特性を理解し、バランスよく展開することで、より多くの患者との接点を生み出すことができます。
MEO(マップエンジン最適化)
MEO「Map Engine Optimization」とは、GoogleマップやYahoo!マップ、Appleマップなどの地図サービスにおいて、自院の情報を適切に登録・管理し、検索時に上位に表示されるよう最適化する集客手法です。
スマートフォンの普及により「近くの内科」「〇〇市 小児科」などの検索をするユーザーが急増しています。Googleではこのようなローカル検索がとくに重視されており、検索結果には地図と一緒に周辺の医療機関が一覧で表示されます。そこに表示されるかどうかは、クリニックの認知・来院に直結する重要なポイントとなっています。
MEO対策としてはGoogleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)に正確な情報を登録し、診療時間や住所、電話番号、院内写真などを定期的に更新することが基本です。加えて、患者からの口コミを集めたり、投稿機能でお知らせやコラムを発信したりすることで、Googleからの評価が高まり、検索結果の上位に表示されやすくなります。
地域密着型のクリニックにとって、MEOはもっとも費用対効果の高い集客施策のひとつです。競合よりも早く・丁寧に取り組むことで、大きな成果を得られる可能性があります。
SEO(検索エンジン最適化)
SEO「Search Engine Optimization」とは、Googleなどの検索エンジンで自院のホームページが上位に表示されるように工夫する施策です。キーワード検索からのアクセスを増やすことで、Web経由の集客につなげることができます。
検索エンジンの主流はGoogleです。日本国内でも大多数のユーザーがGoogleを利用しており、SEO施策の多くはGoogleのガイドラインやアルゴリズムに沿って最適化されます。
たとえば「〇〇市 小児科 予防接種」という検索キーワードに対して、自院のホームページ内に関連性の高い情報を掲載しておくことで、検索結果に表示されやすくなります。
このようにして検索ユーザーのニーズを取り込み、来院という行動につなげていくのがSEOの基本的な考え方です。
医療機関におけるSEOでとくに大切なのは医療広告ガイドラインを厳守することと、地域性と専門性を活かした独自コンテンツの制作です。具体的には、以下のような情報が有効です。
- 実際の診療事例(症例紹介)
- 医師やスタッフによるコラム、健康情報の発信
- 診療時間やアクセスなどの地域密着型情報
また、テキスト情報だけでなく、スマートフォンで見やすい構成や読み込み速度の最適化など、技術面の対応(モバイルフレンドリー・表示速度対策など)も集客効果に影響します。SEOは効果が出るまでに一定の時間がかかりますが、長期的に安定した集客チャネルとなるため、地道に取り組むことで成果が見込める施策です。
SNS
SNS「Social Networking Service」は、現代の情報発信において欠かせないツールのひとつです。とくに若年層は、検索エンジンよりもSNSを通じて情報を得る傾向が強く、クリニックの選定にもSNS投稿を参考にするケースが増えています。
代表的なツールにはInstagramやX(旧Twitter)、Facebook、LINE公式アカウントなどがあり、それぞれに異なるユーザー層が存在します。日常の様子をこまめに発信することで「この病院は開かれた雰囲気だな」「先生やスタッフが感じよさそう」といった印象を与えることができ、初診への心理的ハードルを下げる効果も期待できます。
さらに、SNSは双方向のコミュニケーションが可能な点も大きな強みです。患者からのコメントやDMに適切に対応することで、信頼関係を築くことができ、リピートや紹介にもつながります。
ポータルサイト
ポータルサイトとは、複数のクリニックや病院の情報をまとめて掲載しているWebサイトのことで診療科目や所在地、診療時間、口コミ、医師の紹介などを検索・比較できる仕組みになっています。
多くの患者は、いきなり医院の公式サイトを訪れるのではなく、まずポータルサイトで候補を比較してから、気になるクリニックを深掘りするという行動パターンをとります。つまり、ポータルサイトに掲載されていない、あるいは情報が古い場合は、検討の土俵にすら乗れない可能性があります。
無料で基本情報を掲載できるサービスもありますが、有料プランに切り替えることで、検索結果の上位に表示されたり、写真やコラムなどの詳細情報を充実させたりすることができます。予算に余裕がある場合は、有料掲載による露出強化も選択肢のひとつです。
とくに新規開業や診療科を増設したタイミングでは、認知度の向上と信頼構築を同時に実現できる手段として非常に効果的です。サイトによっては、インタビュー記事や医師の想いを丁寧に紹介してくれる企画ページを持っている場合もあり、医院のブランディングにも寄与します。
WEB広告(リスティング広告)
リスティング広告とは、GoogleやYahoo!などの検索エンジンにおいて、特定のキーワードで検索された際に検索結果ページの上部などに表示される広告のことです。「〇〇市 整形外科」「夜間診療 内科」など、患者のニーズが顕在化したキーワードに対して広告を出稿することで、今まさに受診を検討している層にアプローチできるのが最大の強みです。
特定のエリアやキーワードに絞って広告を表示できるため、地域密着型のクリニックにとっては非常に費用対効果の高い施策となります。また、広告効果は数値で測定できるため、表示回数・クリック率・コンバージョン(電話・予約など)といった成果指標を見ながら運用を改善できる点もメリットです。
自院での運用が難しい場合は、広告代理店やマーケティング会社に相談するのも現実的な選択肢です。
チラシ・ポスティング
チラシやポスティングは、クリニックの存在を地域住民に直接知らせることができる、非常にベーシックかつ効果的な集客手段です。とくに高齢者層やインターネットをあまり利用しない世代に対しては、紙媒体での情報伝達の方が受け入れられやすい傾向があります。
配布エリアを選定しピンポイントで訴求できる点も大きな魅力です。たとえば徒歩10分圏内のマンション群や学区内の子育て世帯など、ターゲットに合わせて配布地域を限定すれば、無駄な費用を抑えながら集客効率を高めることが可能です。
診療科目、診療時間、アクセス、医師の顔写真、院内設備の様子などを簡潔にまとめ、一目で安心感を与える構成が理想的です。また、オープンキャンペーンや検診案内などのタイミングで繰り返し投函することで、記憶に残りやすくなります。
一方で、反応率にはバラつきがあり、配布数に対してどれだけの集患効果があるかは実施してみないと分かりにくいというデメリットがあります。とくに都市部ではほかの広告物と埋もれてしまい、読まれずに破棄されてしまうケースもあります。
また、一方通行の情報発信となるため、SNSやWeb広告のように反応や分析がしづらく、PDCAを回すのが難しいという課題もあります。内容・タイミング・エリア設計を慎重に行う必要があります。
DM(ダイレクトメール)
DMは、既存の患者や地域住民に対して、はがきや封書などの形式で個別に情報を届ける手法です。クリニックでは、定期健診の案内、予防接種のお知らせ、休診情報の共有、イベント開催の告知など、幅広い活用が可能です。
DMは自分宛てに届くため、チラシや広告に比べて開封される確率が高く、内容にも目を通してもらいやすいという特長があります。また、高齢者や家族ぐるみで通院する層などは、紙の情報を手元に残しておく傾向もあり、来院のきっかけづくりとして有効です。
送付対象者をリスト化し、年齢や過去の受診履歴に応じた内容でパーソナライズすることで、より高い反応率が期待できます。発送コストはかかりますが、その分、信頼感や継続的な関係構築には非常に役立ちます。
DMもチラシ・ポスティングと同様に反応率が読みにくいことや一方通行の情報発信になるというデメリットがあります。DMは既存患者との関係性維持・リピート促進に特化した手段として活用し、ほかの施策と併用することで最大限の効果を発揮します。
オフライン広告
オフライン広告とは、インターネット以外の媒体を活用して情報を発信する手法で、駅構内の看板、バス車内広告、地元フリーペーパー、ラジオ、地域情報誌など、多岐にわたるメディアが対象となります。とくに開業時や診療科の拡充など、認知拡大を目的としたタイミングで効果的な施策といえるでしょう。
駅や商業施設に設置された広告は、通勤や買い物などの生活動線上で自然に目に触れるため、クリニック名やロゴが無意識に記憶されやすいという特徴があります。これにより、ブランドの定着やイメージアップにもつながります。また、地域密着型の紙媒体やラジオなどは、地元住民に対して「信頼性」「親近感」「地域貢献性」を伝えやすいメディアでもあります。
さらに近年では、スーパーのデジタルサイネージ(電子看板)や薬局のモニター広告といった、比較的安価に展開可能な新しいオフライン広告の選択肢も増えており、予算に応じた柔軟な活用が可能です。一方で、オフライン広告にもいくつかのデメリットも存在します。
▼オフライン広告のデメリット
| 効果測定が難しい | 広告を見て実際に来院した人数を明確に把握することは困難なため、効果の可視化や改善には工夫が必要 |
|---|---|
| 一過性になりやすい | 通勤や買い物の合間に一瞬だけ目に入る広告は、記憶に残りづらく、即効性に欠ける可能性がある |
| 内容変更がしづらい | 印刷や掲出が完了した広告は、後から情報修正ができないため、キャンペーンや診療時間の変更など、流動的な情報には不向き |
そのため、オフライン広告を実施する際は、地域性・予算・目的の明確化を行ったうえで、Web広告・SNS・MEOなどのオンライン施策と併用し「認知 → 検索 → 来院」までの導線を意識した総合的な集客戦略を構築することが重要です。
クリニック・病院の集客における注意点
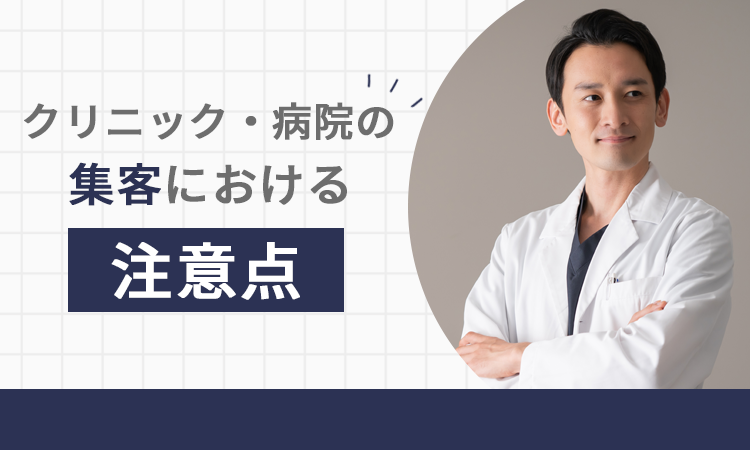
誤った情報発信や院内環境の不備があると、どれほど魅力的なサービスを提供していても患者の不信感を招き、逆効果になりかねません。
ここでは、集客を行ううえでとくに気をつけたい4つのポイントを紹介します。
- 医療広告ガイドラインに気をつける
- 窓口や看護師の対応に問題はないか
- 患者が求める説明・提案ができるか
- 院内の内装は整っているか
それぞれ具体的に解説します。
医療広告ガイドラインに気をつける
医療機関が広告やWebサイトなどで情報発信を行う際には、厚生労働省が定める医療広告ガイドラインを遵守する必要があります。とくにWeb集客では自由な表現が可能なため、知らず知らずのうちにガイドラインに違反してしまうリスクがあります。
たとえば「絶対に治る」「どこよりも安心」「全国No.1」といった表現や、患者の体験談・ビフォーアフター写真の掲載などは、内容によっては虚偽・誇大広告と判断されるおそれがあります。集客に力を入れるほど、つい強い言葉を使いたくなりますが、医療機関としての信頼性を損なわない情報発信が第一です。
窓口や看護師の対応に問題はないか
広告やホームページの印象がどれだけよくても、来院後の受付対応やスタッフの態度が悪ければ、患者の満足度は一気に下がります。とくに初診の患者にとっては、受付や看護師の第一印象がそのクリニック全体のイメージを左右するといっても過言ではありません。
「言葉遣いが丁寧か」「質問に対して親身に対応しているか」「待合室での声かけができているか」など、現場対応の質がそのまま口コミに反映される時代です。集客以前に、院内の接遇教育が整っているか見直すことも重要なポイントです。
患者が求める説明・提案ができるか
診察スキルや診断精度が高くても、患者にとって納得できる説明がなければ満足感は得られません。「専門用語ばかりでわかりづらい」「治療方針の理由が伝わってこない」といった印象は、不安や不信感につながり、リピート率の低下を招きます。
わかりやすい言葉で丁寧に説明し、複数の選択肢を提示してくれる医師には、患者も自然に信頼を寄せるものです。説明の質もまた、集客における差別化要素のひとつといえるでしょう。
院内の内装は整っているか
集客というと情報発信や診療内容ばかりに目が向きがちですが、院内環境も来院者の印象を大きく左右するポイントです。とくに初めて訪れた患者にとっては、院内の清潔感・掲示物・待合室の雰囲気などが安心感や信頼感に直結します。
壁紙が汚れていたり、照明が暗かったり、掲示物が乱雑だったりすると、それだけでマイナス印象を持たれてしまう可能性があります。また、季節感のある装飾や、患者が安心して過ごせる空間演出もまた来たいと思ってもらうための小さな工夫として有効です。
クリニック・病院の集客は「認知度を高めること」からまず始めよう
どれほど優れた医療サービスを提供していても、患者に知ってもらわなければ、来院にはつながりません。まずは認知を広げることが、集客の第一歩です。Webサイトの整備やSNSでの情報発信、口コミの活用など、オンラインとオフラインを組み合わせた認知拡大が重要です。
自院の強みや魅力を明確に打ち出し、信頼性のある情報を継続的に届けることで、地域で選ばれる存在になっていきましょう。集客は技術力ではなく伝える力から始まります。
